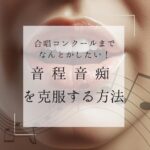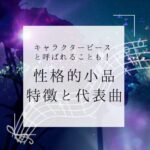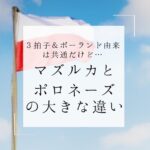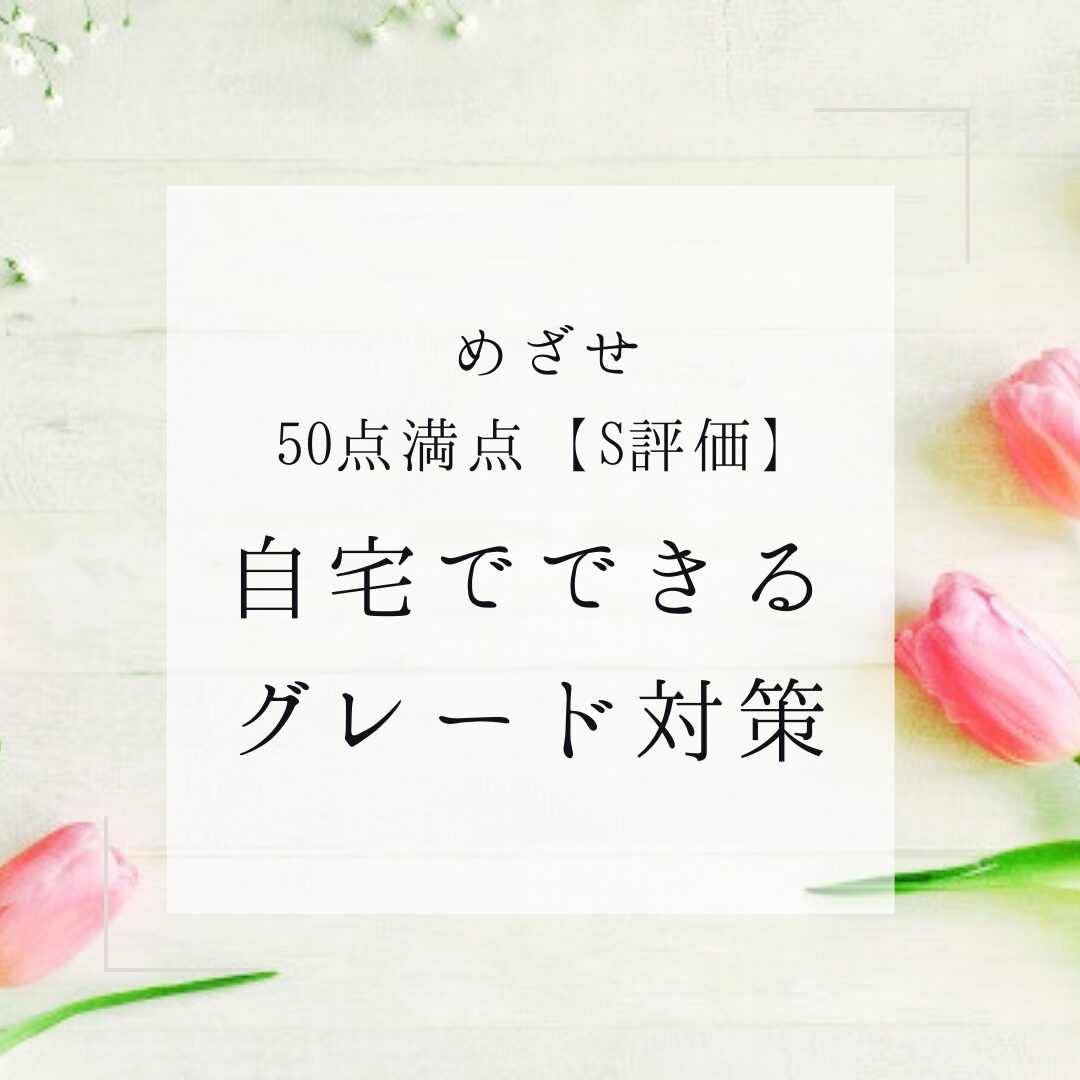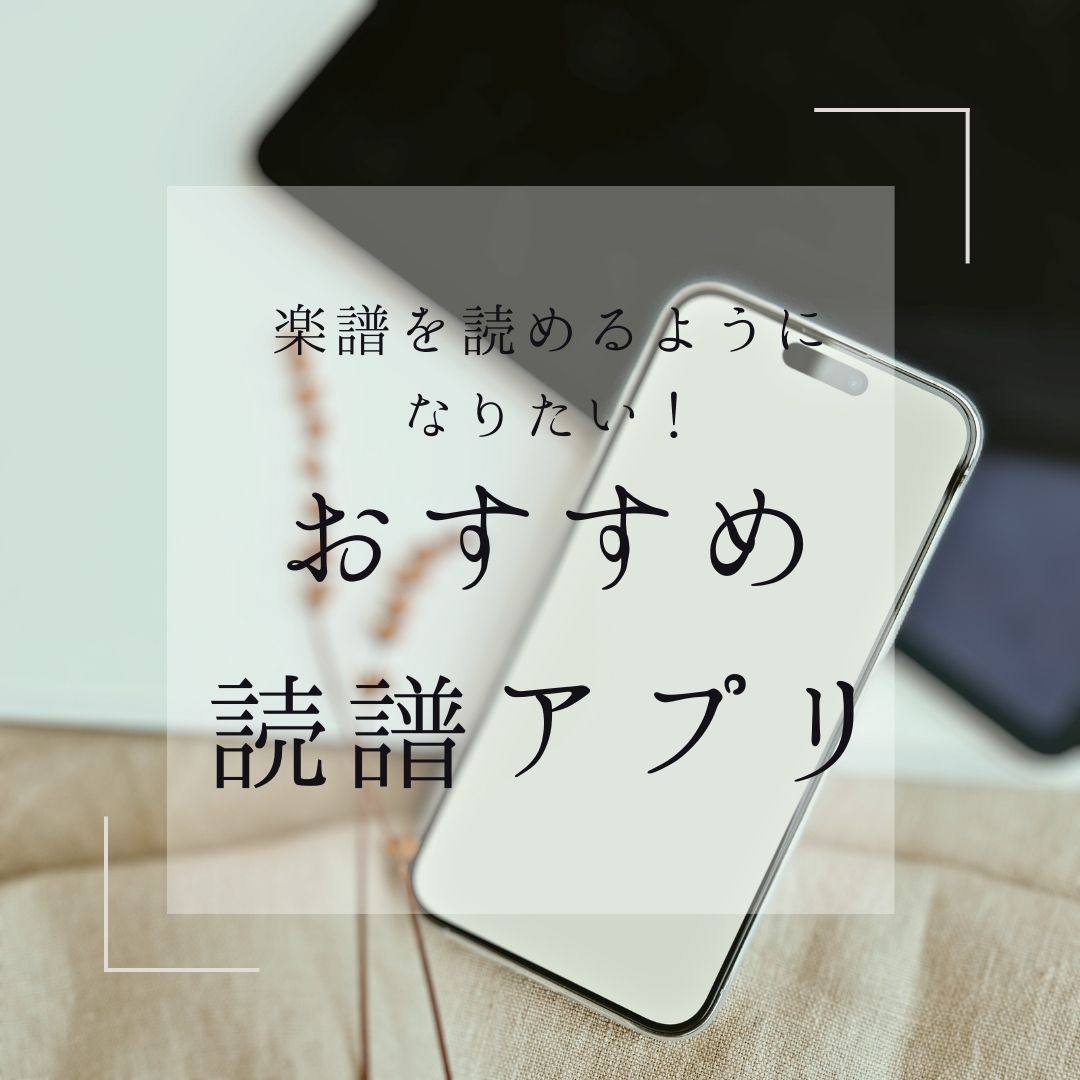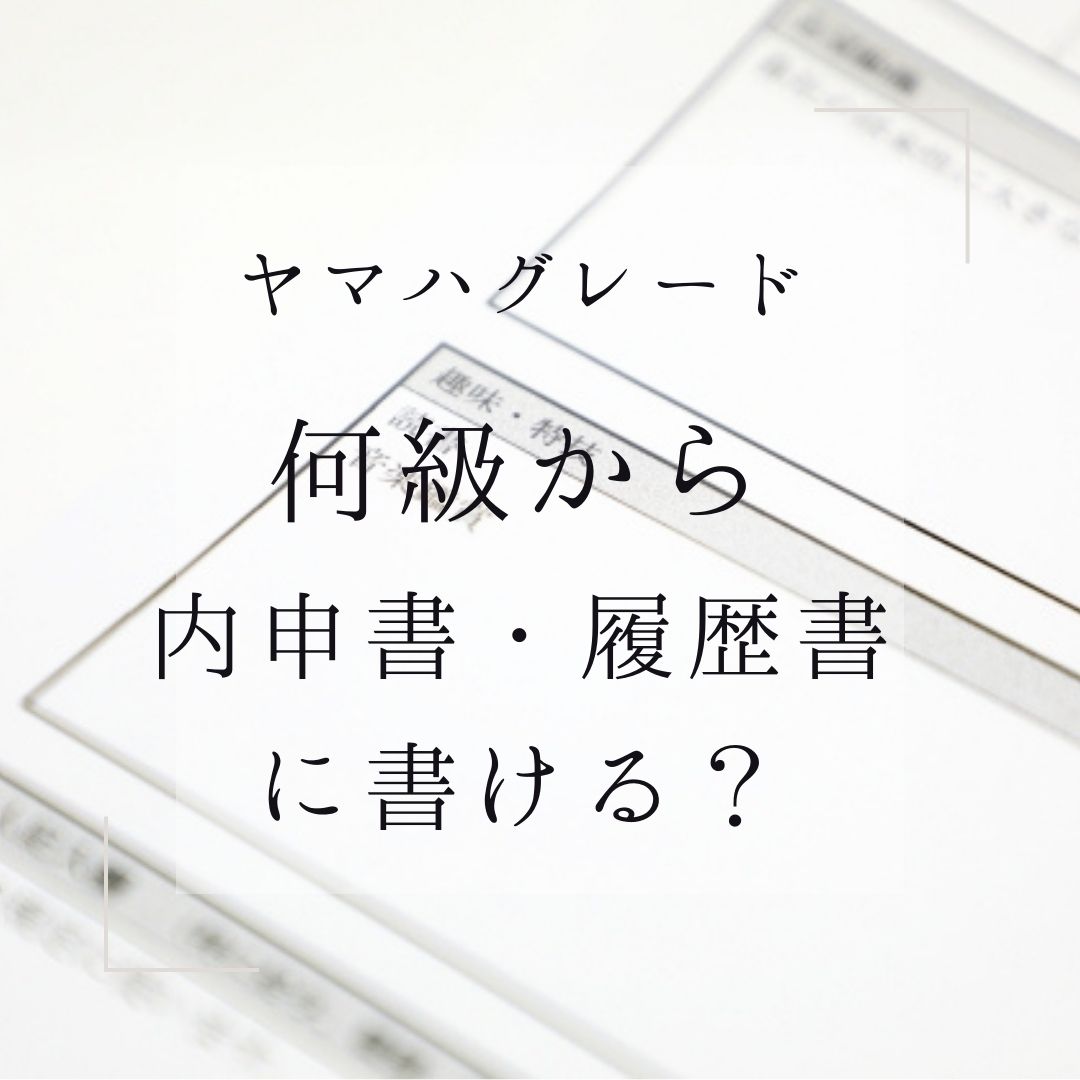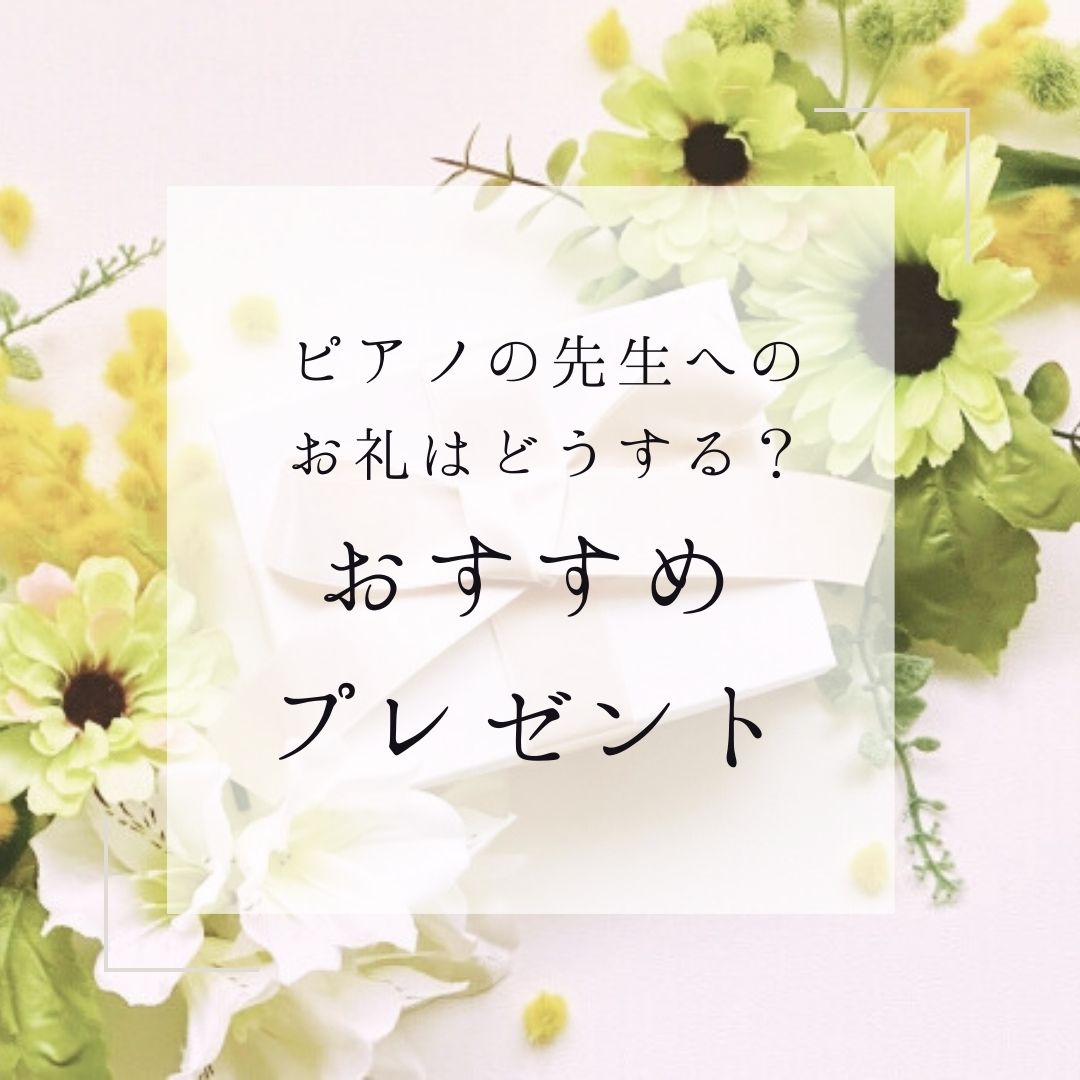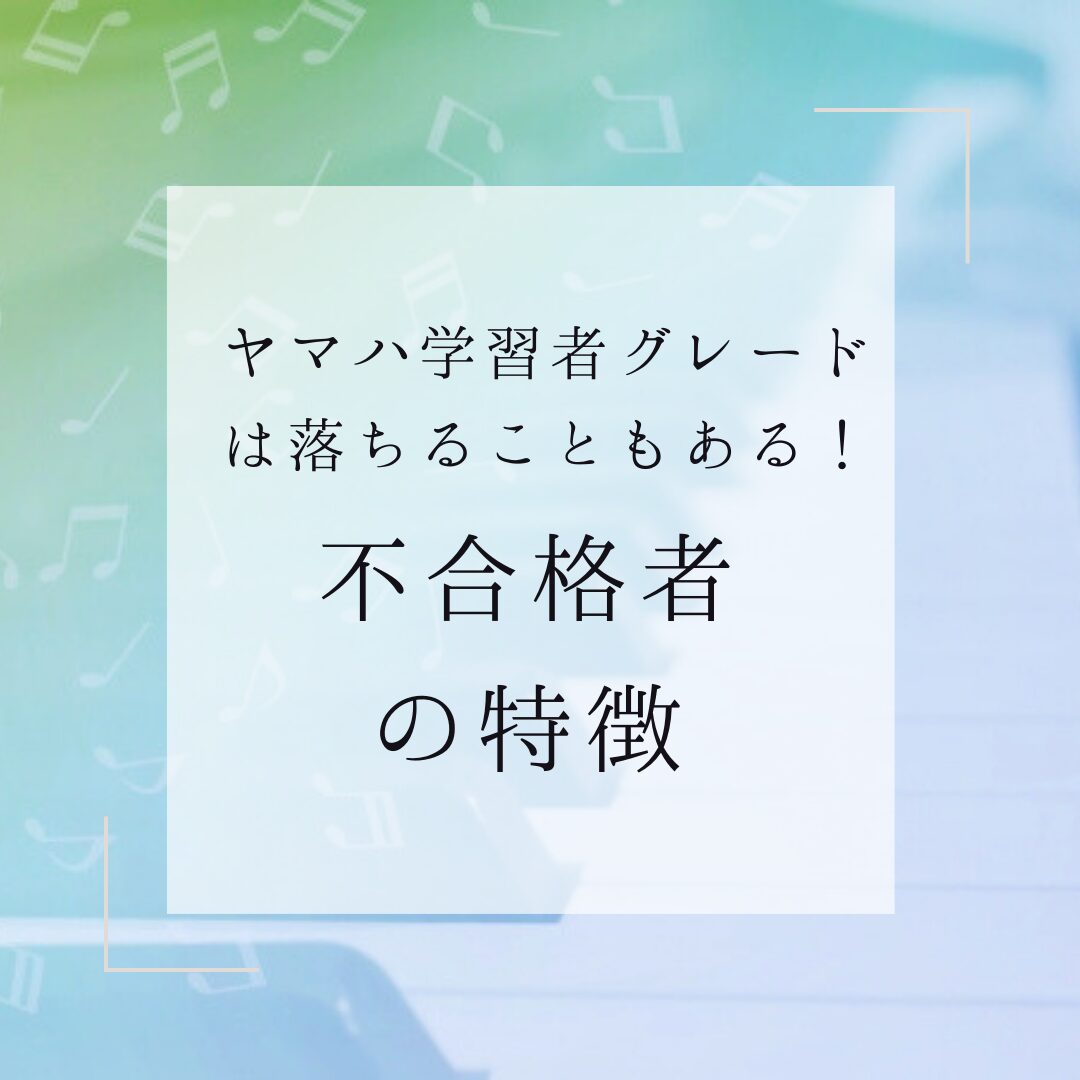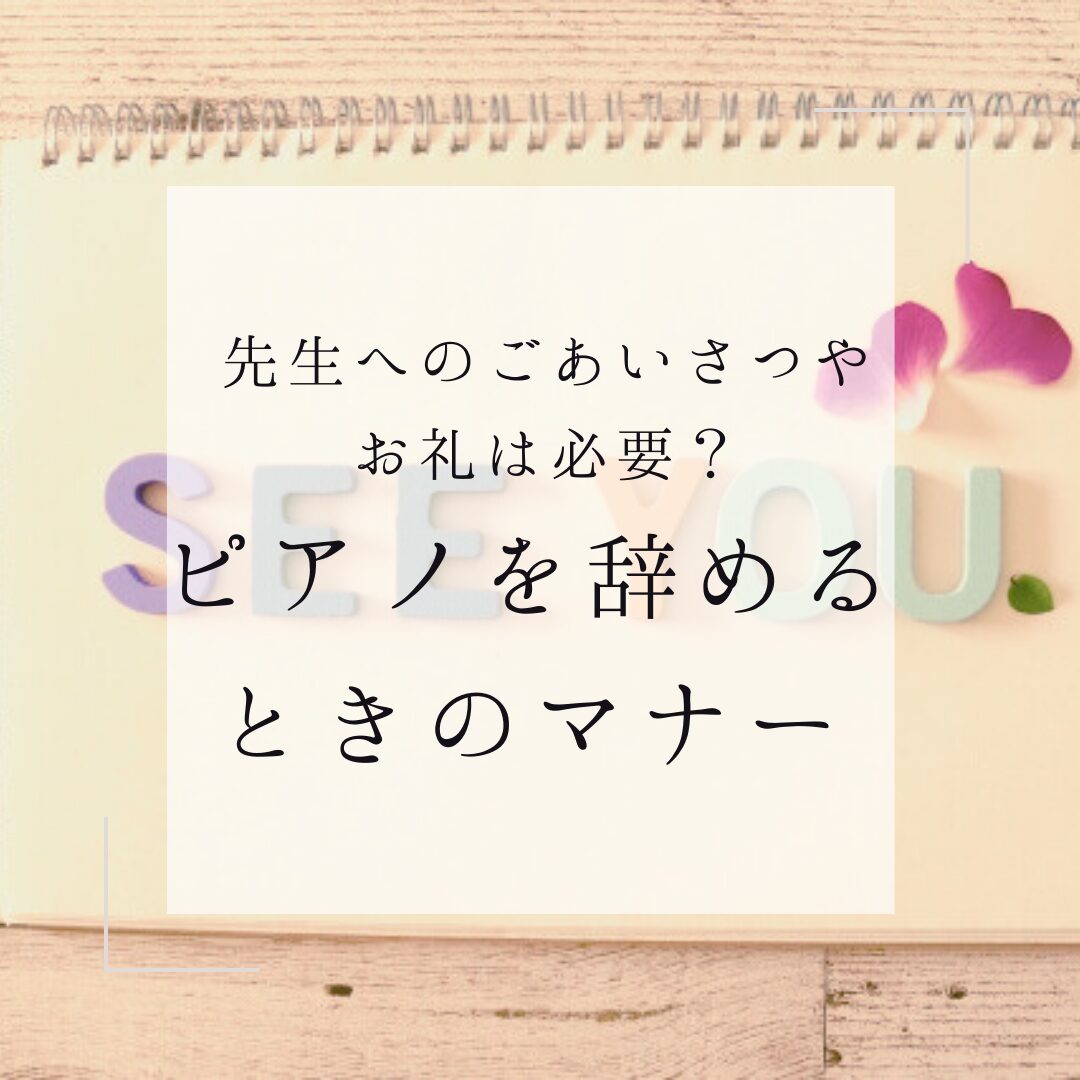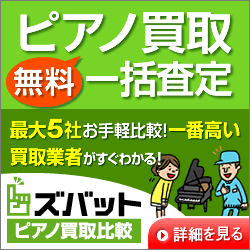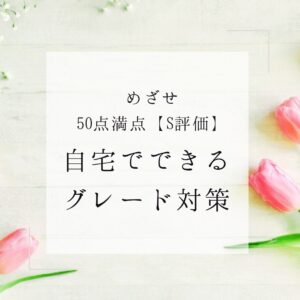ヤマハ音楽教室の生徒でも外部の生徒でも受験できる学習者演奏グレード。
なんと、ピアノ8級Bコースを受験した娘が50点満点【S評価】をとってきました!
親の私もびっくり!
この記事はヤマハ学習者グレード、ピアノ演奏で
- 50点満点をとりたい人
- S評価をとりたい人
- 高得点が出る傾向を知りたい人
におすすめです!
どんな対策をしたか、親目線と指導者目線で振り返っていきます。
参考にしてね♫
ヤマハ学習者グレード試験は49点以上が【S評価】


2018年11月以降受験分からヤマハのグレードの評価の仕方が変わりました。
それまではA~Eの5段階評価だったのですが、 新しいグレードは各項目10点で5項目満点がつくと50点 となります。
各コースの得点の内訳
ヤマハ学習者ピアノグレードにはAコースとBコースがあり、満点の50点は変わらないものの、得点の内訳がコースによって異なります。
\ AコースとBコースの詳しい得点の内訳はこちら /


点数ごとの評価
さらに合計点数に応じてS~E評価が付きます。
点数ごとの評価は次のようになっています。
| 合否 | 評価 | 点数 |
| 合格 | S | 50~49 |
| 合格 | A | 48~41 |
| 合格 | B | 40~33 |
| 合格 | C | 32~25 |
| 不合格 | D | 24~17 |
| 不合格 | E | 16以下 |
【S評価】は1点のミスしか許されない
ここからわかるようにS評価をとるには満点をとるか1点しかミスが許されないということになります。
結構厳しい・・・
私自身も生徒を受験させていますが、対策が効いたのかだんだんとS評価をいただいてくることが増えてきました!
\ AコースとBコースのサブネームの違いはこちら /


【S評価】になるために家でできる対策・練習のコツ


ここからはヤマハ・ピアノ演奏グレード8級Bコースで娘が50点満点をとったときに家で行った対策や、実際に私が自分のレッスンでグレードを受験する生徒・保護者に「自宅での練習に取り入れてほしいこと」として伝えていることをご紹介します。
「良い評価がほしい!」という方は、ぜひ参考にしてくださいね!



よーし、がんばるぞ~!!
【対策①】レパートリーはスラスラ弾けるようにする
娘は週1回のレッスンを受けていますが、グレードの時期となると30分の個人レッスンでは娘の先生もいっぱいいっぱいのようでした。
私も指導者なので分かるのですが、まずはきちんとレパートリーが弾けていないと、なかなか他の対策に時間を使えないのです。
特にBコースは初見演奏だけでなく、伴奏付けや聴奏などもあるので、レッスンは本当に時間との闘いです!
そこで、娘の先生が余裕をもってレパートリー以外に時間を使えるように、レパートリーは家でスラスラ弾けるように練習させました。
- テンポが安定しているか
- 指が転んでいないか
- 苦手な部分はないか
などチェックしてあげて、苦手なところは部分練習を繰り返し行い表現面は先生にお任せしました。
娘の話によると、
本番は止まらずにきちんと表現して弾けたけれど、2回くらいミスタッチした
ということでした。
・・・というのは、自由曲のうち1曲を自作曲の難しいものにしたためです。
小さなミスよりも、表現力やテクニックなど全体をみて評価していただいた印象でした。
ちょっとミスしてもあきらめちゃダメ!
【対策②】カデンツは毎日練習する
ピアノ8級Bコースで何が難しいかというと、ハーモニー聴奏で出てくる両手カデンツのパターンが9級と比べて劇的に増えることです。
ピアノ8級Bコースでは右手の和音が転位したものを含めて3つのポジションで出題されます。
\ 転位形がわからない方はこちら /
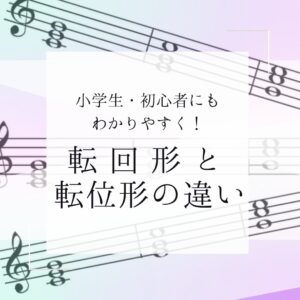
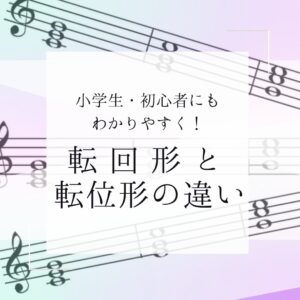
8級Bコースでは
ハ長調・ト長調・ヘ長調・イ短調・ホ短調・ニ短調が出題範囲
となっているので、6つの調×3ポジションで全部で18パターンを定着させなくてはいけないのです・・・。
しかも左手(ベース)は上行と下行のどちらにも指が移動できるようにしないといけません。
ということで、この 18個のカデンツは毎日家で取り組ませて完璧に弾けるように しました。
でも聴奏で出題されるため、ただ弾けるだけではダメ!
「3つのポジションのうちどのポジションで出題されたのか」を聴いて判別しないといけません。
そこで効果的なのが、 右手の和音の最高音(一番高い音)だけを歌いながら弾く練習 です。
私の生徒にも
- なんでカデンツ練習しないといけないの~?
- めんどくさいから嫌い~
- こんなの練習しても将来の役に立たないじゃん
このように文句を言う子います!
そんなときは、
- 合唱の伴奏するときに役に立つよ!
- 自分で好きな曲の伴奏をして弾き歌いできるようになるよ!
- 曲のクライマックスが分かってピアノでの演奏が深まるよ!
という感じで、カデンツを弾いておくメリットを話しています。
いろいろな和音をいろいろなポジションで押さえられると、伴奏譜の譜読みをするのも楽になりますよね。
「今は大変でも、あとできっといいことあるから、頑張ろう♪」と励まして、なんとか頑張ってもらっています。
\ 3つのポジションが聴きとれないときの練習法 /


\ ハーモニーの流れを聴きとる練習法 /
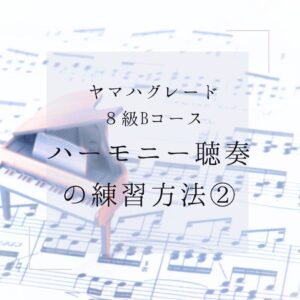
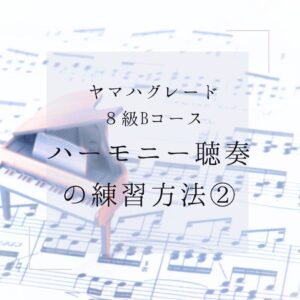
【対策③】8分の6拍子のリズムうち
8級からは9級までにはなかった8分の6拍子という拍子が登場します。
それまでは
4分の4拍子、4分の3拍子といった4分音符を1拍と数える拍子
しか経験していないので、
8分音符を1拍で数える8分の6拍子は苦手な子がとても多い
と感じています。
8分の6拍子は
- やさしいミュゼット(かわいいミュゼット)
- ふなうた
- ベニスの謝肉祭
などのレパートリーでも経験している子もいるのですが、楽譜を見てリズムをつかむというよりは、結構耳に頼っている子が多い様子。
(一応説明はするのですが・・・)
というワケで、まずは8分の6拍子に慣れることが必要です!
初見演奏で出ても落ち着いて対応できるように。
私は
- リズムカードを使う
- 簡単な8分の6拍子の曲を見せてリズムだけ打つ
- 8分の6拍子のリズムの本を使って慣れる
このような手法で対策しました。
娘のグレード対策時や自分の生徒の対策で使用した(使用している)教材は以下のものです。
\ 6/8拍子は4巻に収録!音符が大きくて見やすい♫ /
\ ♩と♪の拍の違いを丁寧に解説♫ /
\ 自分で並べたリズムを打ってもらおう! /
初見演奏で8分の6拍子が出ても慌てないように、たくさんリズム打ちをして対策しておきましょう!
ちなみに・・・実際、娘が受験したときは初見演奏で8分の6拍子が出ました!!
でも、落ち着いてきちんと拍を数えながら止まらずに弾けたそうです。
対策しておいてよかった!
【対策④】グレード問題集で練習する
現在、新しいグレードに対応している問題集は各級1冊しか販売されていません。
家でもグレードで出題される問題と同程度の内容で練習したいなら、ぜひ購入しましょう!
\ グレード受験するなら問題集はマストアイテム /
特に 初見や伴奏付けなどは問題集を見ると出題傾向が分かります。
「ここでこの形が出てきて、こう終わる」みたいな。
傾向が分かると、対策もできますよね!
問題集の初見演奏も全部終わったら、 何年か前にやっていた曲集を引っ張り出してきて、初見のように取り組む方法もおすすめ です。
受験する級の問題集に載っているくらいのレベルのものを選ぶといいですね。
昔使ったテキストに掲載されている習っていない曲がおすすめ!
\ 各級のポイントをまとめたよ /
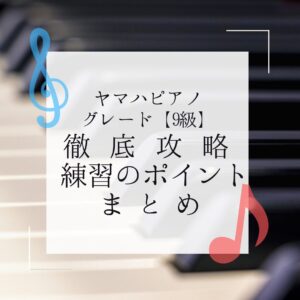
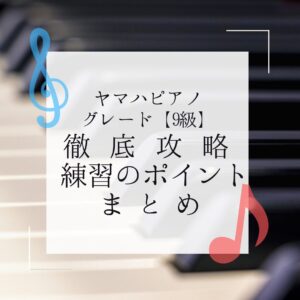
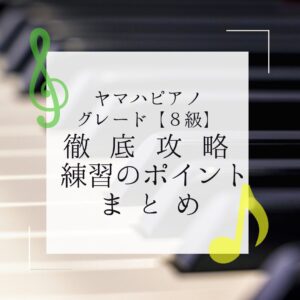
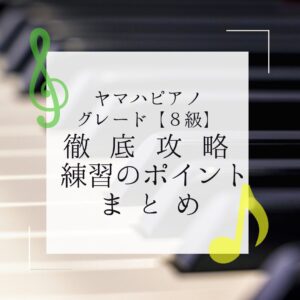
50点満点【S評価】が出やすい傾向を分析


どんな場合に50点満点やS評価が出やすくなるのでしょうか?
満点を獲得してきた娘や生徒の様子から、高得点が出やすい傾向を分析しました。
10~8級などの比較的低い級での受験
受験する級によって求められるレベルも変わるため、学習者グレードの最高レベルである6級に近くなるほど評価も辛口になっていくと予想されます。
ということは、S評価は10~8級くらいだと出やすい傾向ということになりますね!
特に7~6級は即興演奏といって初めて見るメロディーに和音をつけて、さらに変奏して弾く・・・という課題がありますし、聴奏も両手(エレクトーンなら両手&ベース)の聞き取りとなり、ミスなく余裕をもって仕上げるのはとても大変です。
BコースよりAコースの方が高得点が出やすい
Aコースは演奏中心の試験となるため、本番も落ち着いて演奏できるよう曲の練習をしっかりしていけば高得点が期待できます。
もちろん初見演奏の対策も必要です!
それに対し、Bコースは音楽総合力が必要になるため楽曲演奏以外の
- 初見演奏
- 即興演奏・伴奏づけ
- 聴奏
これらは当日どんな問題が出るかわかりません。
出題される問題によって調や拍子など得意不得意があると思いますので、対策していっても出来が左右されてしまいます。
事前に自宅で準備していけるものが多いAコースのほうが、満点に近い成績が出やすいでしょう。
AコースとBコースのどちらを受験するかは、習っている教室のシステムや講師の考えによります!
やさしい試験官・相性の良い試験官にあたる
グレードの試験官はどんな方が担当するのかは当日行ってみないとわかりません。
点数や評価は、その時担当していただく試験官の先生の判断になります。
ある程度の基準はあると思いますが、「演奏の好み」は人それぞれ。
ちょっとミスしても表現力とテクニックでカバーできていれば高得点を出してくれる先生もいますし、完成度が低いと評価して減点されるケースもあるでしょう。
緊張マックスで「やらかしちゃった~!!」と帰ってくる生徒でも、いざ結果を見てみると【S評価】や【A評価】だったケースもあります。
案ずるより産むが易しかも?
\ グレードで緊張しそうな方必見! /


家でできることをしっかり対策してグレードに臨もう!


グレードはとっても緊張します!
私も生徒時代、発表会やコンクールより緊張して受験していたのを覚えています。
生徒のなかには「試験官が目の前にいるから余計緊張する」という子もいました。
それでもカデンツの練習やレパートリーの練習など、家で対策できることをしっかりやっておけば、レッスンもグレード当日も余裕をもって受けることができるはず。
特にカデンツは量も多いので「一度に全部」ではなく、「まめにコツコツ」練習することが大事です!
落ち着いてグレードに臨もう♪
\ 各級のポイントをまとめたよ /
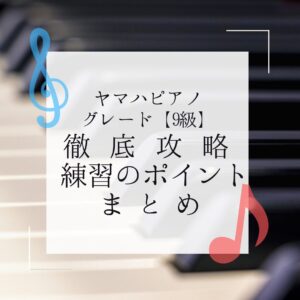
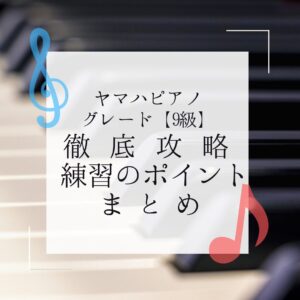
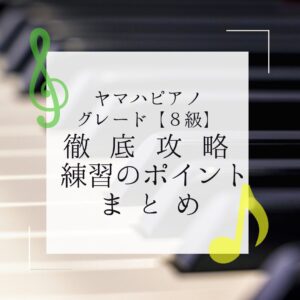
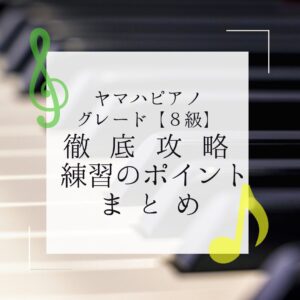
\ グレードってなんで受けるの? /


この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿