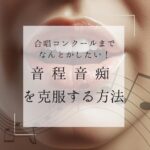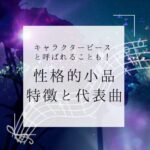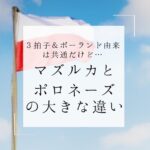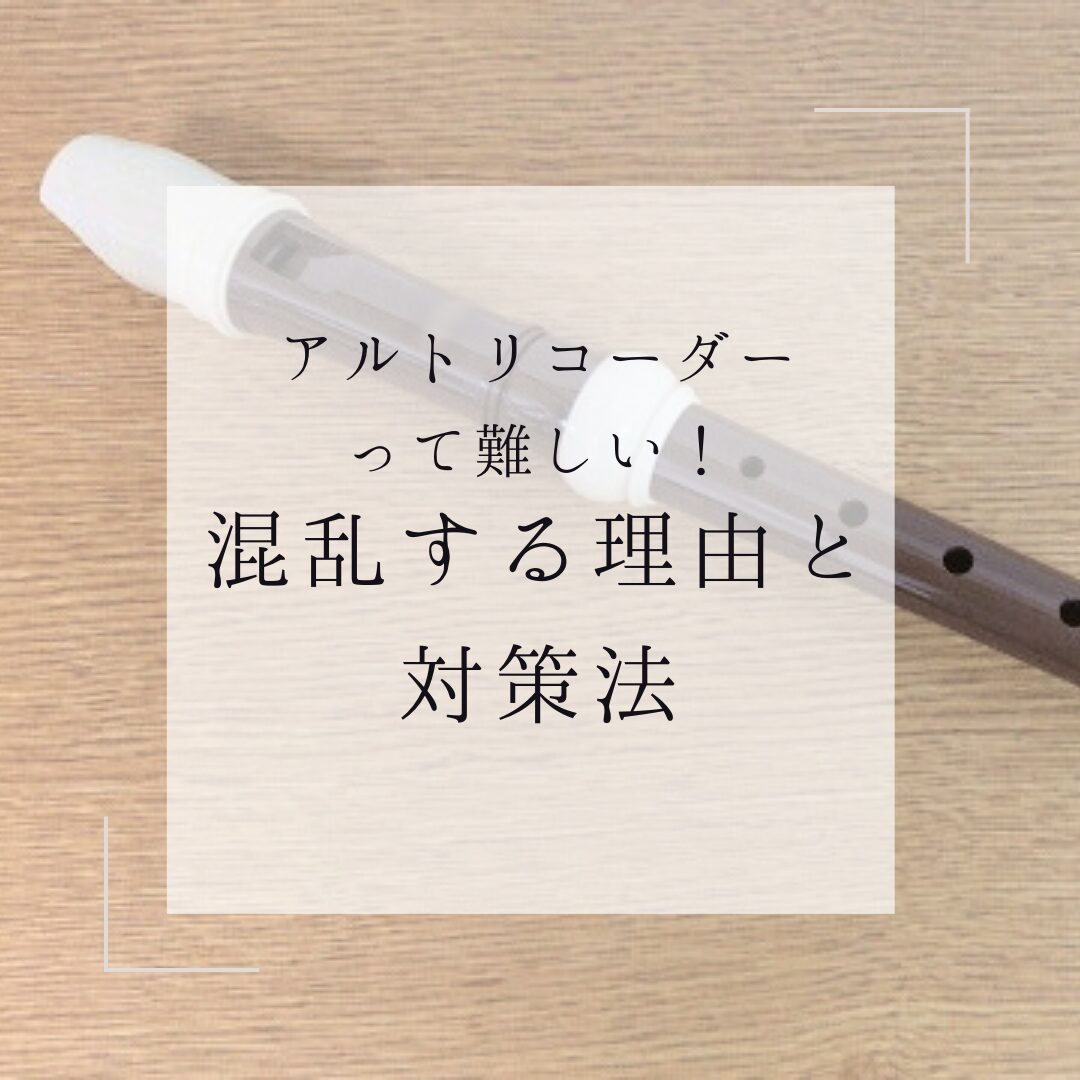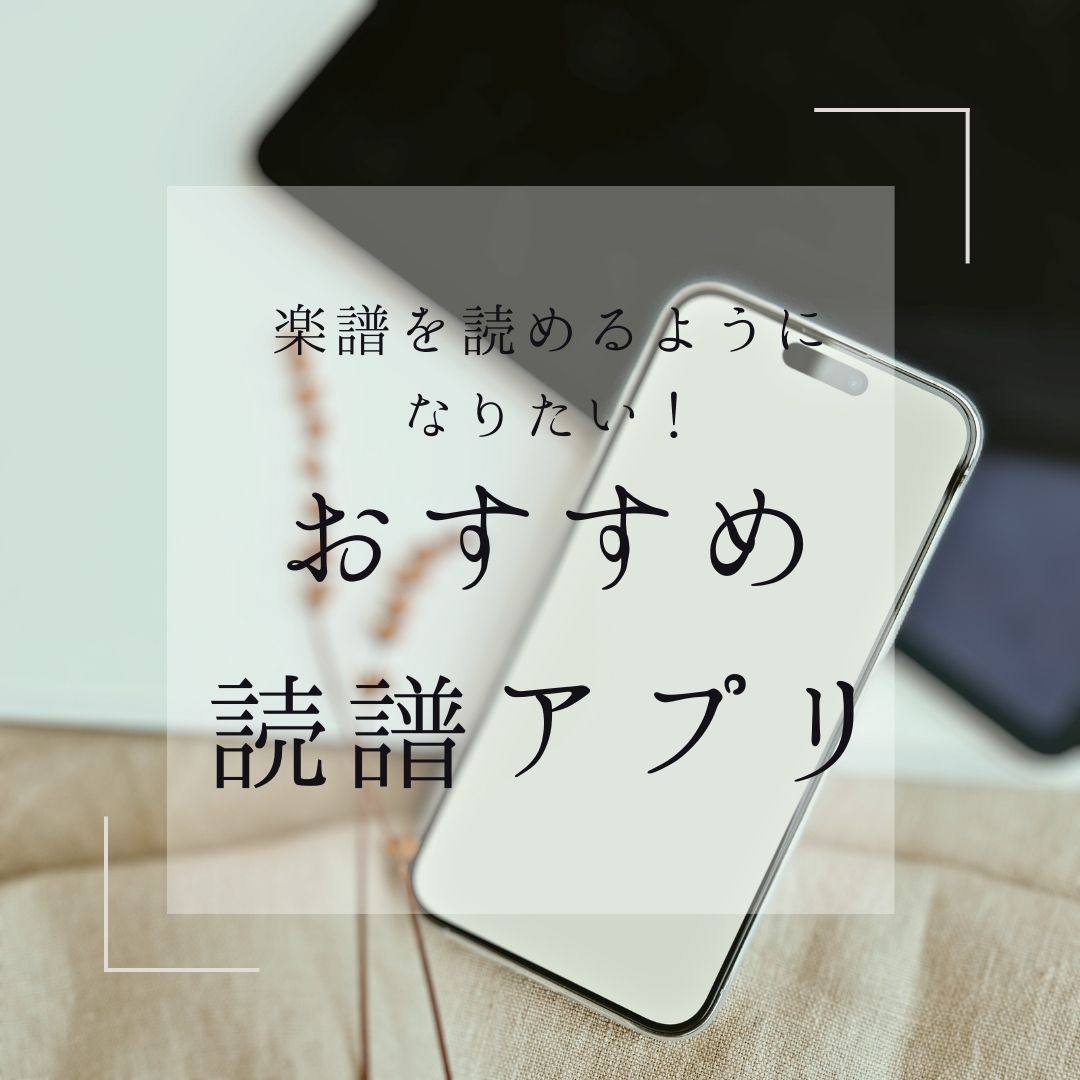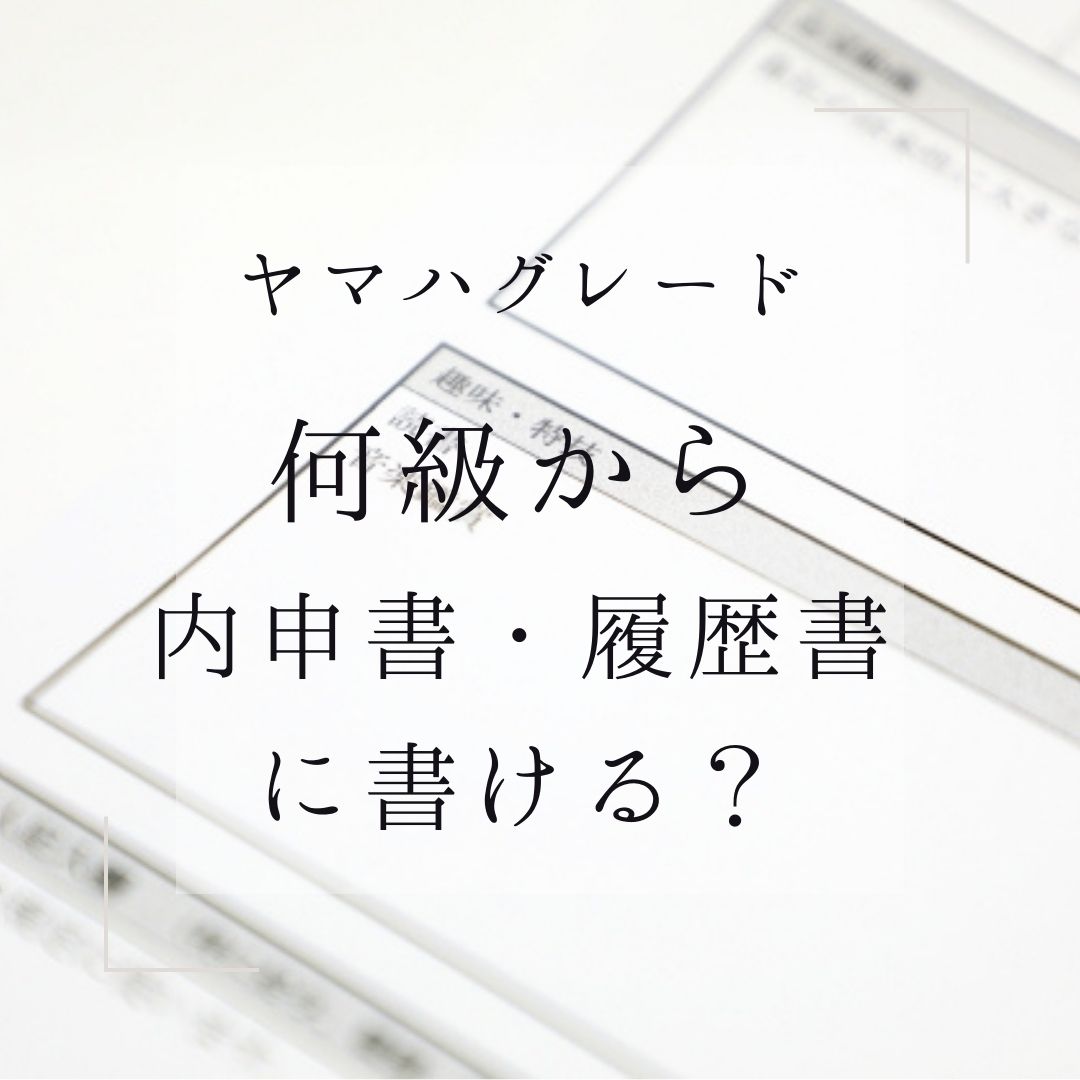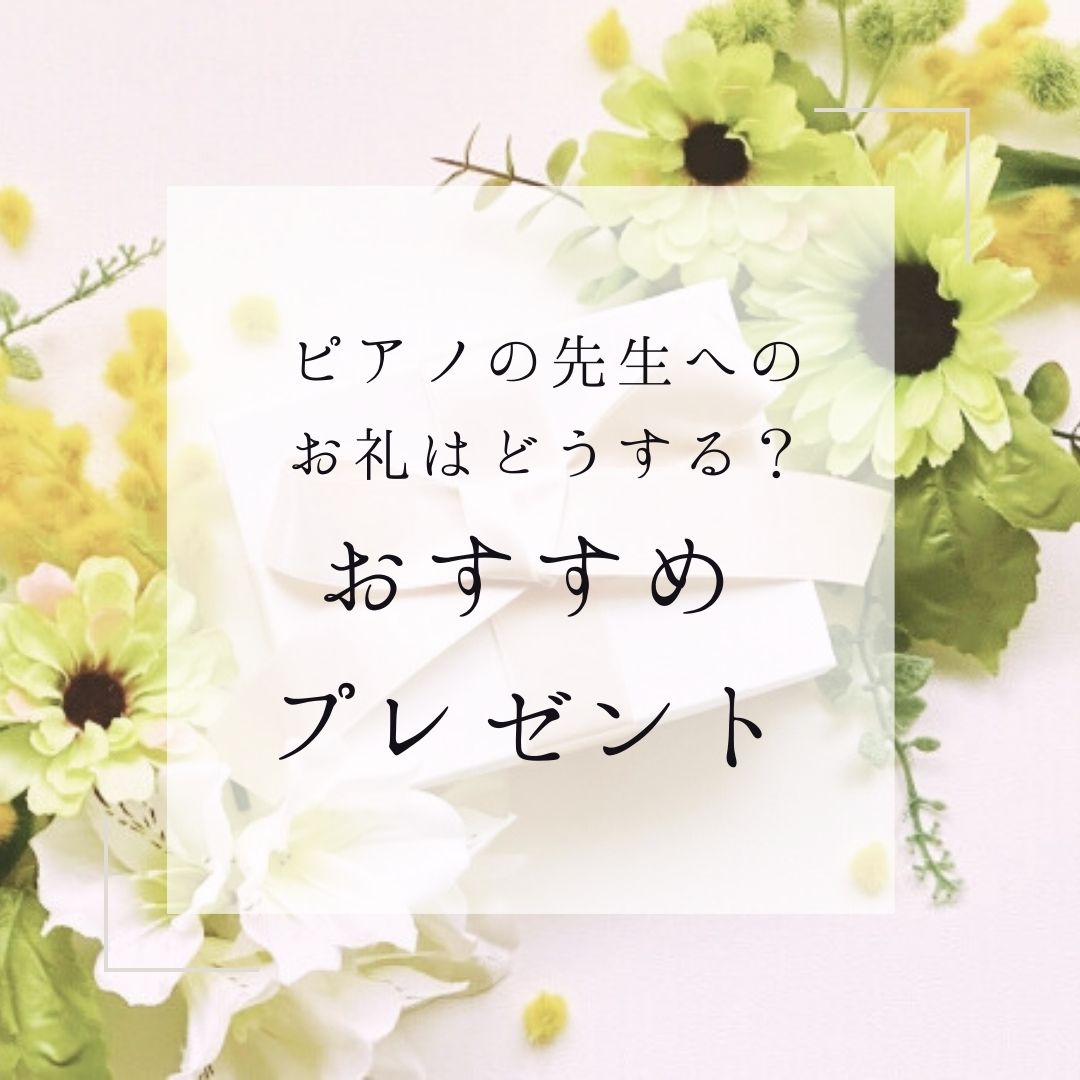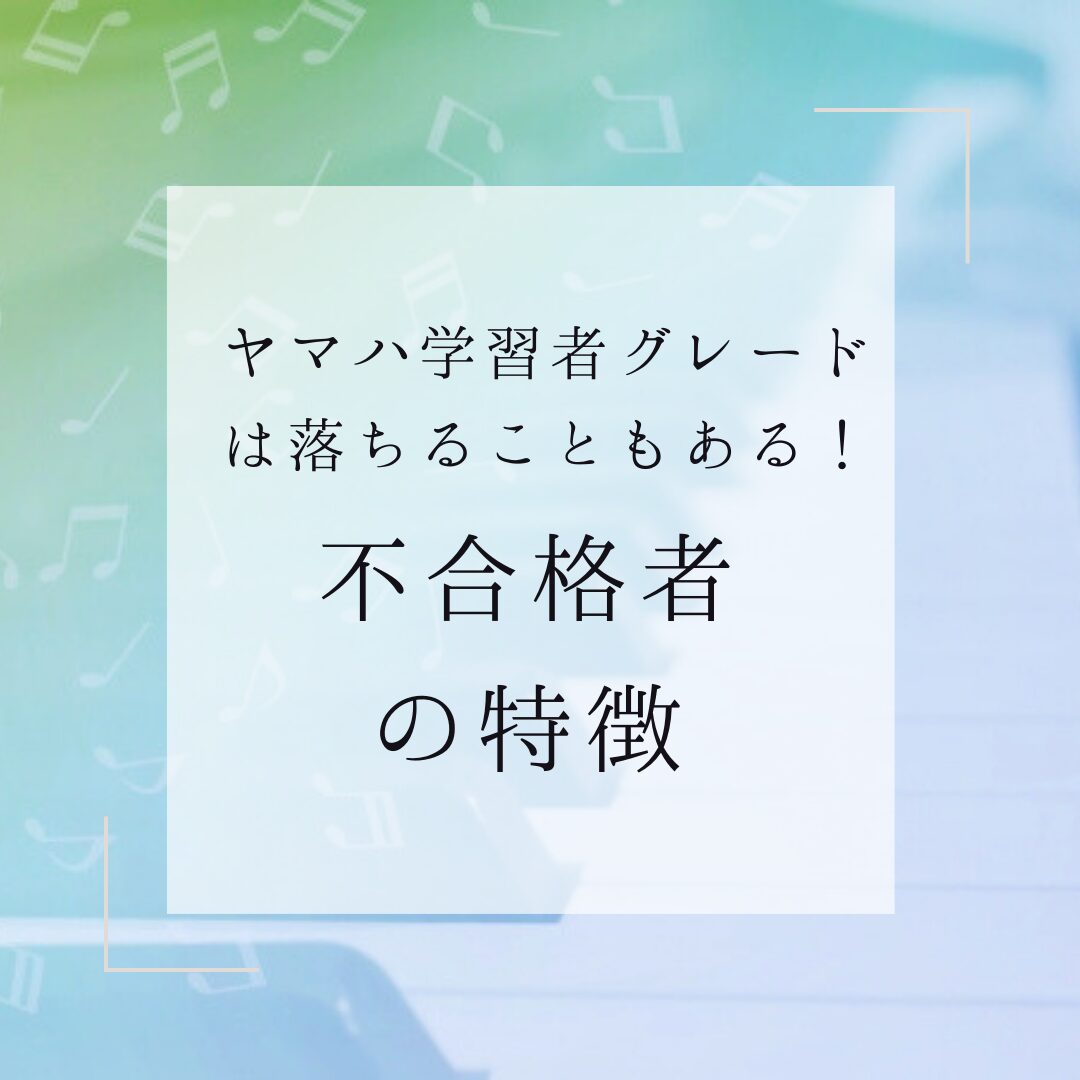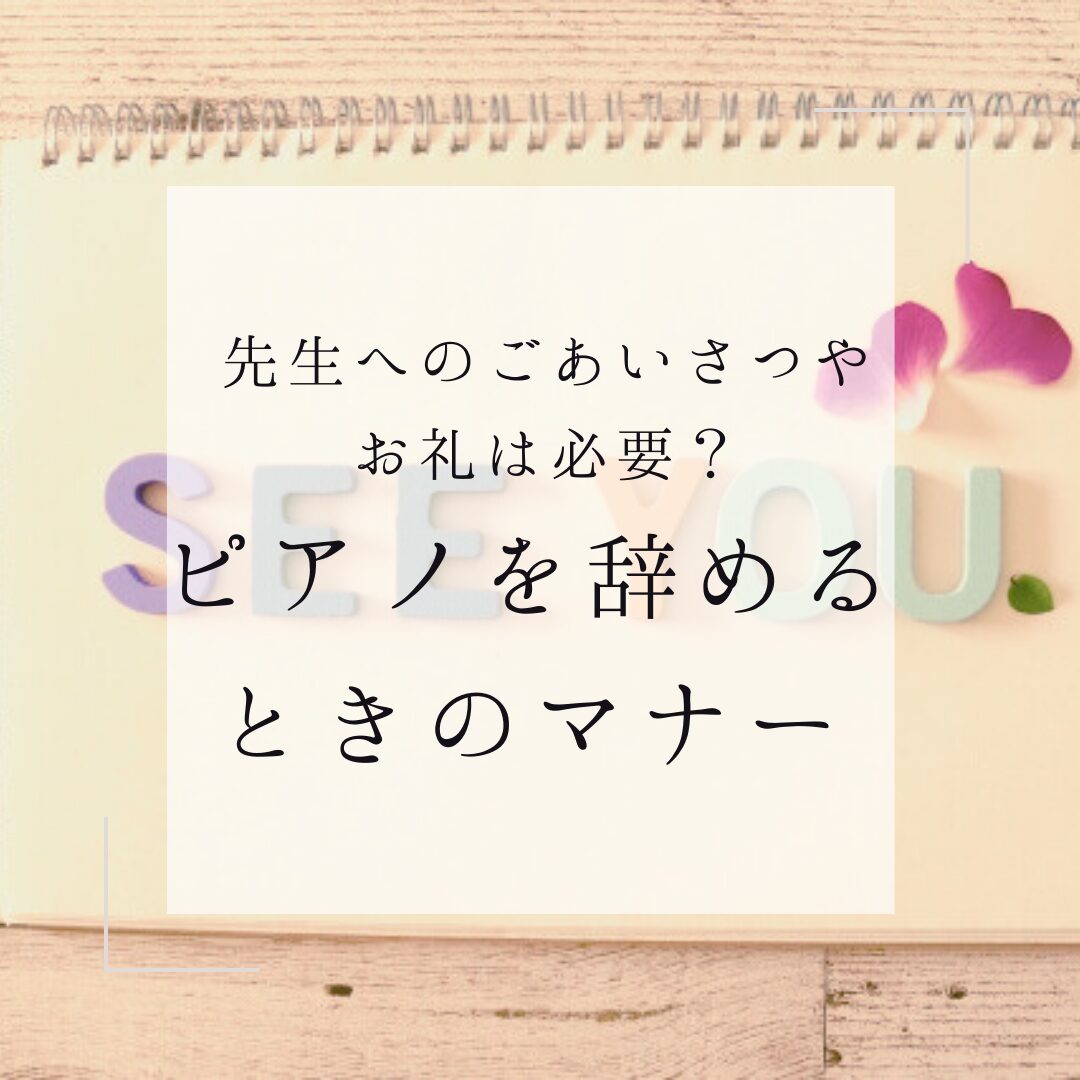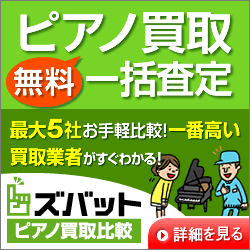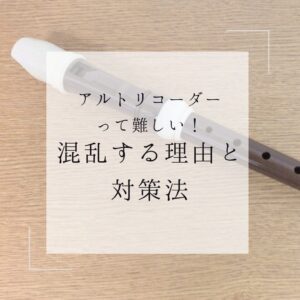学校の音楽の授業といえば、
- ピアニカ(鍵盤ハーモニカ)
- リコーダー
- 合奏
- 合唱
などを思い出す人が多いのではないでしょうか?
小学校ではソプラノリコーダーを学習して、中学校ではアルトリコーダーをすることになったけれど、

指の動きが難しくて挫折しちゃった・・・
という声も聞きます。
この記事は
- 中学音楽でアルトリコーダーを演奏している人
- ソプラノリコーダーとの違いで苦労している人
- アルトリコーダーが上手に演奏できるようになりたい人
- アルトとソプラノでなぜ運指が違うのかを知りたい人
におすすめです!
どうしてアルトリコーダーは難しく感じられるのか、その原因と対策について考えていきましょう!
私も中学で演奏したよ♪
\アルトリコーダーを学習しない学校もあるって本当?/
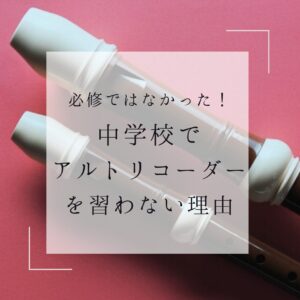
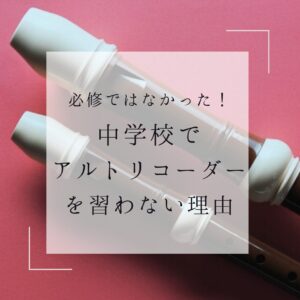
ソプラノリコーダーとアルリコーダーの違い


まず、アルトリコーダーの特徴を理解するために、ソプラノリコーダーとの違いについて理解する必要があります。
いくつか違いがあるので、一つずつ確認していきましょう!
サイズ(大きさ)の違い
ソプラノリコーダーとアルトリコーダーをくらべると、ソプラノリコーダーの方が小さいのがわかります。
アルトリコーダーは、ソプラノリコーダーよりも太く長いのが特徴です。
音域の違い
ソプラノリコーダーとアルトリコーダーでは、鳴らせる音域が異なります。
- ソプラノリコーダー高音域
- アルトリコーダーソプラノリコーダーより低い音域
この音域の違いによって、指の押さえ方や息の使い方に違いが出てくるため、手のサイズが小さい子は苦労することも・・・
またアルトリコーダーはソプラノよりも大きく、より多くの息を必要とするため、初心者には息のコントロールが難しい楽器でもあります。
\ソプラノ・アルト以外にもまだまだあります!/
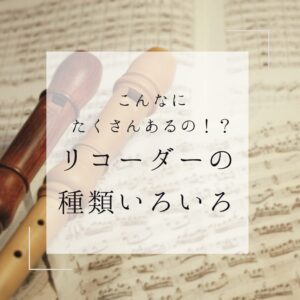
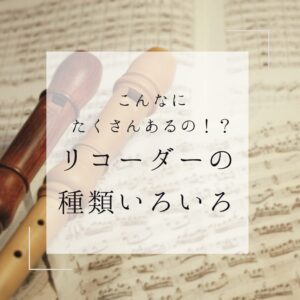
運指(指使い)の違い
中学音楽でアルトリコーダーを習う際に挫折しやすいポイントの一番の原因は、ソプラノリコーダーとの運指の違いだと考えます。
特に、「ド」の音の押さえ方が異なるため、ソプラノリコーダー経験者はこの時点で混乱してしまうことも・・・
このため、初めてアルトリコーダーを学習するときは、新たに運指を覚え直さなければなりません。
\指使いをマスターして名曲を奏でよう/
運指(指使い)が異なる理由


ソプラノリコーダーとアルトリコーダーで、どうして運指が違うのか、その理由を知るためにリコーダーの歴史を少し学んでいきましょう!
リコーダーの元はアルト
日本では子どもの手に馴染みやすく扱いやすいという理由から、小学校で学ぶ楽器はソプラノリコーダーとなっています。
しかし、リコーダーの歴史をたどっていくと、 一番最初にできたといわれているのはアルトリコーダーであるといわれているのです。
実際にミドルC(ピアノでいうまんなかのド)はアルトリコーダーで鳴らすことができるのですが、ソプラノリコーダーで指を全部おさえたときに出る「ド」の音は、実はミドルCよりも1オクターブ高い「ド」なのです。
ピアノと一緒に吹くとわかるよ!
リコーダーは移調楽器である
リコーダーは移調楽器の一つでもあります。
ソプラノリコーダーは、先ほどもお話ししたように、穴を指で全部おさえると「ド」の音が鳴ります。
つまり、ソプラノリコーダーはC管ということができます。
では、アルトリコーダーはどうでしょう?
アルトリコーダーの穴を指で全部おさえると「ファ」の音がしますね。
ソプラノリコーダーと同じ運指(指使い)で吹いてしまうと、「ファ ソ ラ ♭シ ド レ ミ ファ」となってしまいます。
つまり、アルトリコーダーはF管の楽器なのです。
移調楽器だけど楽譜は実音
という人が多いのは、 アルトリコーダーがF管という移調楽器にもかかわらず、楽譜の表記が実音になっていることが大きな要因 だと考えられます。
移調譜を使えば、すぐに対応できそうですが・・・(絶対音感がある人にとっては、気持ち悪いだけですが・・・)
\移調楽器について詳しく知りたい/


指使い(指の運び方)が難しい


ソプラノリコーダーとの運指の違いの難しさについて触れましたが、それ以外にも
- 楽器自体の大きさ
- 穴の大きさ
によって、上手に指をコントロールできない場合があります。
アルトリコーダーは音域が広く、低音から高音まで幅広い音をカバーするのですが、この音域の広さが指使いの難しさに繋がります。
低音域を出すコツ
初心者はまず低音域の運指にしっかり慣れることからはじめましょう!
最初から理想のテンポで演奏するのではなく、ゆっくりとしたテンポからはじめ、指の動きをしっかり確認しながら進めることで安定した音が出せるようになりますよ。
高音域を出すコツ
高音域では半押しの技術が必要!
これは穴を完全に押さえず、半分だけ指を乗せて音を出す技術で、多くの初心者がここでつまずいてしまいがち・・・
ソプラノリコーダーとは穴の大きさが違うため、「半分押さえるサイズ」も変わります。
高音域の指使いに慣れるためには、1つの音だけを集中してねらう練習するのが効果的!
指をしっかり押さえることはもちろんですが、力を抜いて息のコントロールをすることが重要です。



強く吹くとピーってなっちゃう
音程(ピッチ)・息のコントロールが難しい
ソプラノリコーダーに慣れていると、アルトリコーダーはサイズが大きくなるので、使う息の量も異なり音程を安定させることが難しいと感じる人も多いようです。
音程を微調整するためには、息の量や強さ、指の押さえ方に注意を払わなければなりません。
また、音程がずれていることに気づきにくい方は、演奏が不安定になりやすいので、音程が正しく出せているかチューナーで確認するのもよいでしょう。
\正しいピッチ/
アルトリコーダーの難しさを克服しよう!


リコーダーは移調楽器の一つで、ソプラノとアルトでは運指が異なったり、鳴らせる音域も異なることが分かりましたね。
アルトリコーダーが難しいと感じる理由は、
- 息のコントロール
- 運指
- 音程の調整
- 移調楽器なのに移調譜を使用しない
など、いくつかの要因にあります。
しかし、ゆっくり丁寧に音程を確認しながら練習すれば、難しさを克服することも十分可能ですよ!
コツコツ練習して、アルトリコーダーに慣れていきましょう。
練習なくして上達なし!
\レパートリーにしたい曲がたくさん!/
\リコーダー関連記事はこちら/
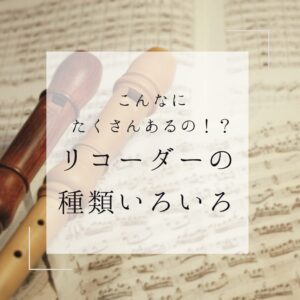
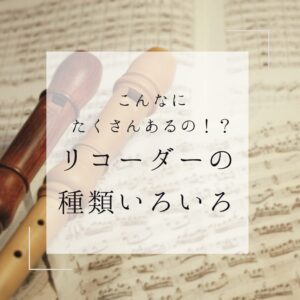
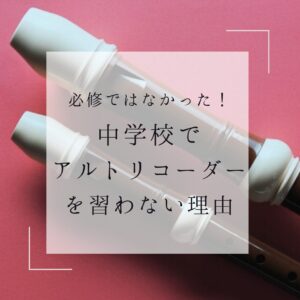
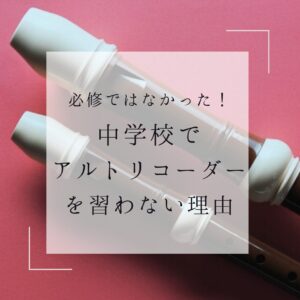


\中学音楽といったら合唱コンクール!/
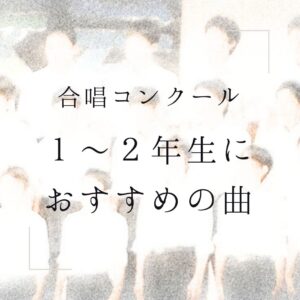
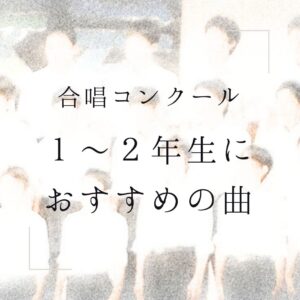
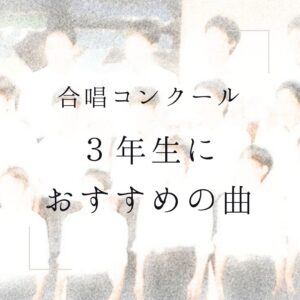
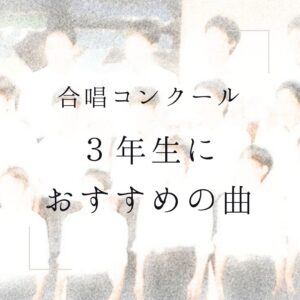
この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿