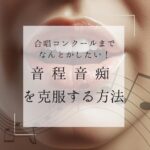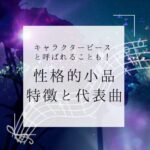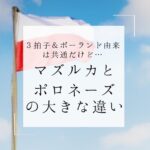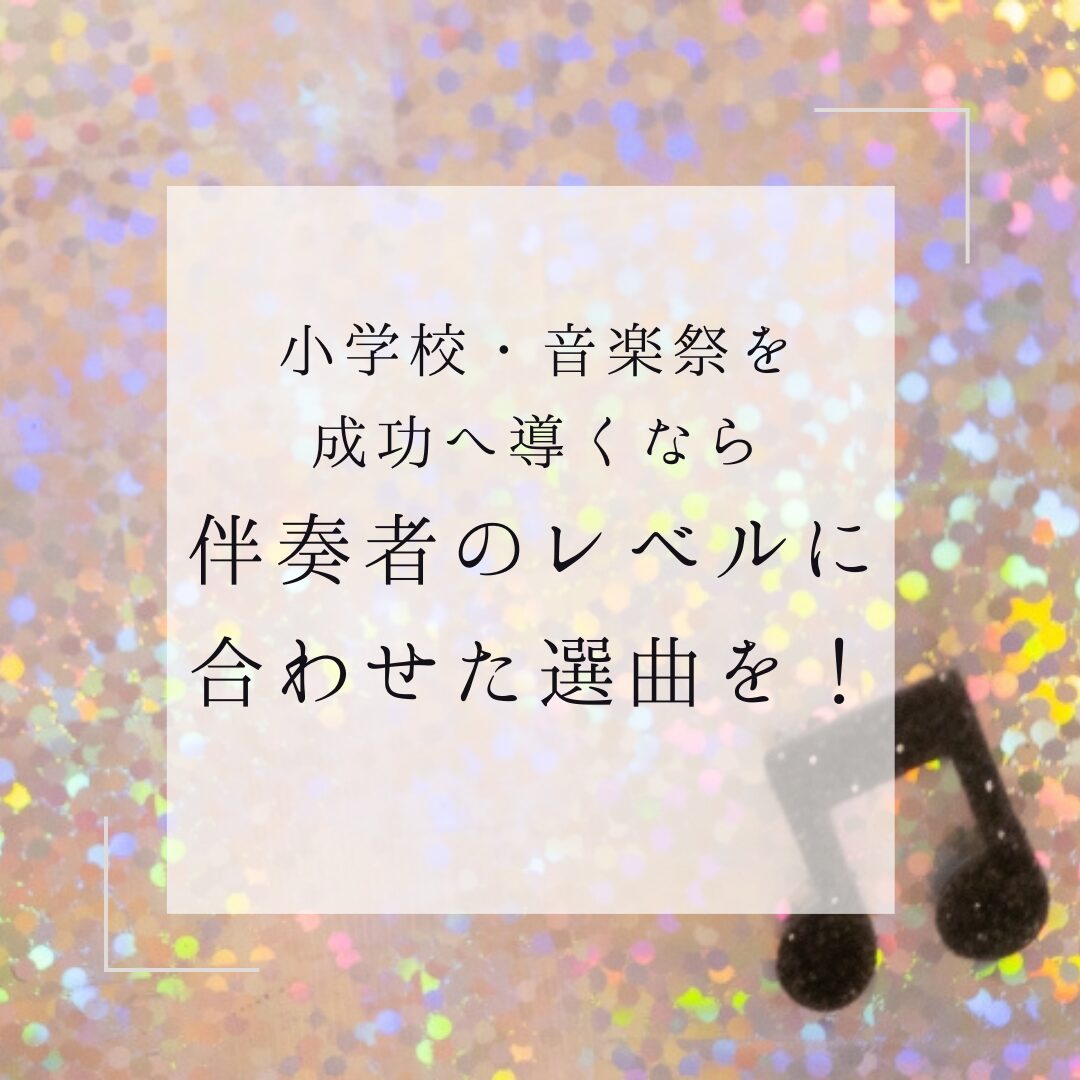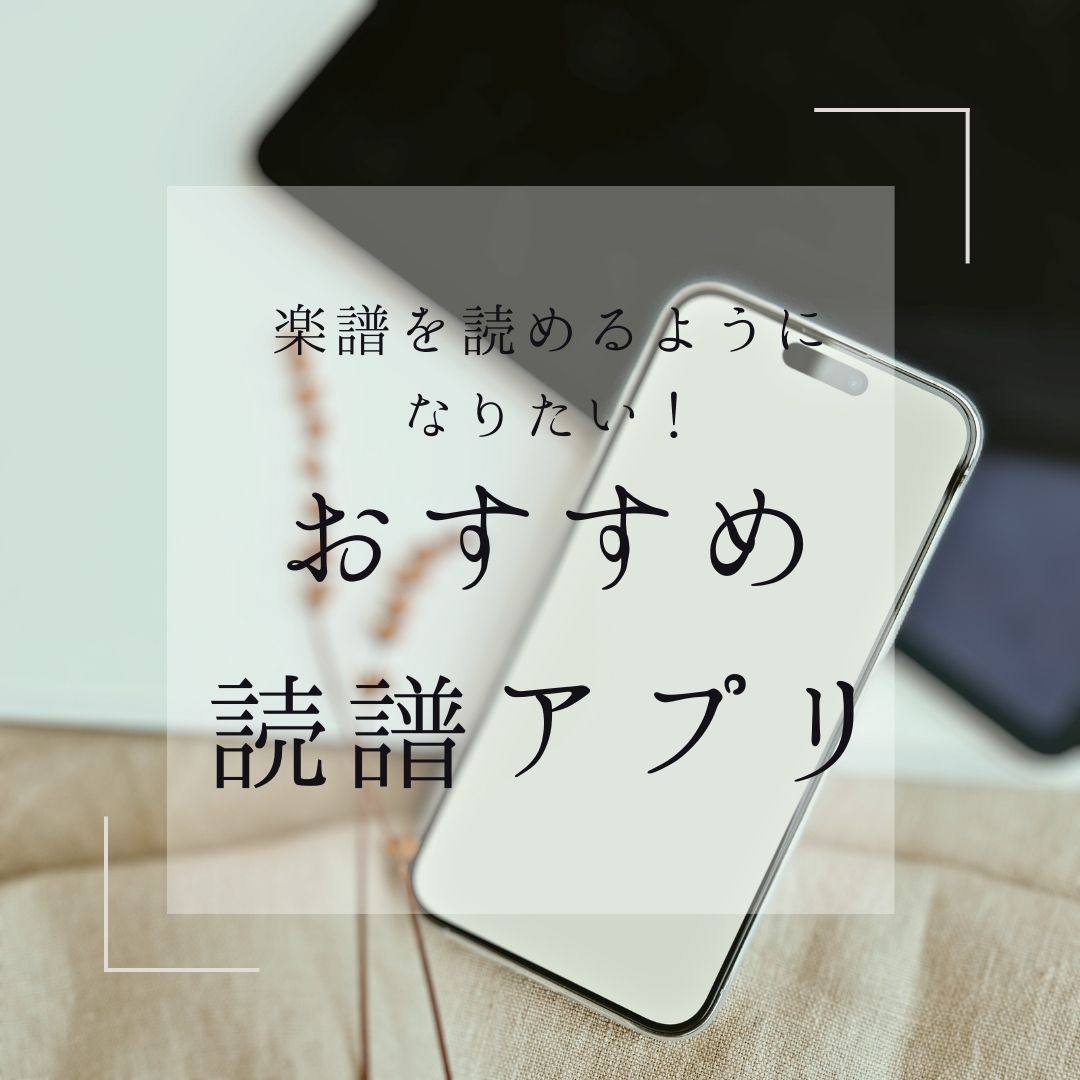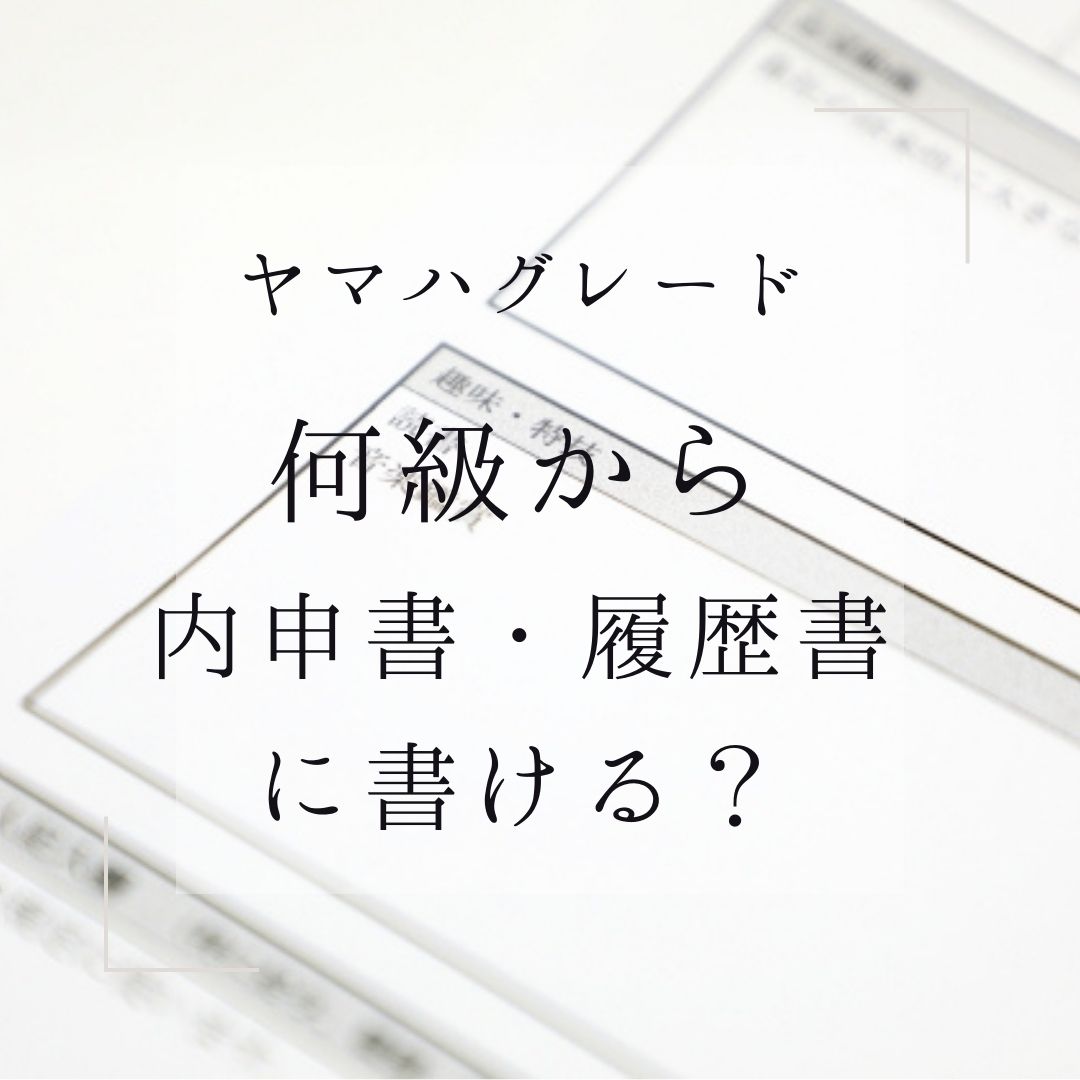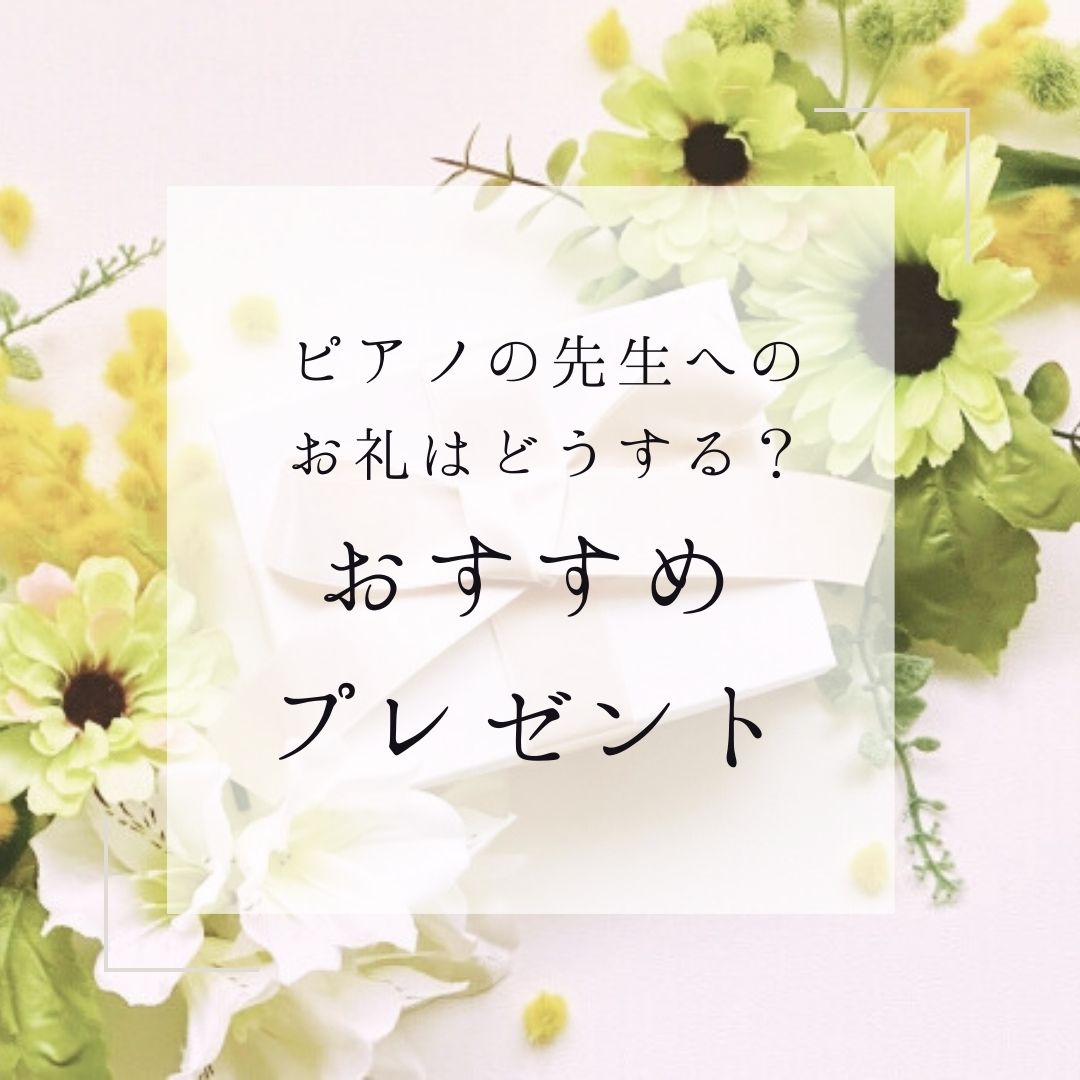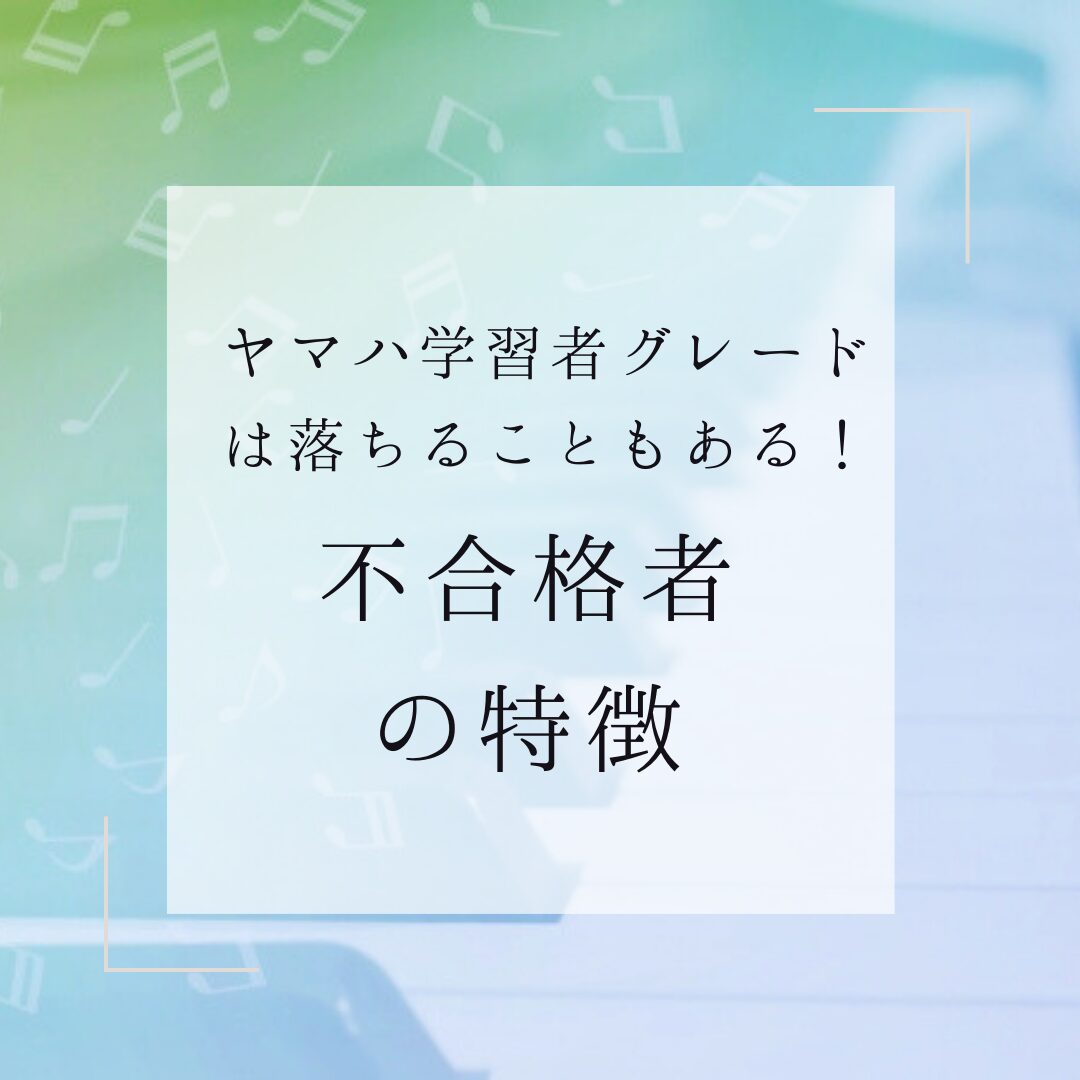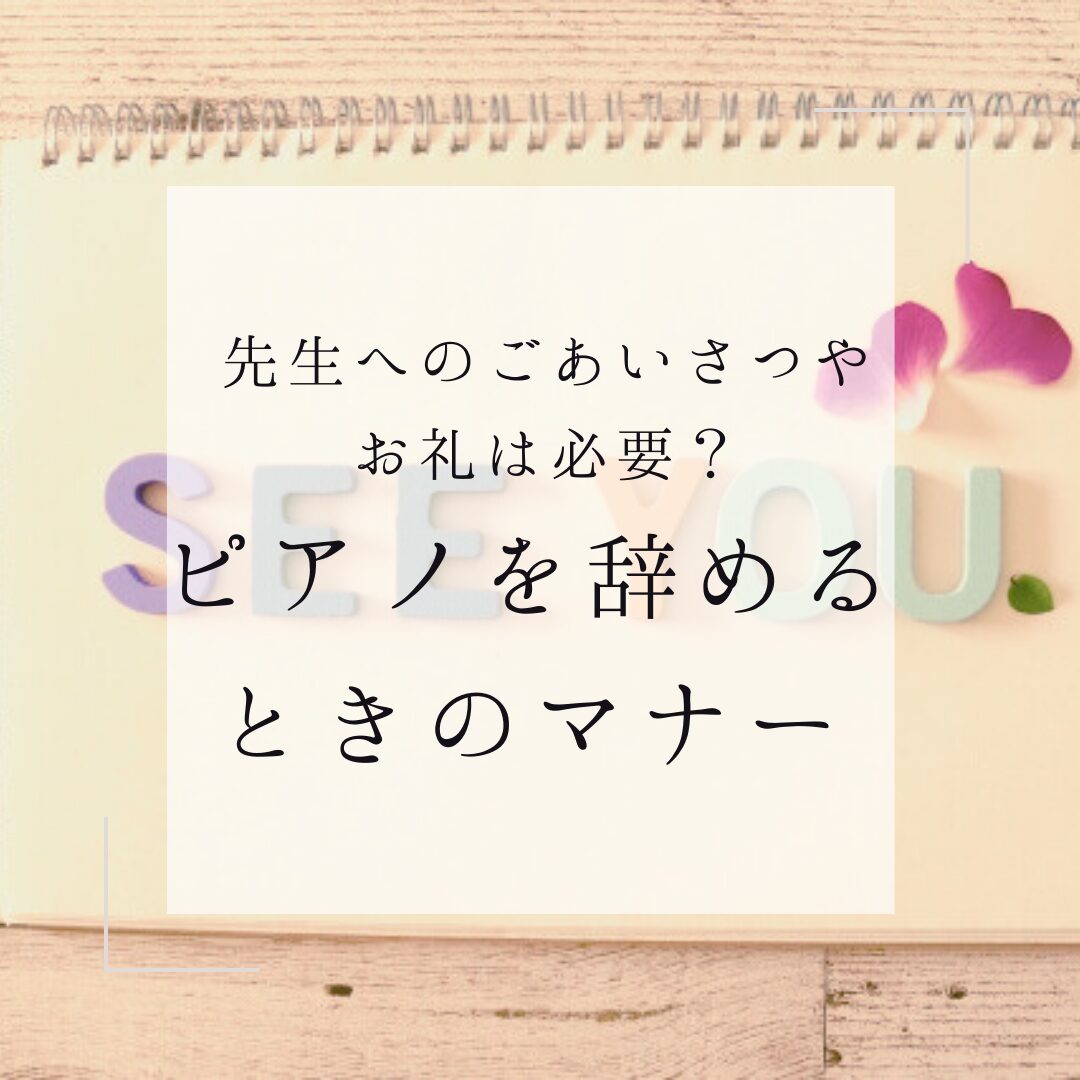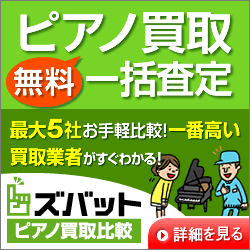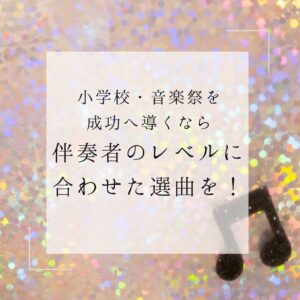小学校の中学年になると地区で音楽祭があるため、生徒が伴奏を頼まれたり、「オーディションがあるから来週までに少し弾いてきてね」と言われたりすることがあります。

先生、この楽譜なんですけど、うちの子は弾けますか?
このように生徒のお母さんに楽譜を見せてもらうこともあるのですが、
大丈夫!間に合いますよ!
と即答できないような曲を貰ってくることも・・・。
この記事は
- 音楽祭や文化祭の選曲(曲選び)に悩んでいる小学校の先生
- 生徒が弾けるレベル曲なのか判断に迷っている小学校の先生
- お子さんが学校で伴奏を頼まれてきたというご家庭
におすすめです!
小学校の先生にぜひ知っておいてほしい、音楽祭・文化祭で発表する合唱・合奏曲の選曲方法についてお話しします。
現役ピアノ講師の本音!
選曲は伴奏する生徒のレベルを見極めることが大切


私が住んでいる地域は小学校4年生になると、秋に地区の音楽祭に参加し、同じ曲で学芸会・文化祭でも発表するところが多いようです。
そのため、ピアノを習っている子を募って夏休み前(夏休み後という学校も!)に伴奏者を決めて、先に伴奏の練習をしてもらうシステムになっています。
すぐできる子・時間がかかる子…生徒の状況はさまざま
それで生徒は楽譜をもらってくるわけですが、
というものから
というものまで、これまでいろいろなレベルの楽譜を持ってきました。
なかには中学校の合唱コンクールで歌う曲をもらってきた・・・なんてことも!
さすがに学校の先生へお電話しました
物理的にまだ弾けないことも


コンクールで上位をとっている子なら譜読みも早いですし、調号がたくさんついていたり、曲の途中で転調があったりしても大丈夫なことが多いかもしれません。
しかしこれまで生徒が渡された楽譜のなかには、オクターブがたくさんあったり、4和音がいっぱい出てきたり・・・と、普通にピアノを習っているレベルでは、弾きこなすことが無理な場合もあります。
小学校中学年は、まだ1オクターブが届かない生徒も・・・
学校の先生は余裕で届くので「弾けるでしょ」と思うかもしれませんが、子どもの手は大人とサイズが違うので物理的に不可能なこともあるのです。
教師のエゴを生徒に押し付けない
学校の先生にしてみれば、
「感動できる曲だから歌わせたい」
「自分が好きな曲だから、ぜひ生徒に歌わせたい」
など理由があると思います。
しかし、 生徒にしてみれば自分が練習している曲より遥かにレベルの高い曲を渡されて、毎日1~2時間泣きながら練習しないと間に合わない・・・ という状況になるかもしれないのです。
さすがにそれはかわいそうですし、 生徒自身が
という状況になってしまっては元も子もありません。
「もう人前で弾きたくない!」という子も・・・
ピアノ講師がアレンジすることも


渡された楽譜が生徒にとって
- ちょっとレベルが高いかもしれない
- 弾きにくいところがある
- この和音は物理的につかめない
という場合は、学校の先生に確認して伴奏譜を簡単に直してあげることもあります。
ときには、その生徒が弾ける範囲内で楽譜をすべて書きなおしたこともありました。
しかし、いくら生徒のためとはいえ「これって著作権上、大丈夫なんだろうか・・・?」とビクビクしてしまうことも・・・
営利目的ではないでので大丈夫なのかもしれませんが、完全なボランティアで楽譜を書きなおすのもなんだか腑に落ちません。
一言お礼があると嬉しいです!
\保護者が気を遣ってくださることも/
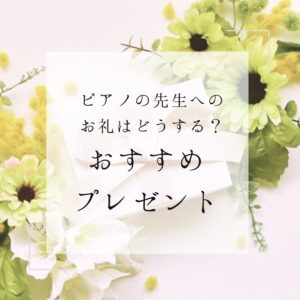
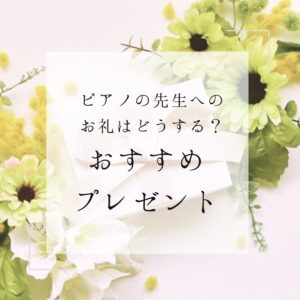
選曲する際の5つのポイント


ここから、小学校の先生にお願いしたい選曲上の注意点として5つのポイントをご紹介します。
生徒のレベルに合わせた選曲をする
これは強くお願いしたいことです。
伴奏をお願いする生徒が「どれくらい弾けるのか」を、先生自身がきちんと知っておいてほしいです。
たとえば、生徒の状況を確認する方法としては次のようなことが挙げられます。
- 今レッスンで習っている楽譜を持ってきてもらう
- 発表会で弾いた曲を弾いてもらう
- 一曲仕上がるのにどのくらい時間がかかるのか保護者に聞いてみる
このようなことを確認すれば、伴奏をお願いする生徒がどのくらい弾けるのか判断できるはず!
伴奏してほしい曲を生徒に見せても、中学年くらいだと「自分が弾けるか弾けないか」が分からない子どももいるので気を付けましょう。
\オーディションするなら必見!/
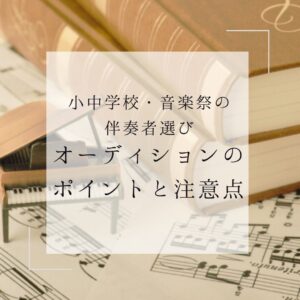
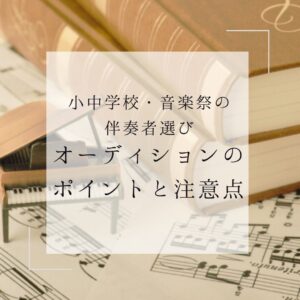
\卒業シーズンの場合はこちら/


小学校・中学年用にアレンジされた曲を使う
小学校の音楽の教科書にのっている曲ならレベル的にも間違いないと思いますが、「ちょっとそれじゃあ芸がないのでは?」と思われる方は、小学校・中学年用にアレンジしてある曲集から選曲してみてはいかがでしょうか?
小学校・中学年で演奏することを前提として編曲・編集してあるので、「絶対無理!」というものはおそらくないはずです。
もしコンクール入賞歴があり、中学年用の楽譜だと物足りなさを感じるようなことがあれば、高学年用の楽譜または音楽の先生用のアレンジでも大丈夫かもしれません。
伴奏をお願いする生徒の状況に合わせて、対応していきましょう!
\生徒のレベルに合わせて選べる!/
\解説入りで指導しやすい/
ピアノ講師と連携をとる


可能であればですが、伴奏をお願いする生徒のピアノ講師と連絡を取ってみてください。
生徒や保護者よりも、その生徒がどのくらい弾けるのか状況をよく理解しているのはピアノ講師です。
生徒を通じて、ピアノ講師にお手紙を渡してみるのもいいでしょう。
達成感を味わえる曲を選ぶ


達成感や一体感を味わえる作品に出会えるといいですね!
みんなでーつの曲を完成させることが、集団教育の目的でもあり大切なことの一つです。
「うまくできなかった」「失敗した」とならないように、余裕を持ってしっかり完成しそうな曲を選びましょう。
- ハモるところは難しくないか
- 複雑で生徒にとって難しそうなリズムはないか
- 自分で指導できる範囲内の曲か
なども確認して選曲してくださいね。
みんなで一つのものを作るよろこびを感じたい!
音楽専攻の先生に相談する
小学校の先生は、すべての教科に携わるのでとても大変です!
大きい学校なら、音楽の教科担任の先生がいるかもしれませんが、小さい学校だといないこともあります。
近年では教科担任制を導入する学校も増えてきたので、苦手だった先生はホッとしているのではないでしょうか?
もし音楽の教科担任の先生がいるなら、「この曲で大丈夫かどうか」を相談してみてください。
いないようでしたら、昔ピアノを習っていた先生に相談してみましょう!
伴奏する生徒に寄り添った選曲をしよう!


小学校の合奏・合唱曲を選ぶ際に、先生に気をつけてほしいことをまとめました。
ぜひ伴奏をする生徒の身になって、「楽しかった思い出」「成功体験」の一つになるよう配慮して選曲していただきたいです。
もし選曲に悩んでいるなら、何曲か楽譜を生徒に持たせてピアノ講師にご相談ください。
きっとその生徒のレベルに合った曲を選んでくれるはずですよ!
相談してね♪
\オーディションするなら早めの検討を/
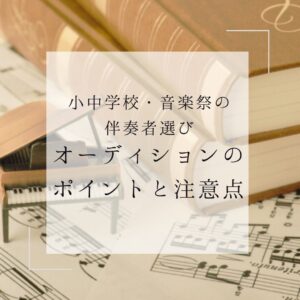
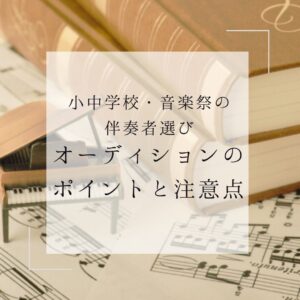


この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿