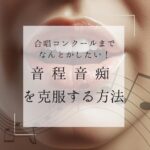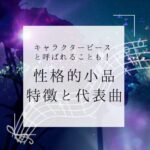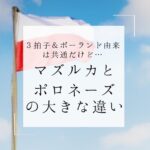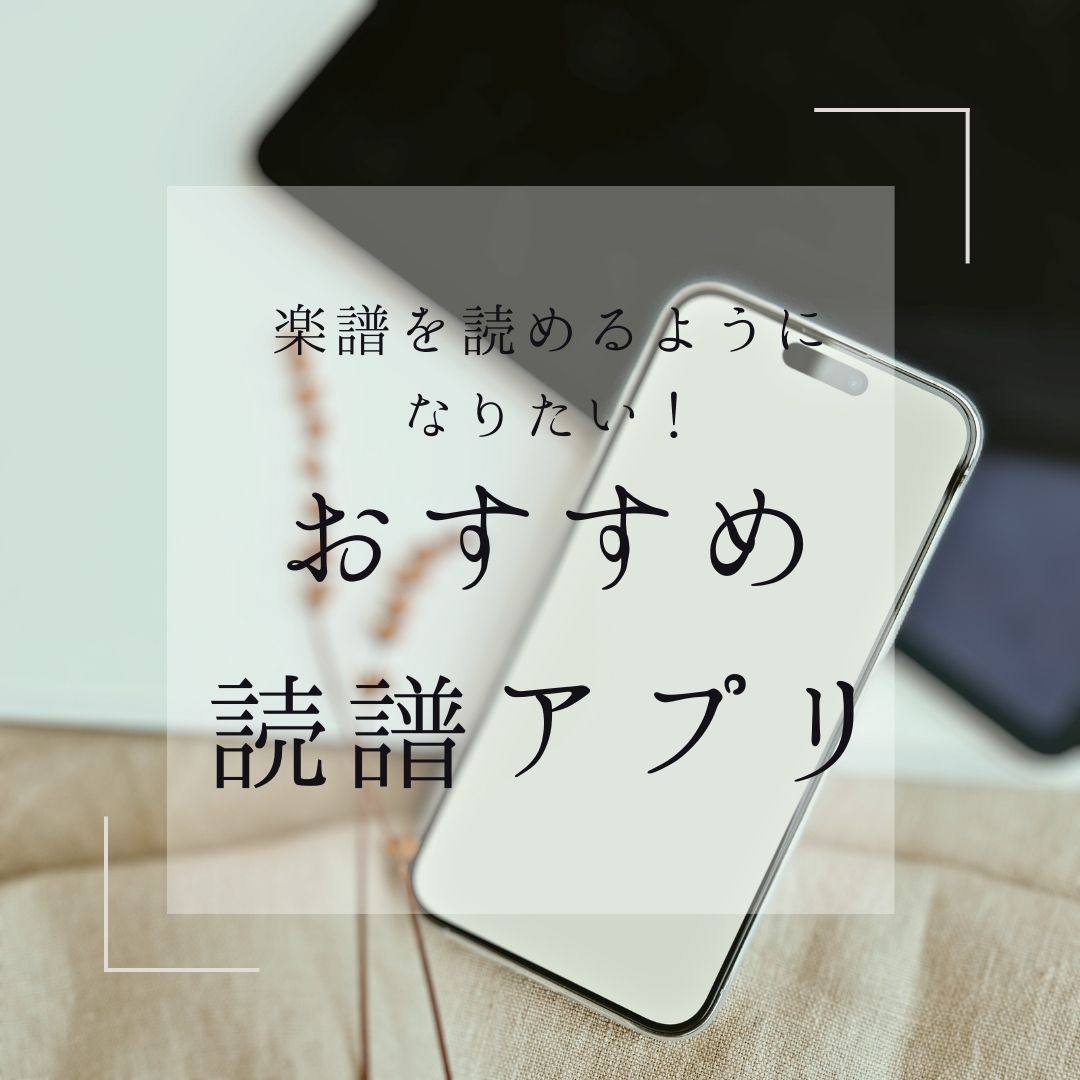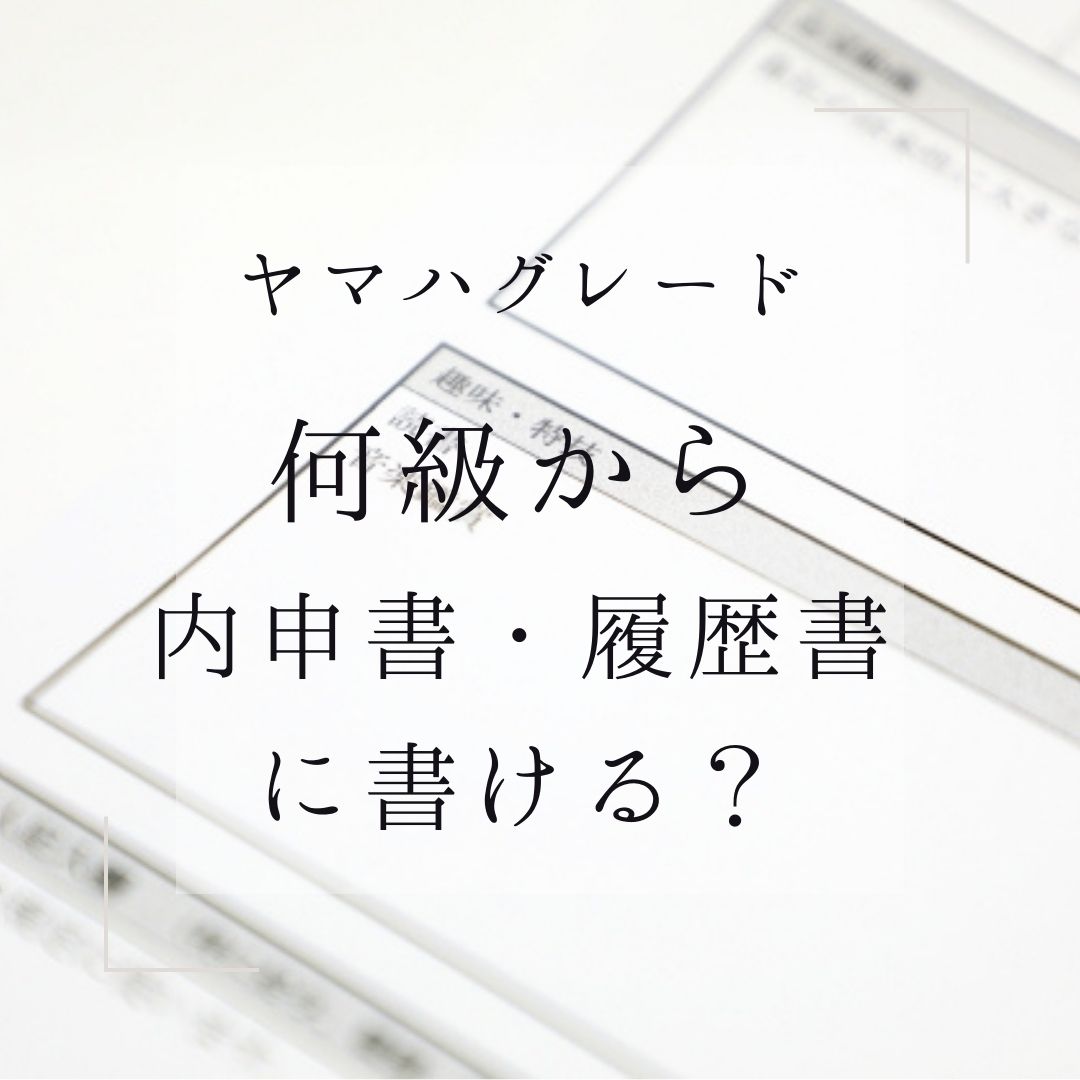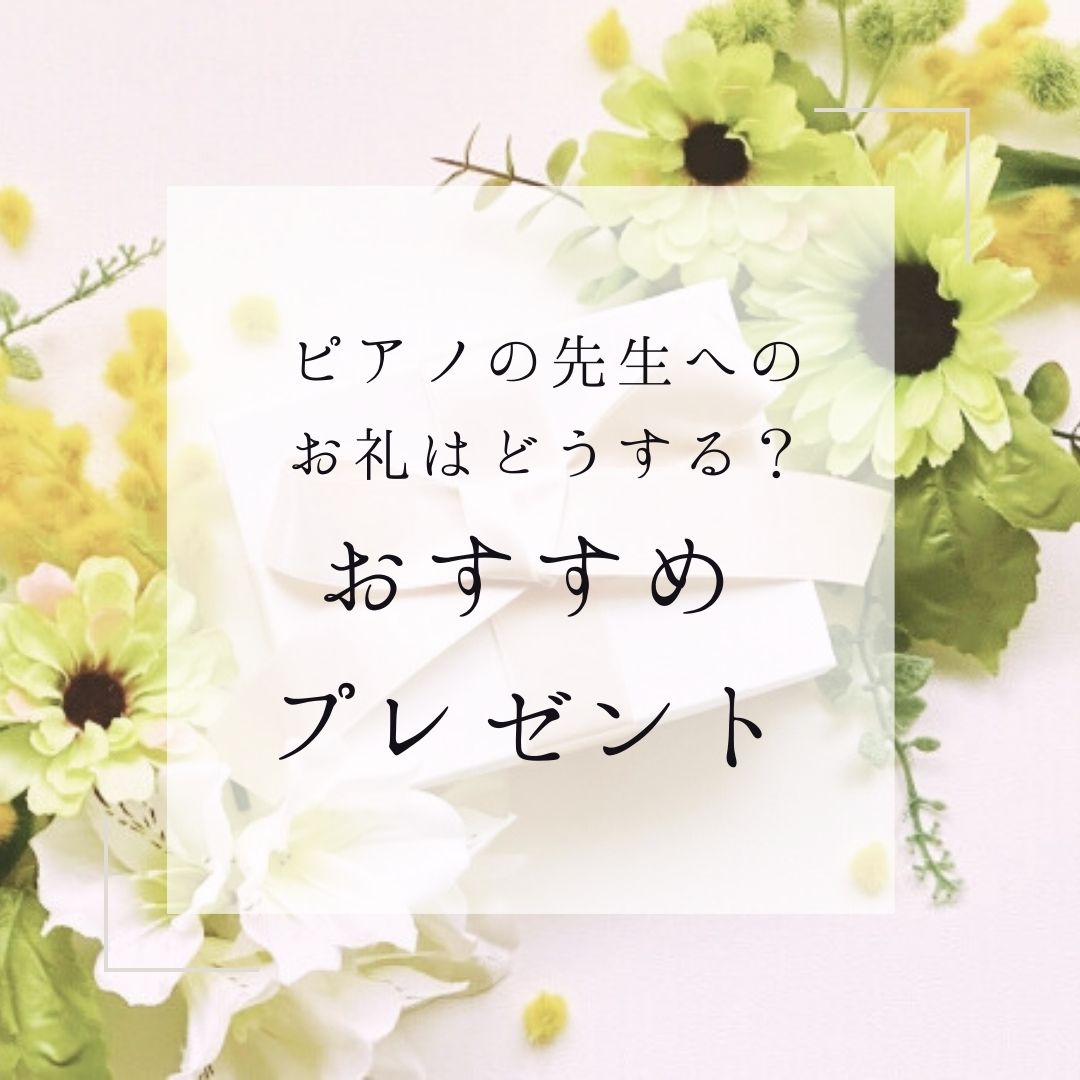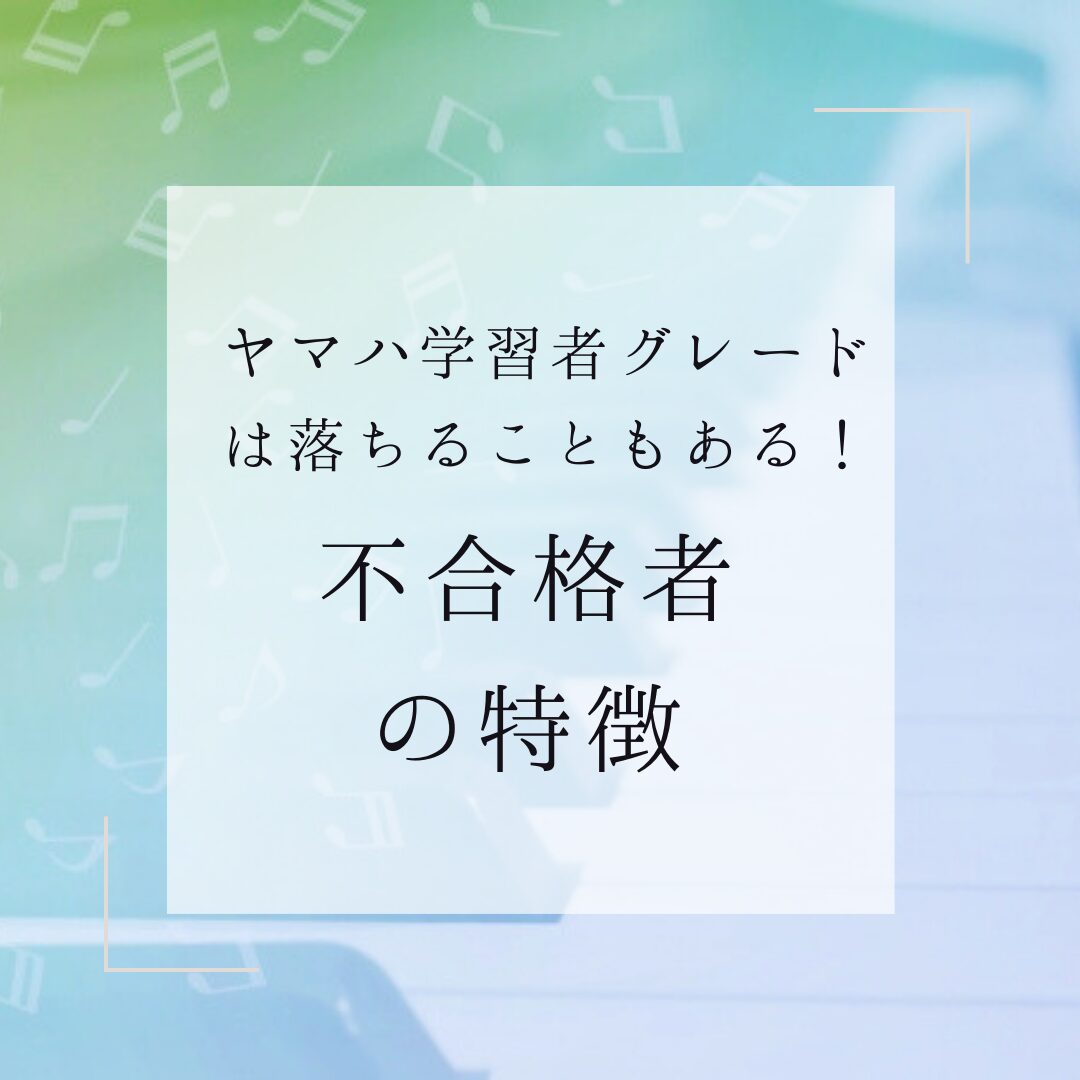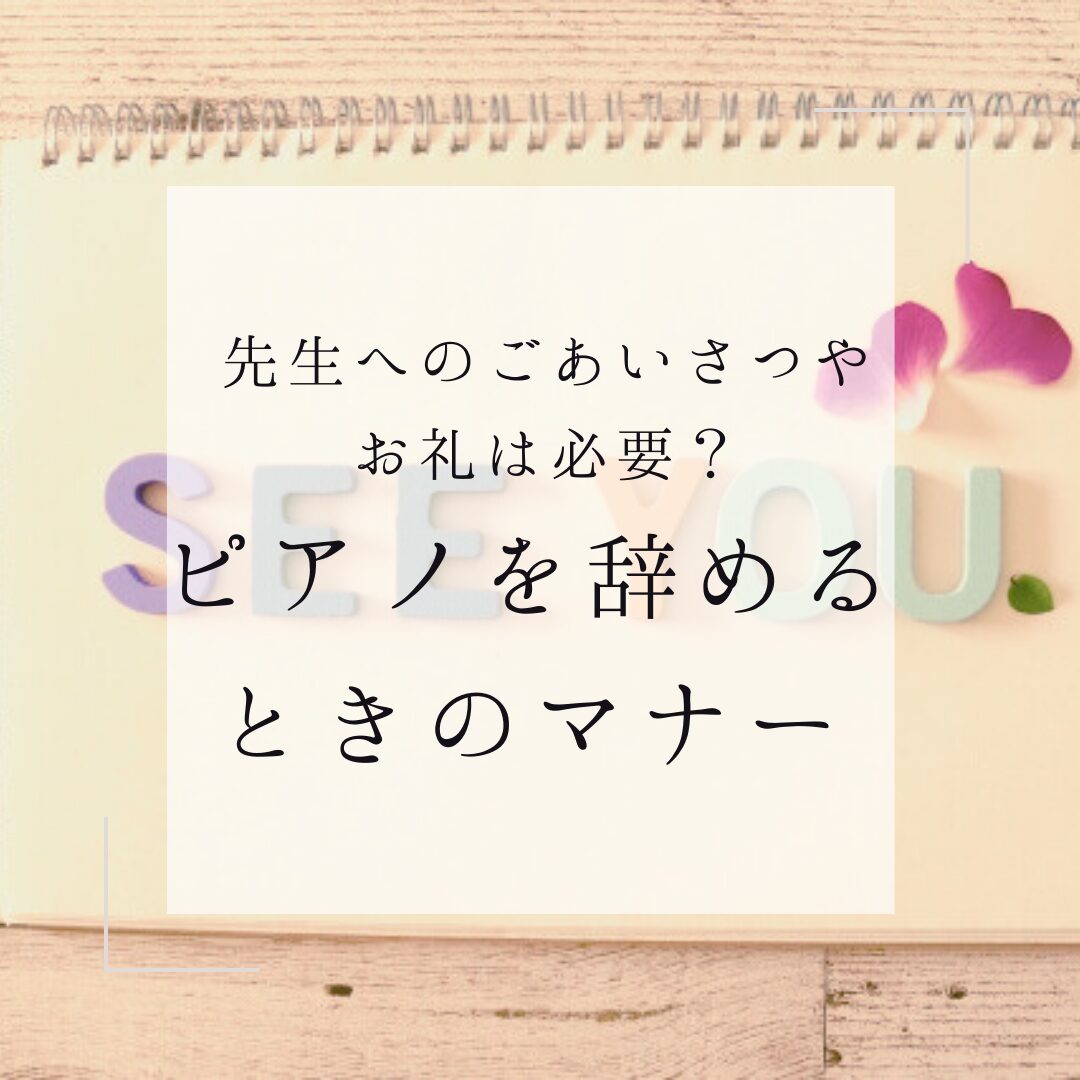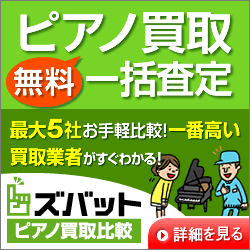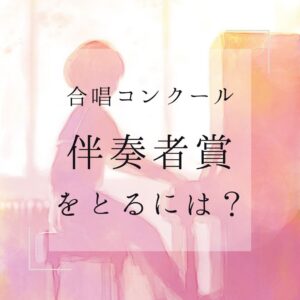中学校の合唱コンクールでは、指揮者・伴奏者のなかから優秀な生徒に賞を与えることがあります。
そのなかで、伴奏者賞はピアノを習っている人なら一度は受賞してみたい賞ではないでしょうか?
この記事は
- 伴奏者賞をとりたい人
- 合唱コンクールの伴奏の役割を知りたい人
- 伴奏者のレベルに合わせた選曲方法を知りたい人
におすすめです!
合唱コンクールで伴奏者賞をとるために、なにができるのか、練習方法や選曲のポイントなどもご紹介します。
伴奏者賞をとるにはどうしたらいいの?

校内合唱コンクールのピアノ伴奏に選ばれるということは、ピアノを習っている人にとって嬉しいことですよね!
その一方で、曲がすごく難しかったり、指揮がめちゃくちゃで全然合わせられなかったり・・・と不安な面もあるのではないでしょうか。
ピアノを習っていて伴奏者になったら、考えてしまうのが「伴奏者賞をとれるかどうか」ということ。
ピアノを習っている人にとって、伴奏者賞は名誉なことです。
伴奏者賞をとることで、自信もつくはず。
では、どうしたら伴奏者賞がとれるのでしょう?
今回は、合唱コンクールで伴奏者賞をとるためにできることをお話しします。
\ 指揮者に選ばれた方はこちら /

合唱コンクールで伴奏者賞を目指すための6ステップ

ここからは、実際に私が中学生の生徒に合唱コンクールの伴奏指導をした経験から、伴奏者賞を目指すためにできることをいくつかご紹介します。
①審査基準や審査員は誰なのかを知ろう
学校によって審査基準がバラバラなので、「こうしたら絶対に伴奏者賞をとれる」と断言できませんのでご了承ください。
合唱コンクールの審査員は、校長先生や教頭先生など、校内の偉い先生が行っているところや、外部から合唱の指導を行っている専門家を招くところもあります。
もし、外部から音楽を理解している人が審査員としてやってくるなら、技術的な部分はもちろん、表現力も磨かないといけません。
楽譜に書いてある指示を守り、曲想豊かに、難しいところも細部まできちんと弾けるように練習しましょう。
一方、校内の先生が審査員だとしたら、音楽的に細かいところまではわからない方が多いので、表現力やクラスの一体感というところに重点を置いて審査することもあると思います。
審査員が誰なのか、審査基準はどんなところなのかを事前に把握できるのであれば、チェックしておきましょう。
②どんな曲を選ぶか・選曲も重要!

そして大事なのが選曲です。
どんな曲を選ぶかで、伴奏者としてのテクニックを見せられるかが変わってきます。
曲を選ぶ段階になったときには、かならず伴奏者も同席して自分の意見をいいましょう。
では、具体的にどんな曲を選ぶと映えるのでしょうか?
聴き映えする合唱曲を選曲するポイント
- 緩急がある(テンポが速いところ、ゆっくりなところがある)
- 盛り上がりがはっきりしている
- 速弾き・細かいパッセージやアルペジオなどテクニックが必要な場面がある
このような要素がふくまれている曲を選ぶと、伴奏者の腕をみせることができますよ!
あまり曲調に変化がない単調な曲は、伴奏も単調なのでテクニックをみせることができません。
歌いやすくても、伴奏者賞をとるには不向きな場合があります。
華やかな場面、盛り上がる場面などがはっきりしている曲を選ぶといいでしょう。
\ 選曲の参考にどうぞ! /
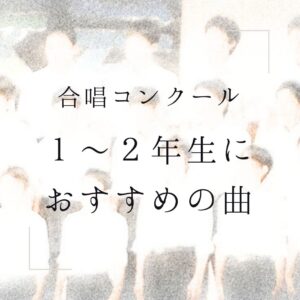
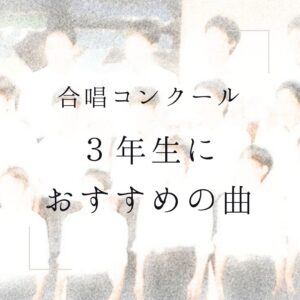
③指揮者ときちんと打ち合わせしよう

「指揮と伴奏が合っているか」ということも伴奏者賞を狙うには必要になってきます。
「指揮者が全然振れなくて、私に合わせて振ってもらってるの」という伴奏者の話も聞きますが、果たしてそれでいいのでしょうか?
クラスの合唱をまとめるのは、伴奏者ではなく指揮者です。
そこは勘違いしないようにしてください。
指揮者がうまくできないなら、伴奏者が寄り添って練習に何度も付き合ってあげましょう。
「あうんの呼吸」で、できるようになればベストです。
そこに至るには、指揮者と伴奏者が二人で合わせる時間をできるだけ多く作ることが大事!
「ここはもっと盛り上げたい」
「ここはもう少しゆっくりしたいんだけど」
・・・など、指揮者と細かいところを打ち合わせながら、たくさん練習してくださいね。
そして 本番は自分の伴奏だけに集中せずに、指揮者をチラチラ見ながら弾くくらいの余裕をもてるようにしましょう。
④クラスの一体感を楽しもう
ピアノの発表会など、ステージで一人で演奏したことがある人はお分かりかと思いますが、ステージでの演奏は何度やっても緊張するものです。
でも合唱コンクールはピアノソロではありません。
クラス全体で臨むステージです。
仲間がいるんです!
合唱コンクール本番では、伴奏者は縁の下の力持ち的存在です。
主役は「合唱」なので、クラスのみんなが気持ちよく歌えるように伴奏でサポートしてあげましょう。
合唱・指揮者・伴奏者が一体となり、一度きりのステージでの演奏を思い切り楽しんでください。
\ 本番は緊張する~!という方へ /

⑤全体のバランスを考えて演奏しよう
先ほどもお話ししましたが、全体のバランスを聴きながら演奏することはクラスの一体感を出すためには欠かせんません。
前奏や間奏、後奏などピアノにスポットが当たる場面は、メロディーとなる部分が聴こえるように演奏することが大切です。
それ以外の合唱がメインとなる部分は、
右手…ハーモニー
左手…ベース
となることが多いのですが、このときにハーモニーがあまり強くならないように注意しましょう。
左手のベースが全体の支えとなる部分なので、ベースラインを意識して演奏するとバランスよく聴こえてきますよ。
メロディーとベースを意識するといいバランスになるよ♪
\めざせ優秀賞/
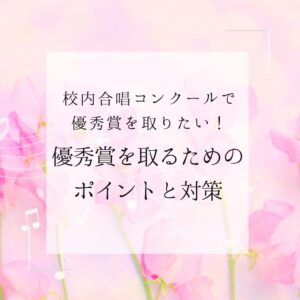
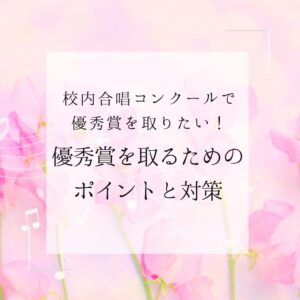
⑥カメラマンに動揺しない
生徒が伴奏を務める合唱コンクールを見学した際に見たのですが、卒業アルバムに掲載するためにカメラマンがステージに上がり、伴奏する生徒に近づき、横や後ろから写真を撮っていました。
演奏する側からすると、視界に入る場所で写真を撮らるのは集中力を欠いてしまうこともあるため迷惑なのですが、そんなことはカメラマンはお構いなしの様子でした。
卒業アルバム用の写真を撮るためにカメラマンがくるかもしれない
と予想し、カメラマンが来ても動じないくらいの余裕を持って準備しておくことが大切です。
集中して演奏しよう!
思い出に残る合唱コンクールになりますように


近年の中学校のピアノ伴奏は、難しいものが多くなってきたように感じます。
聴き映えするかどうかも大切ですが、自分の力量に合わせたものを選ぶことも大事です。
伴奏者賞をとりたいがために、難しいものを選んで弾きこなせず自爆・・・といったことにはならないよう、気をつけましょうね。
「これくらいの曲、どのくらい時間があれば弾けるかな?」と判断に迷ったときは、ピアノの先生や学校の音楽の先生に相談しましょう。
指揮と合唱、そして伴奏の3つがまとまって、一つの音楽を作り出すのが合唱コンクールです。
すごい伴奏を弾いて「目立ちたい!」という気持ちもわかりますが、「伴奏はあくまで脇役」という気持ちも忘れずに。
謙虚な姿勢で臨もう♪
\ 音痴の人に教えてあげて /
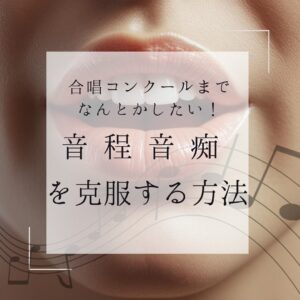
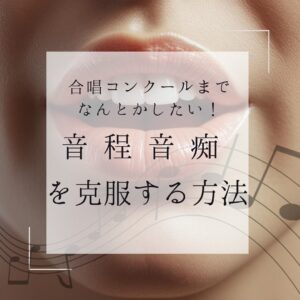
\オーディションは公平に!/
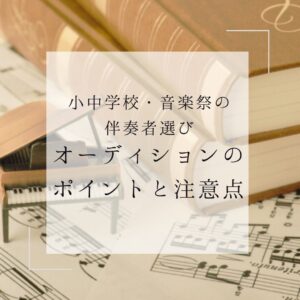
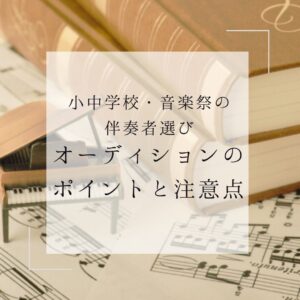
この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿