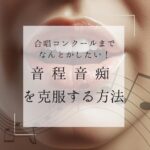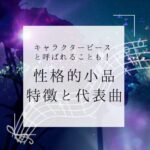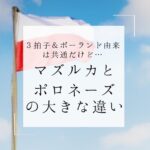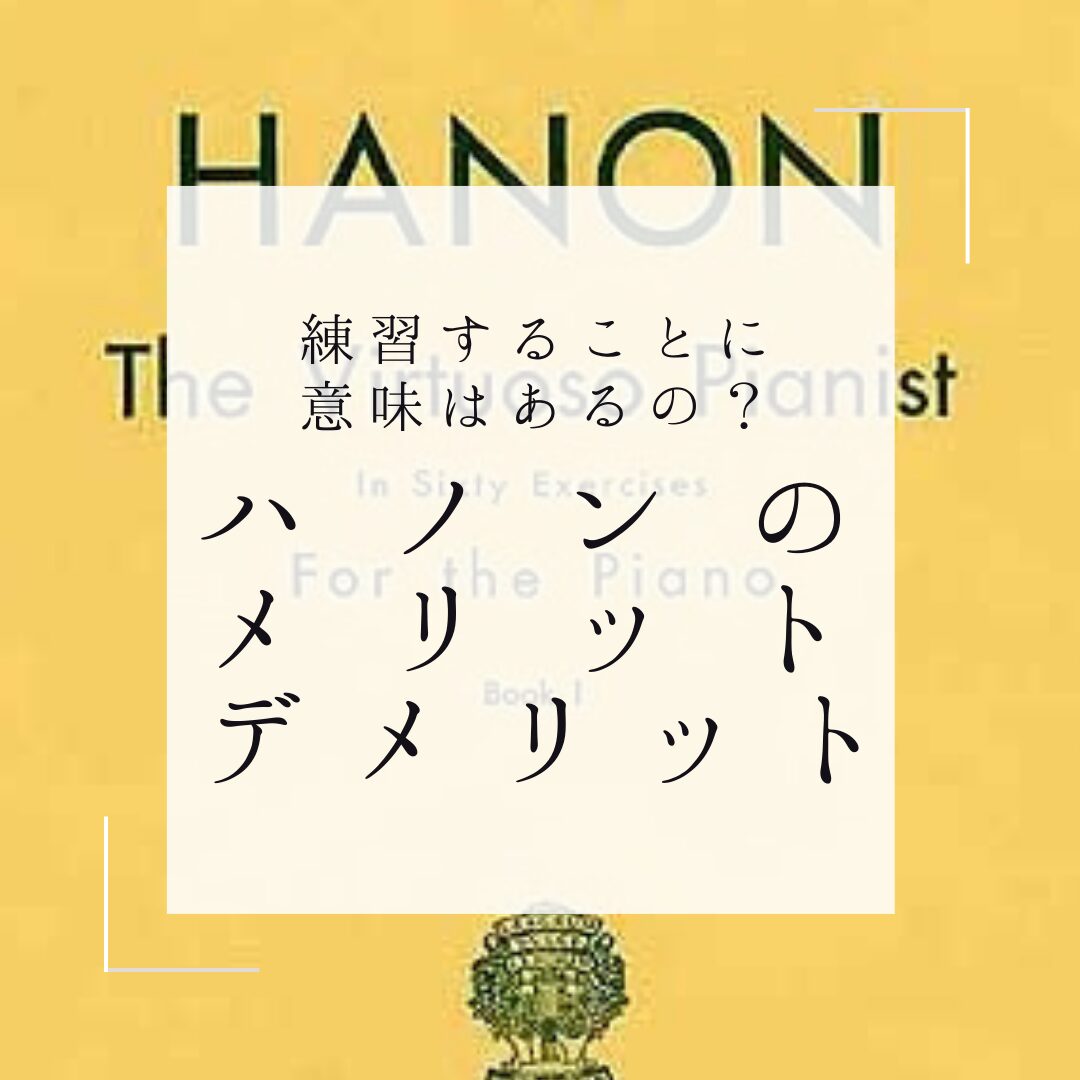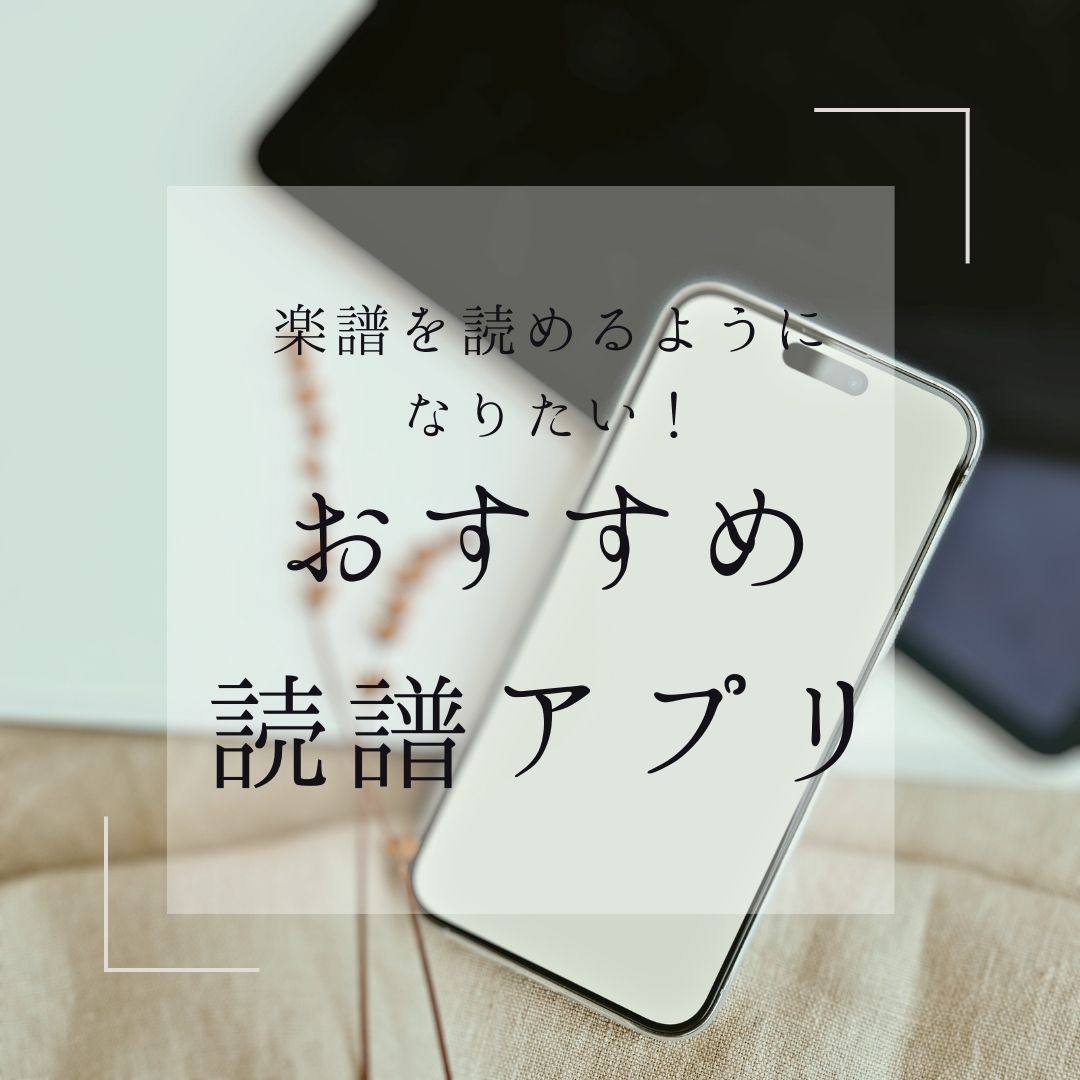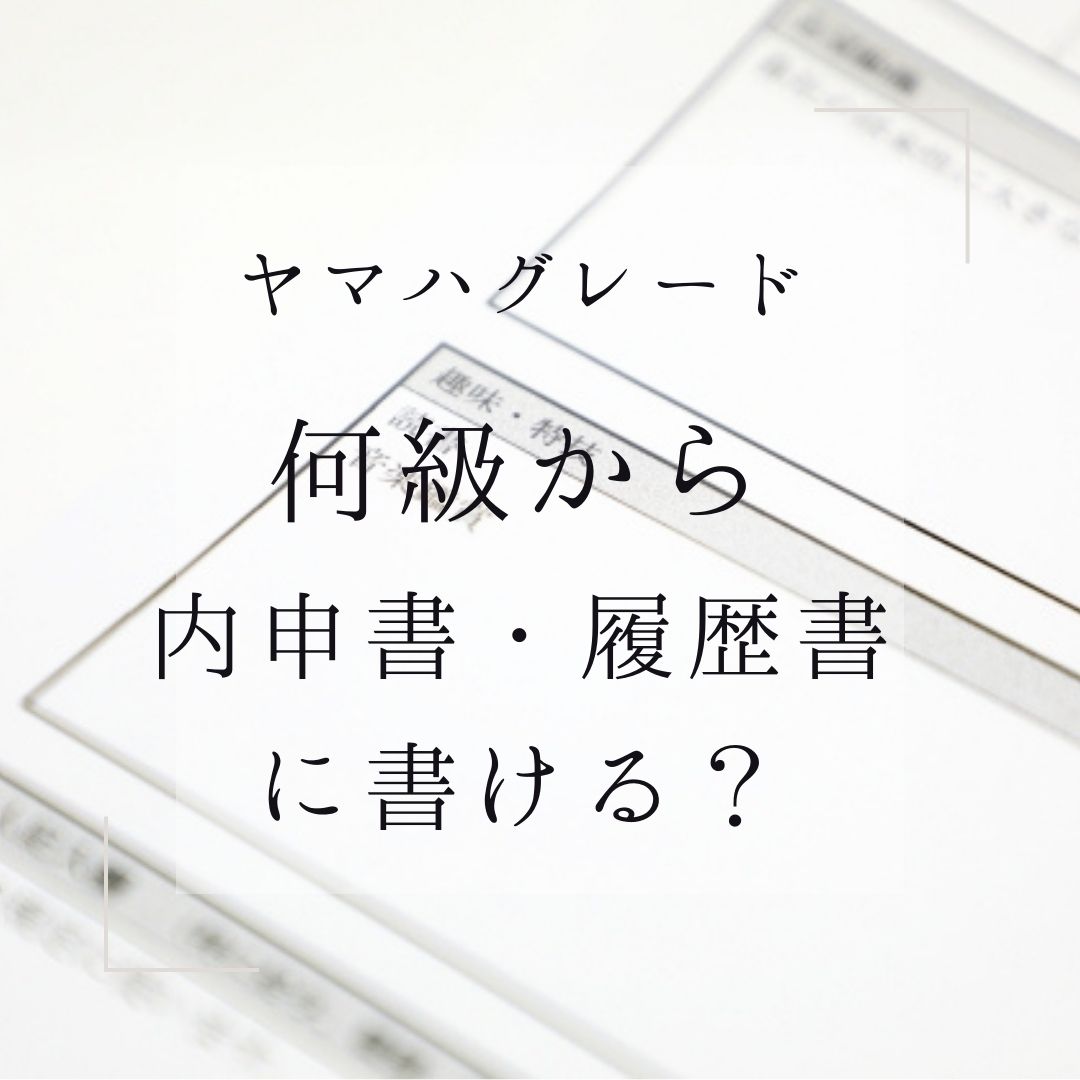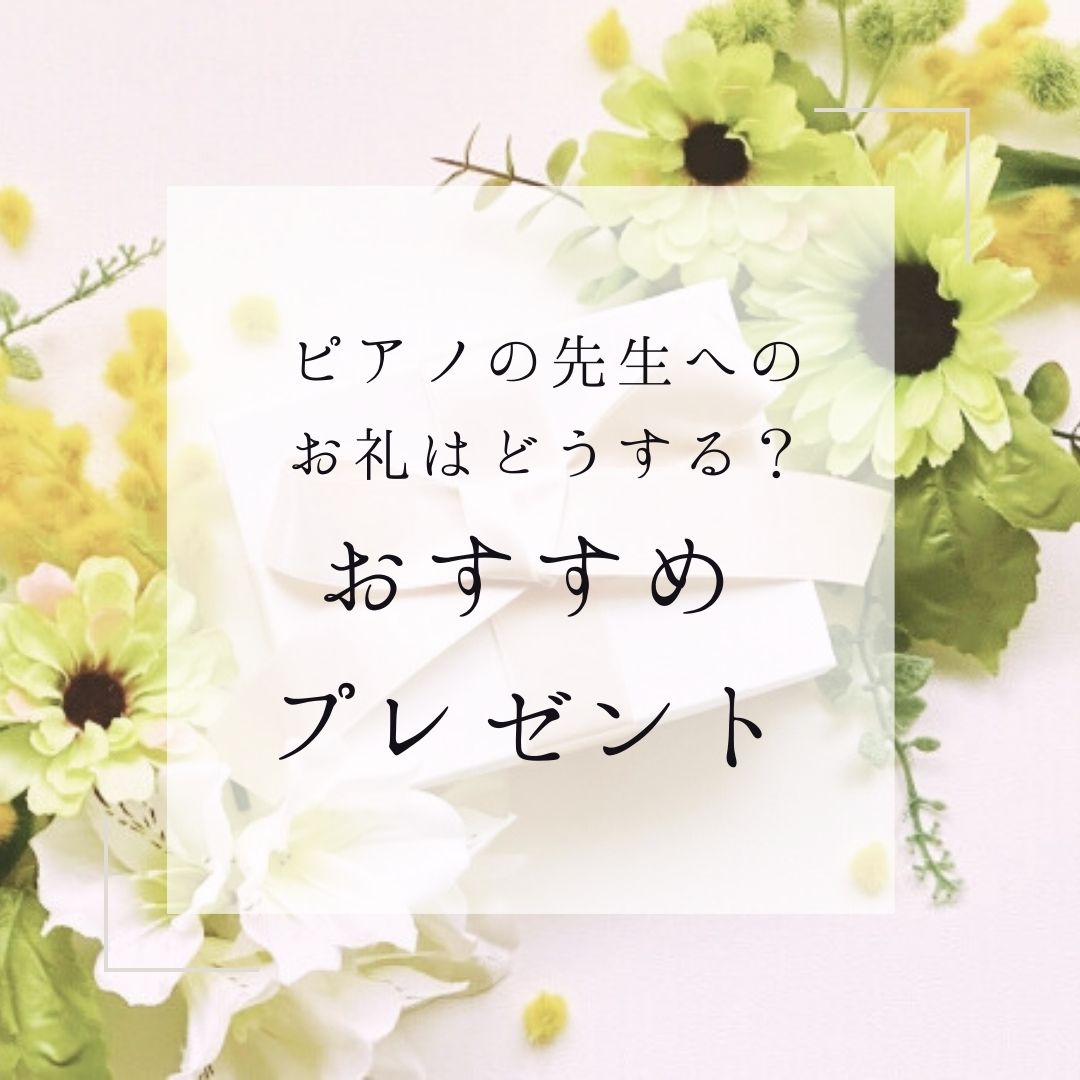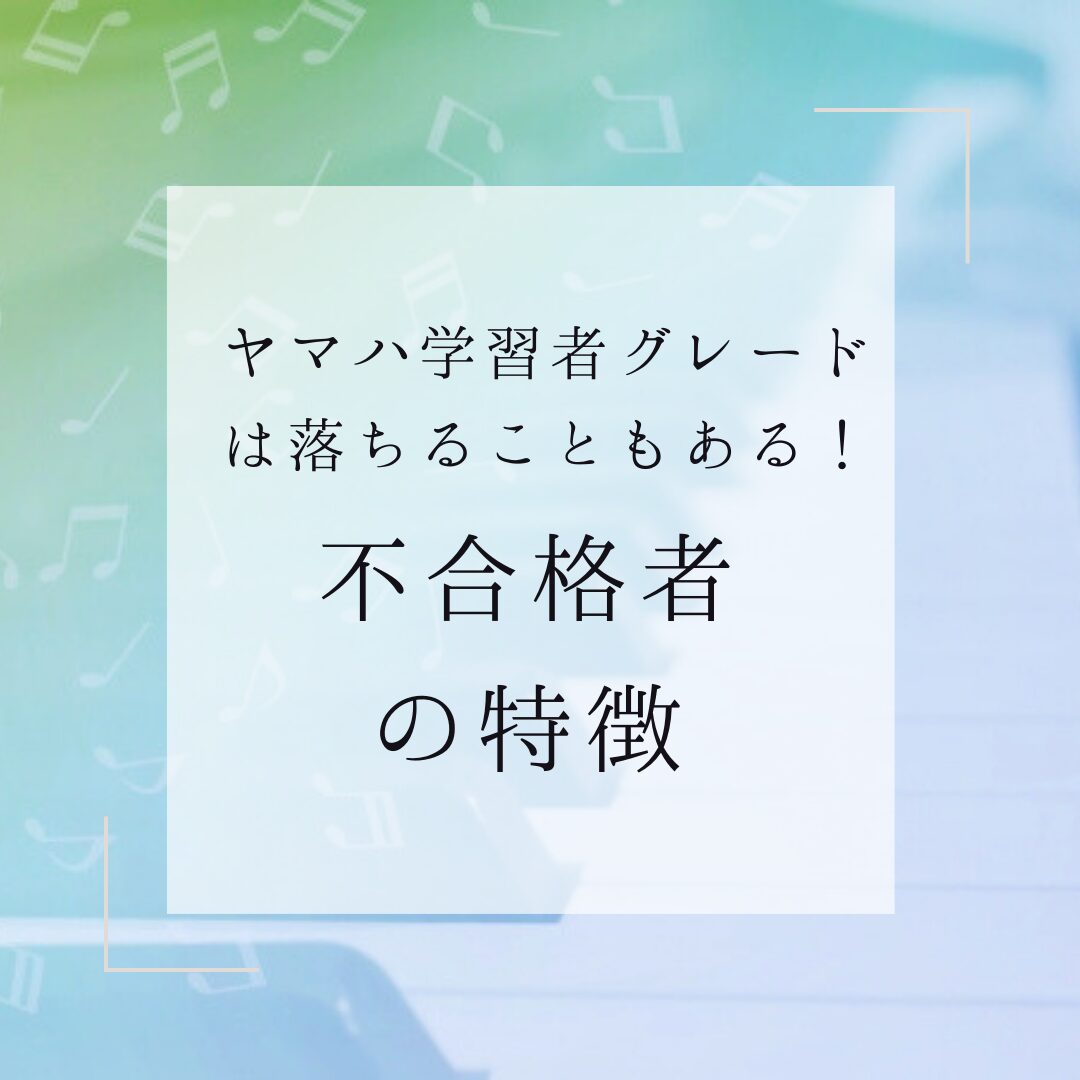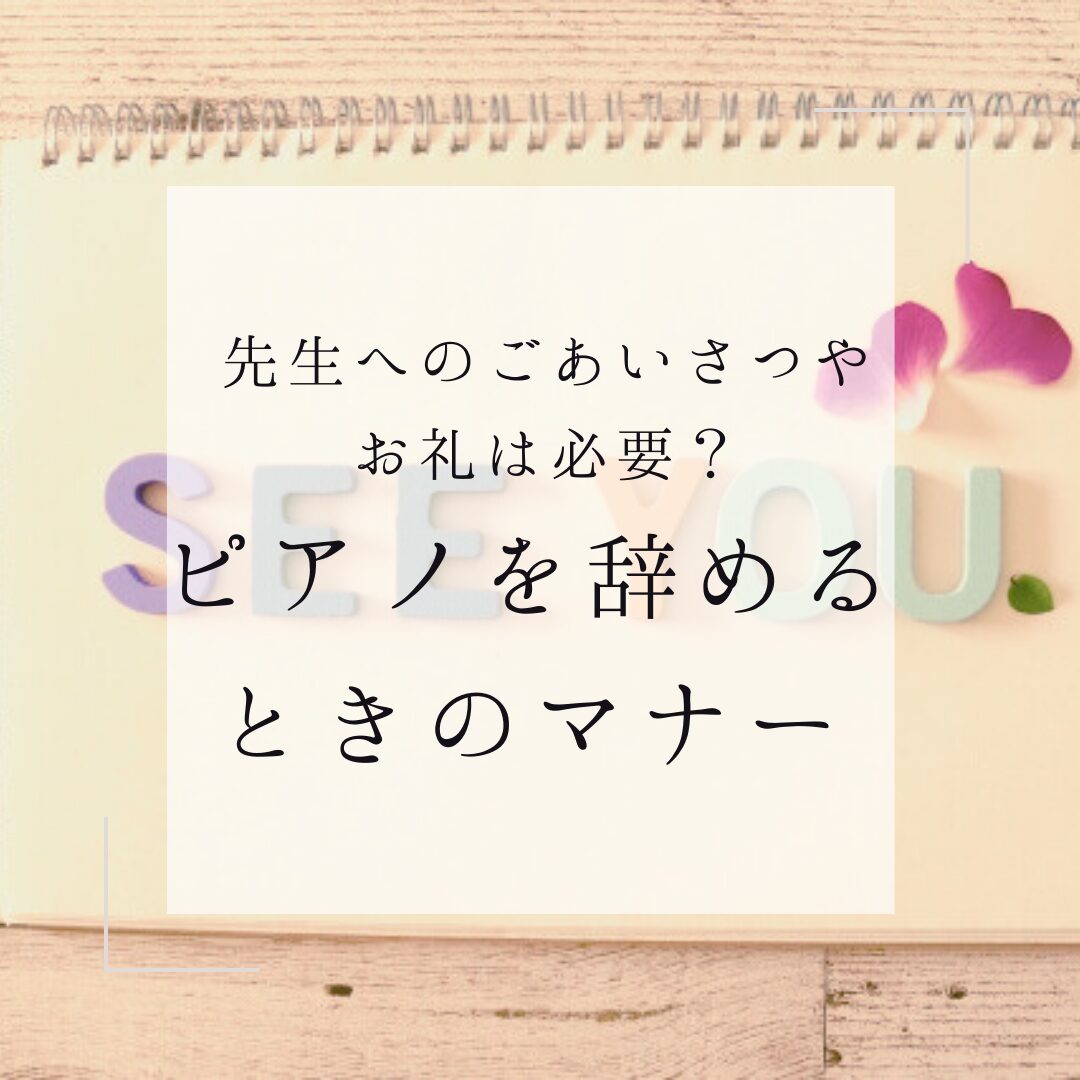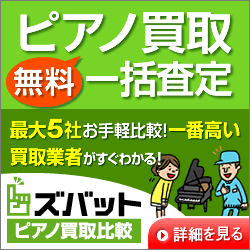ピアノを習ったことがある人なら、レッスンで使ったことがあるかもしれない教材の一つにハノン(HANON)が挙げられますね。
現在も、いわゆる「指の運動」として、5本の指を鍛えるためにレッスンで使用しているところも多いのではないでしょうか?
この記事は
- 現在ハノンをレッスンで使っている
- ハノンを練習することに意味はあるの?
- ハノンの練習をするメリット・デメリットを知りたい
という生徒や保護者、ピアノの先生におすすめです!
今回はハノンの特徴と、ハノンを練習するメリットやデメリットについてご紹介します。
なんで練習するんだろう?
ピアノ教本「ハノン」の作曲者と教本の特徴


ピアノを習っていると「ハノン」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか?
実際は人の名前なのですが、指のトレーニングをする教本自体を指す場合が多いですよね。
はじめに作曲家ハノンと、ハノンが作曲した教本について説明します。
作曲家:Hanon,C.L.
ハノンはフランスの作曲家です。
作曲家であるほか、ピアノやオルガンの先生や、教会で演奏家として活躍していた一面もあります。
Charles-Louis Hanon が正式な名前で、「シャルル ルイ アノン」と発音します。
でも日本では「アノン」とは呼ばずに「ハノン」と呼ぶ傾向にありますね。
フランスでは「アノン」と呼びますが、ドイツやイギリスでは「H」も発音するので「ハノン」として日本で浸透しているそうです。
1819年に生まれ1900年に亡くなりましたが、その間に次のような作品を作曲しています。
- 60の練習曲によるヴィルトゥオーゾ・ピアニスト(これが一般的にハノンと呼ばれているもの)
- 大作曲家の名曲より要約
- 初歩のピアノ教本
- 50の歌曲集
有名な「60の練習曲によるヴィルトゥオーゾ・ピアニスト」以外にも「初歩のピアノ教本」という別の教本があることが分かりますね。
ハノン本人は
「60の練習曲によるヴィルトゥオーゾ・ピアニスト」で指を鍛え、表現力を磨くために「大作曲家の名曲より要約」を用いて美しいメロディーに触れてほしい
という言葉を残しています。
歌曲も作曲してた!
「60の練習曲によるヴィルトゥオーゾ・ピアニスト」の構成
昨今では「ハノン」というと、この「60の練習曲によるヴィルトゥオーゾ・ピアニスト」を指すことがほとんどです。
ヴィルトゥオーゾ=イタリア語で「達人」「名手」という意味
なので「ピアノの達人を目指すための60の練習曲」といったところでしょうか。
この教本は、3部構成でできています。
- 第一部(1~20番)
- 第二部(21~43番)
- 第三部(44~60番)
第一部では、5本の指の独立を目指すために様々な音型を練習していきます。
第二部では、第一部の音型をさらに発展させたものと、スケールとカデンツ、半音階、アルペジオなどを練習します。
第三部では、「最高のテクニックを身につけるための練習」となっていて、同音連打やトリル、分散スケールや分散アルペジオ、トレモロなどのより高度な技術の習得を行います。
ピアノ教本「ハノン」の特徴
ハノンの練習曲は、短いフレーズで同じ音型が繰り返される構成。
指の独立性を高め、均等な音を出すことを目的としているため、単純なメロディーではなく、パターン化された動きが中心です。
「ハノン」を全部弾くとどのくらいの時間がかかる?


ハノン本人は
この全巻は1時間あれば弾けます!
と言葉を記しています。
しかし60個の練習曲を1時間で行うのは、不可能です。
youtubeなどで『ハノンを弾いてみた』という動画がありますが、全曲合計して2時間はかかるようですね…。
ハノン本人は実際に全曲をどのくらいの速さで弾いていたのでしょうか?
気になるところ♪
なぜ「ハノン」を練習するのかを理解していない人は多い


現在の日本のピアノレッスンでも、指の運動としてハノンを取り入れているところが多いですよね!
過去を遡ってみると、ピアノレッスンは
バイエルとハノン!
という感じで、必ず使っていた時代もあったといわれています。
最近ではその傾向は少し薄れつつあるようですが、ハノンをレッスンに取り入れている先生は今でも多いですよね。
しかし、生徒時代の私もそうでしたが、生徒の中には
なんでこんなつまらない運動を何回もしないといけないんだろう?
と思う人も存在していることは確かです。
しかも、ハノンさんは「1番~5番を毎日1回以上弾きなさい」などという指示まで書いています。
とよく思ったものです。
このように「ハノンを練習する意味や必要性」を理解していない生徒は意外に多くいるため、教本を渡すときは
どうしてこの本を使って練習するのか
を話しておく必要があるでしょう。



言われるがままに練習してた…
ハノンを練習するメリット


では、ハノンを練習することでどんな力が身につくのでしょうか?
まず、ハノンを練習するメリットをご紹介します。
指が強くなる
まず一つ一つの指を均等に動かすことで、それぞれの指がまんべんなく強くなります。
「指の筋トレ」をイメージするといいかもしれませんね。
ピアノ演奏では、すべての指を均等に使うことが求められます。
しかし、日常生活では1の指(親指)や2の指(人差し指)は多く使いますが、4の指(薬指)・5の指(小指)はあまり使用することがありません。
そのため、4・5の指は他の指と比べると弱くなりがちです。
ハノンを練習することで、これらの弱い指を鍛え、スムーズな演奏が可能になります。
もう1つは「指の持久力をつける」といったところでしょうか。なんだか体育会的ですね!
指の独立性が高まる・持久力がつく


ハノンでは、さまざまなパターンの音型を反復練習することで、5本の指を鍛え独立させていきます。
また、同じ音型を繰り返し弾くことで指に持久力がつきます。
ただ楽譜の通りに弾くだけでなく、いくつかのリズム練習を取り入れ、左右揃えて弾くことを意識するといいでしょう。
このように練習することで、早いパッセージを弾くときに転びやすい4・5の指が鍛えられるほか、音の粒をそろえる練習にもなりますね。
テクニックの向上につながる
ハノンは音型反復の練習だけでなく、スケールやアルぺジオなども登場します。
そのため、この教本一冊で基本的なピアノ技術を効率よく身につけることも可能です。
この教本で得たテクニックは、クラシックだけでなくポップスなど幅広いジャンルの曲を演奏する際にも役立つでしょう。
\スケール練習にも意味がある/
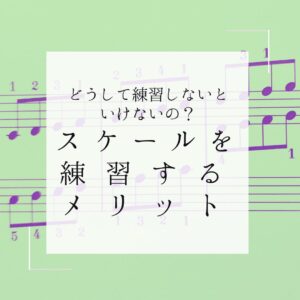
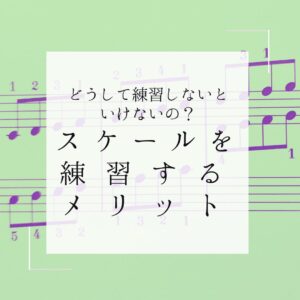
運指がスムーズになる
指の動きをパターン化して鍛えることで、実際の楽曲を演奏する際に指の運びがスムーズになります。
特に速い曲や難しいパッセージにも、スムーズに対応しやすくなるでしょう。
\よく見るハノン教本は全音版/


ハノンを練習するデメリット
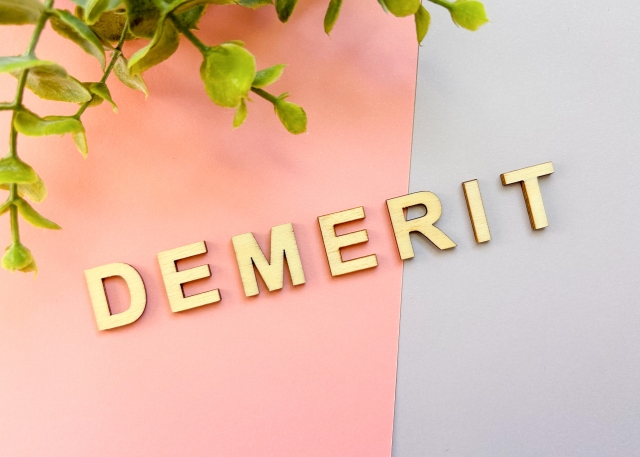
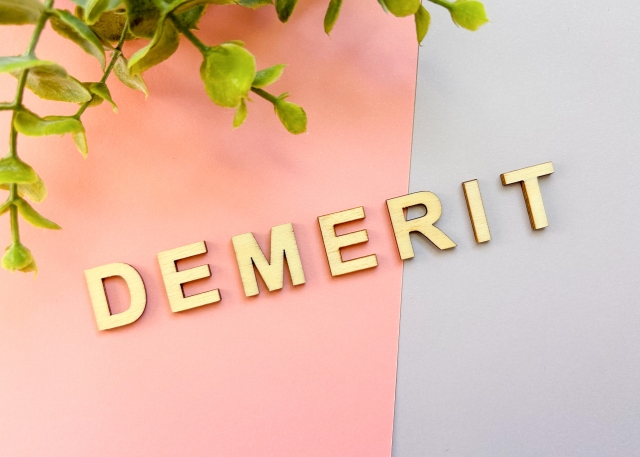



ハノンを弾くのに、どんな意味があるの?



これって何の練習?
ハノンの【第一部】1~31番をやったことがある人なら、一度はこのように思ったことがあるのではないでしょうか?
メロディーがあるわけでないし、ハーモニーがあるわけでもない
ハノンは機械的な音型の羅列ともいえますね。
ここからは、ハノンを練習するデメリットをご紹介します。
表現力の向上は期待できない
ハノンは主に指のトレーニングに特化しているため、楽曲の表現力や感情を豊かにする練習には向いていません。
同じ音型の反復だけを練習していても、表現力を身につけることはできません。
音楽的な表現を磨くには、実際の楽曲を演奏することも大切ですよ!
譜読みの練習には向かない
ハノンが譜読みの練習になるかというと、そうとはいえません。
同じ音型の反復なので、最初の一小節だけ読めてしまえば、あとはスライドしていけば良いので、音型を覚えてしまう人も多いのではないでしょうか?
もしくは、ある程度譜読みに慣れている場合は初見で弾けてしまうため、譜読みの練習にはならないでしょう。
\読譜力を上げたい方はこちら/
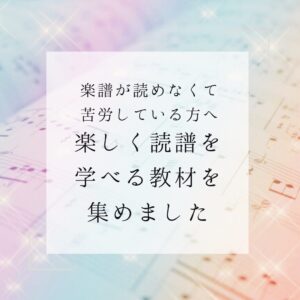
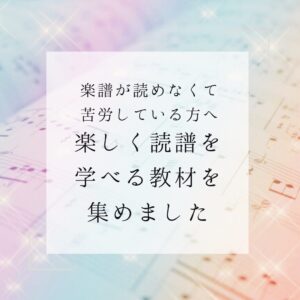
やる気がなくなりやすい


一番困ってしまうのは「生徒のやる気がなくなる」という点ではないでしょうか?
特に小さい子どもの場合は、ハノンのように同じことを何回も繰り返してやることは飽きる原因にもなりますね。
という生徒を生み出しすこともあります。
大人でも
- なぜこの練習が必要なのか
- 練習する意味
を説明してもらわないと、やる気が出ませんよね?
このように、単調な音型の繰り返しとなるハノンは、継続するモチベーションを保つことが難しいと感じる人も少なくありません。
無理な練習が手を痛める原因になる
ハノンはフォルテ(強い音で)指をはっきり動かして弾くように指示が書いてあります。
そのためハノンだけに時間をかけて練習している生徒は、上手に脱力することができず力任せに弾いてしまう傾向にあるようです。
ハノンに時間をかけすぎると
- どんな曲もフォルテで弾きゴツゴツした演奏になりやすい
- 手や指・腕などを痛めてしまう
このような悪循環を生み出すことも考えられます。
そうならないためにも、 ほかの楽曲や練習曲(エチュード)などを通して、表現を磨いていく必要がありますね。
ハノンを練習するときは、正しい姿勢と音の出し方を意識しながら、無理のない範囲で練習を続けることが重要です。
\フォームをチェック!/
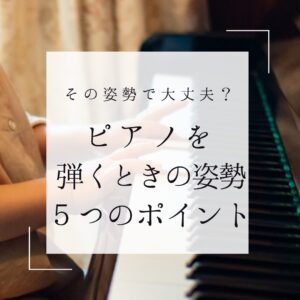
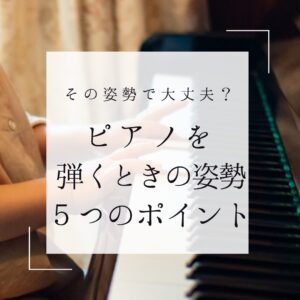
テクニック&表現力をバランスよく身につけることが大切


ハノン教則本は今でも多くのピアノ教室で使われています。
その使い方は先生によってさまざまあるかと思いますが、 ハノンだけに時間をかけてしまうと練習嫌いの生徒が生まれたり、音楽的表現に欠ける生徒が生まれたりすることもあります。
指を鍛えることは大事ですが、そこだけに重きを置かないように気をつけて、ほかの楽曲や練習曲を使ってテクニックや表現方法をバランスよく磨いていきましょう!
メリットとデメリットを理解したうえで、正しい練習方法を取り入れることで、より効率的にピアノの技術を向上させることができますよ。
\なんとなく弾いてない?/
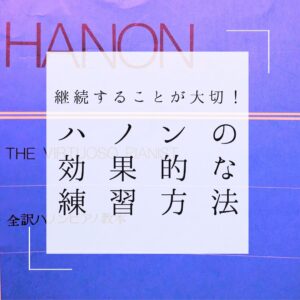
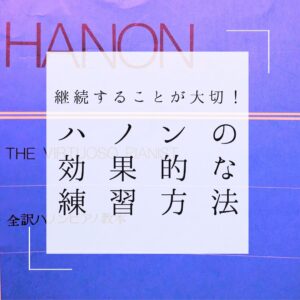
この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿