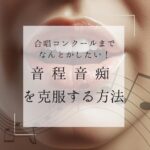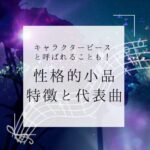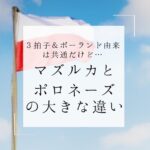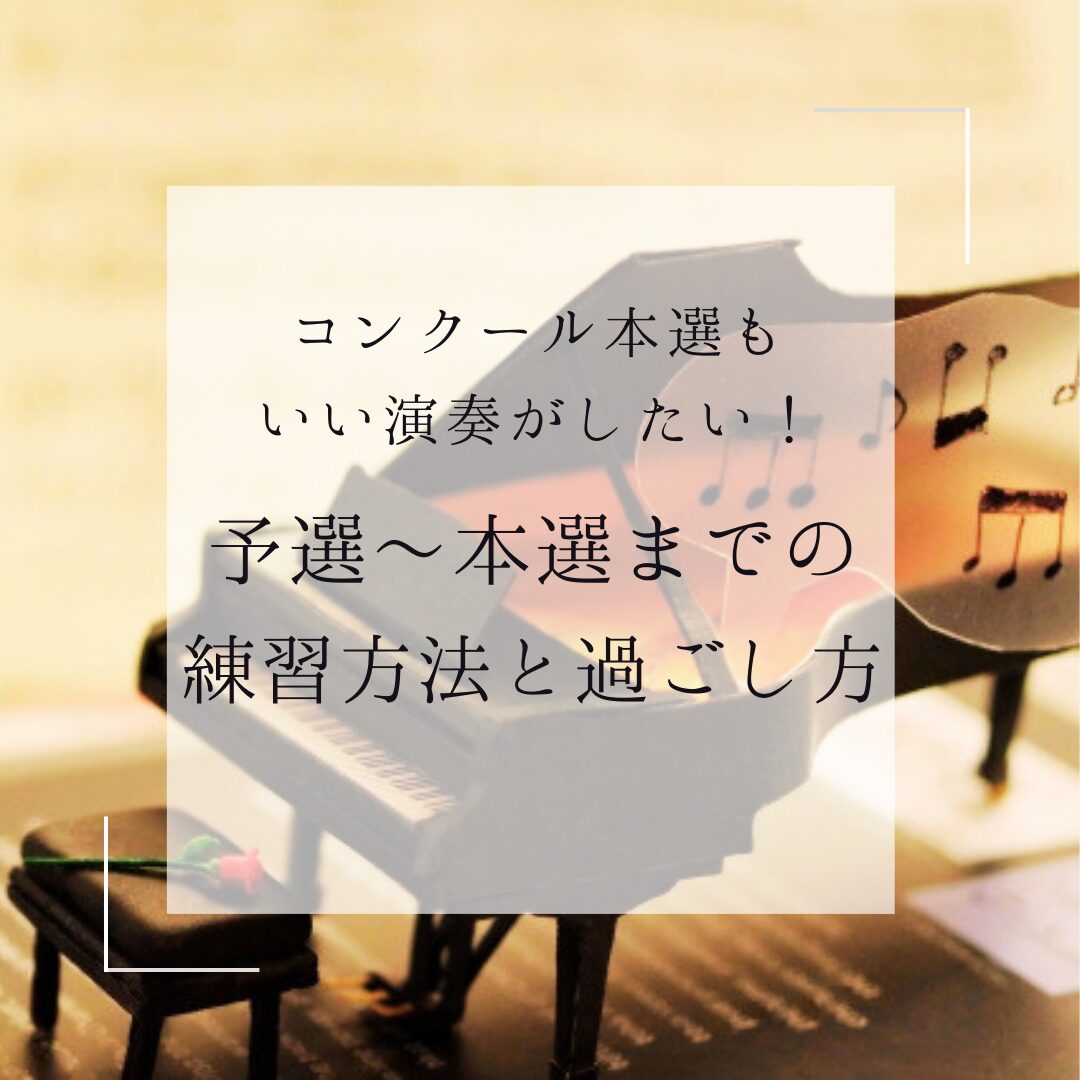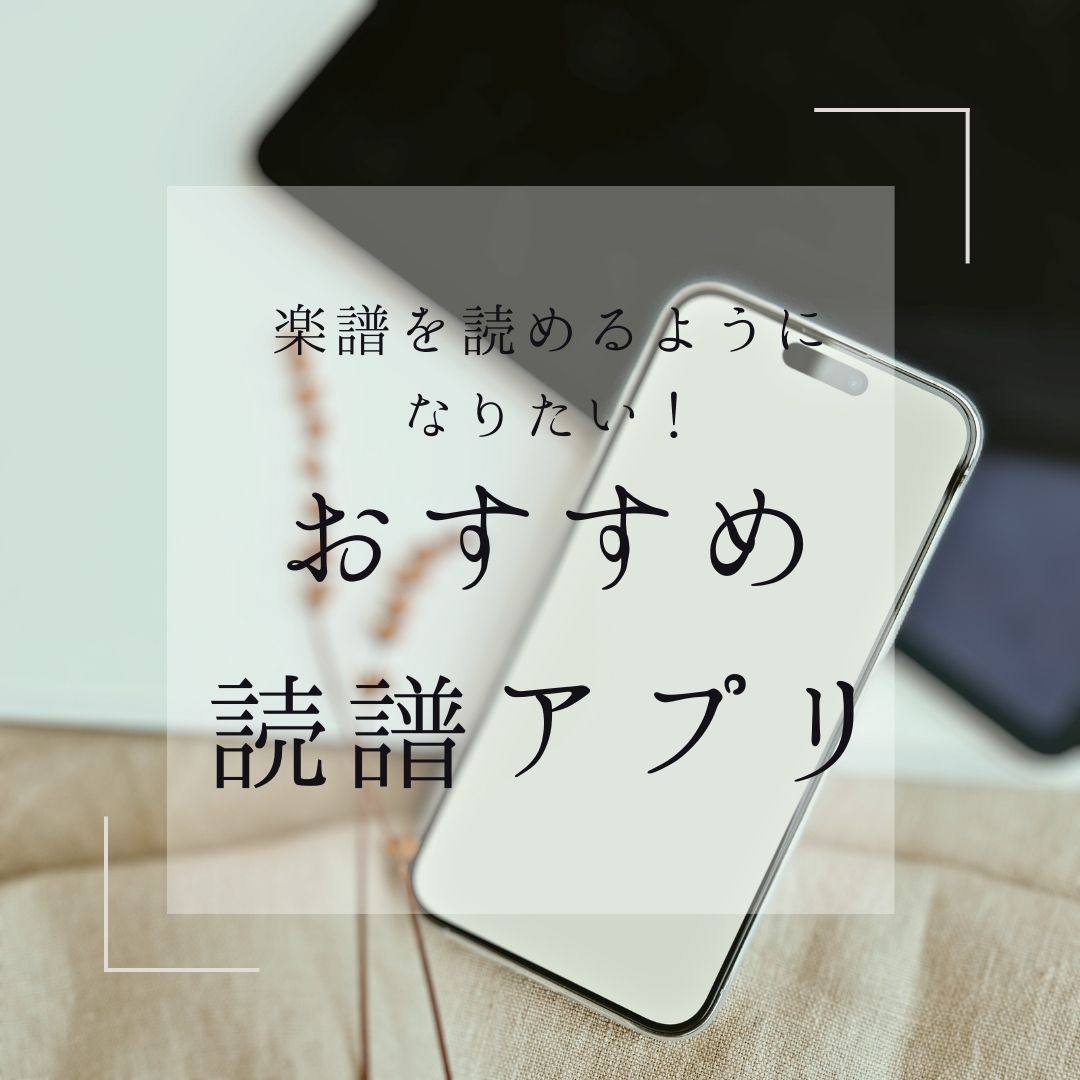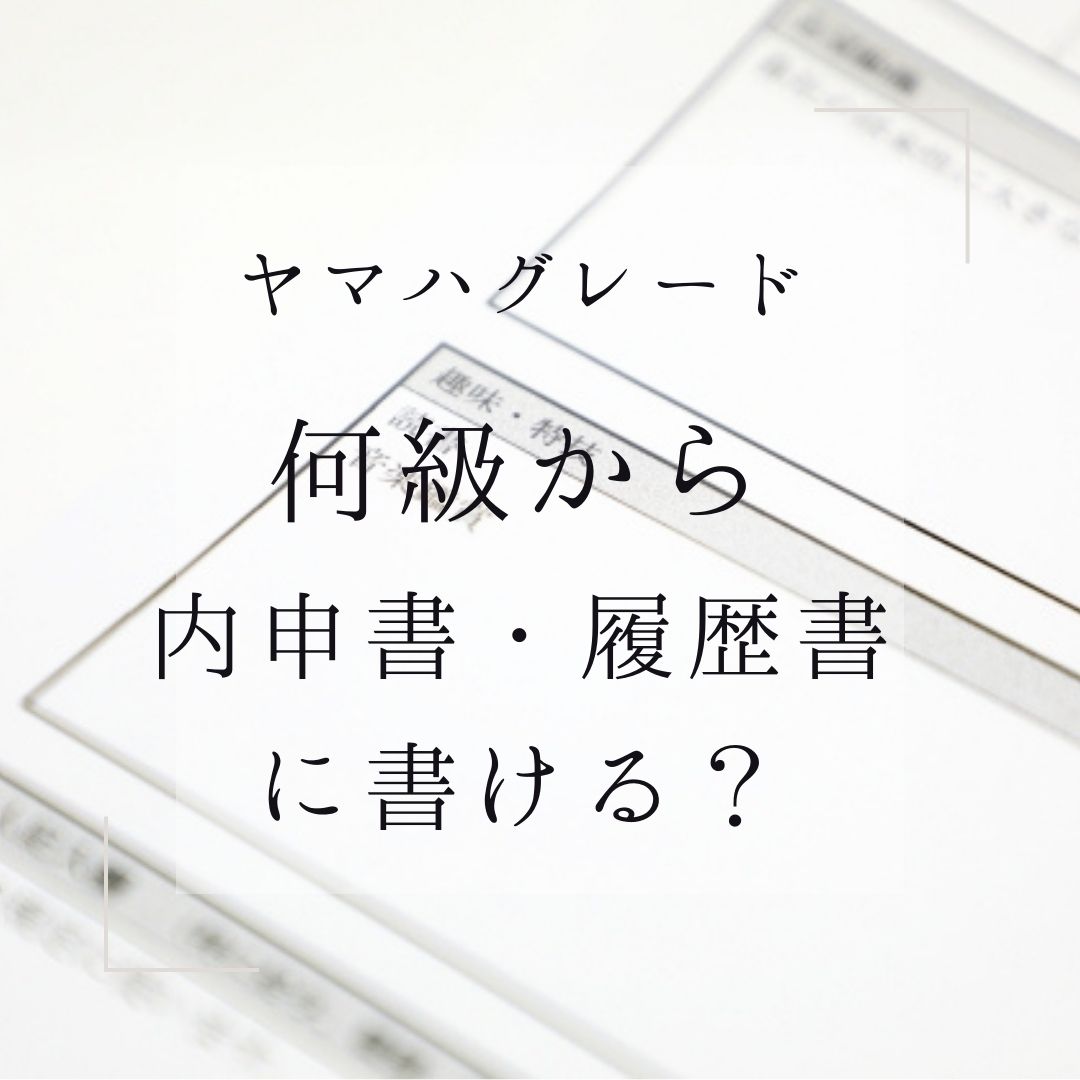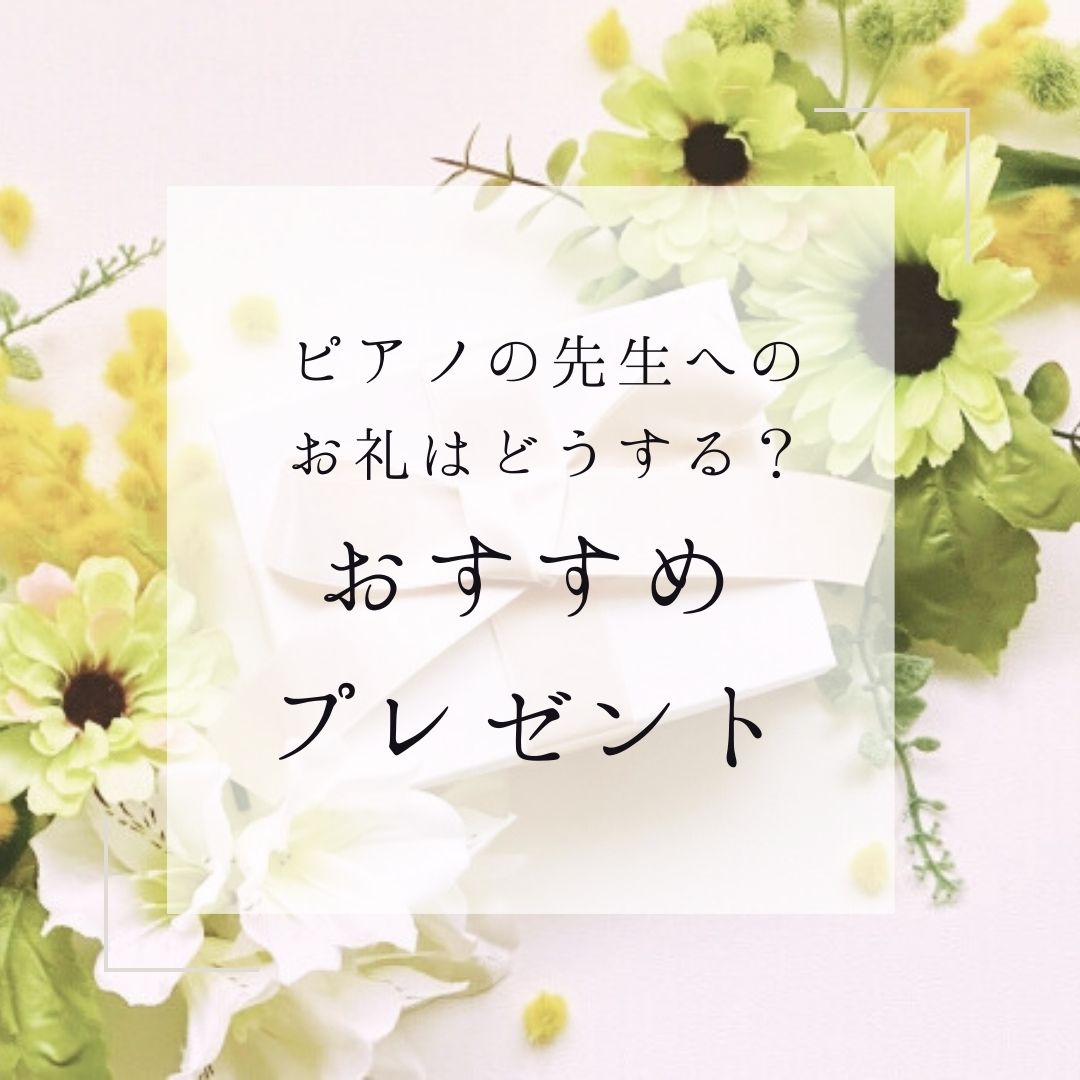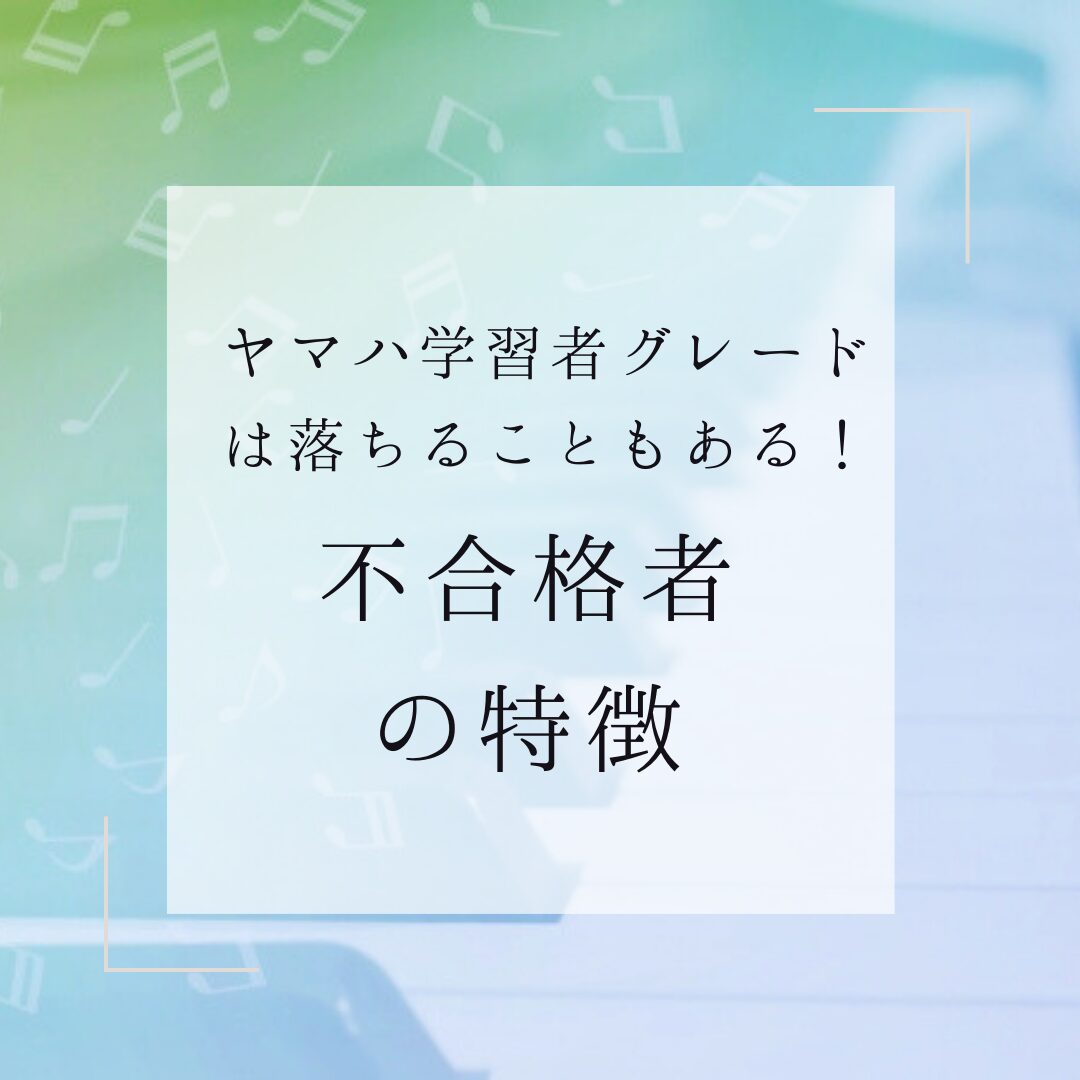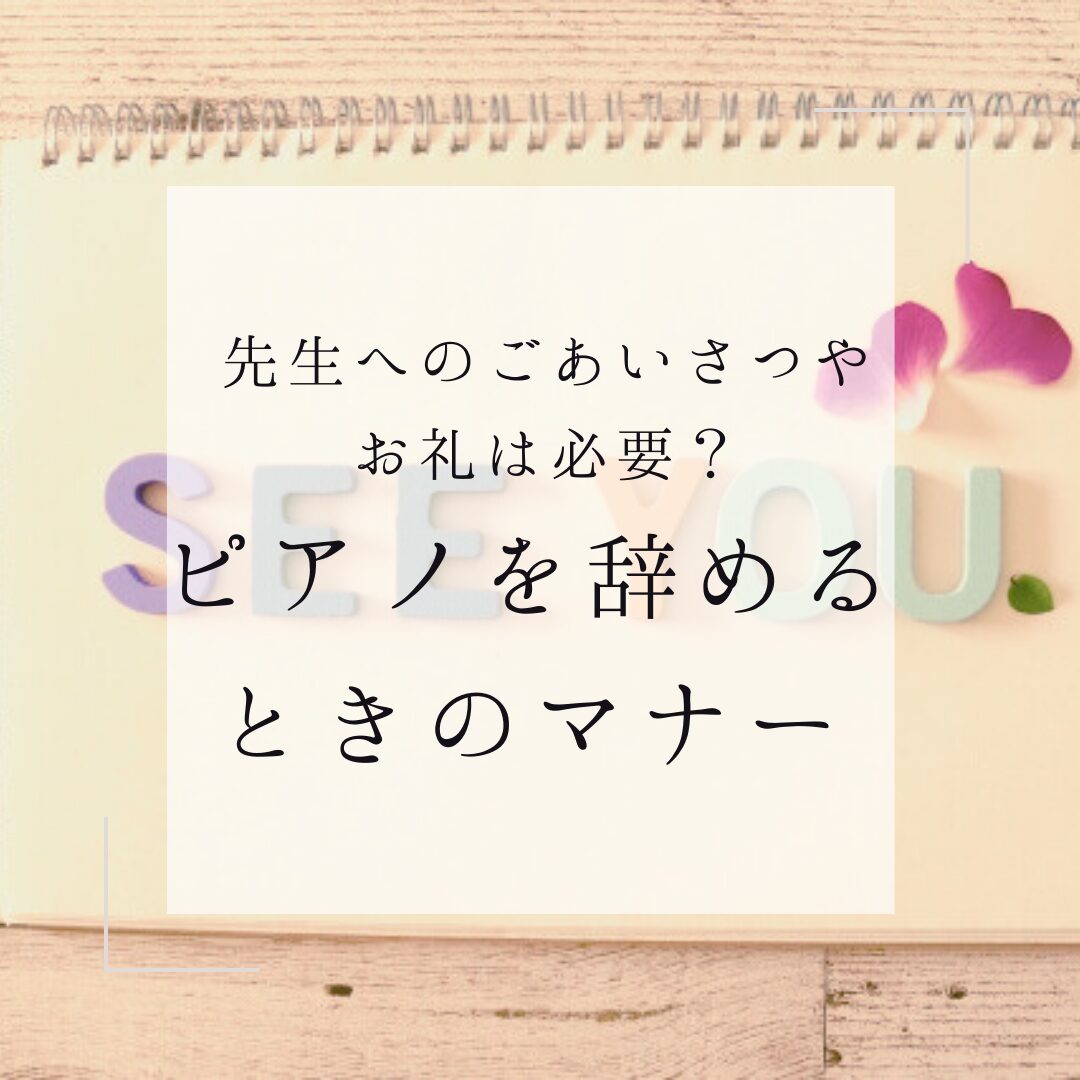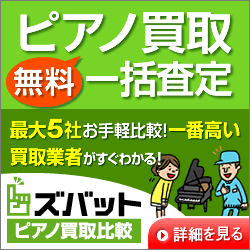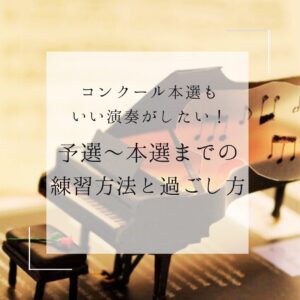ピアノのコンクールの予選を見事通過し、次はいよいよ本選・・・!!
というあなた、予選から本選までの過ごし方や練習方法は「予選までと同じ」では本選で思うような結果が出ないかもしれませんよ?
この記事は
- 予選を通過してこれから本選へ臨む方
- 予選はいい演奏ができるけれど本選でうまくいかない方
- 本選までの練習方法を知りたい方
- 本選で最大限の力を発揮したい方
におすすめです!
ピアノのコンクールは、テクニックや音楽性の高さを競う場であると同時に、自身の成長のための大きなステップにもなりますよね。
予選から本選までどのように時間を使うかは、結果に大きく影響します。
今回は長年指導してきた経験をもとにコンクールに向けた効率的な練習方法と、精神的な準備に焦点を当てて、その過ごし方を詳しく解説します。
一日一日を大切に過ごそう♪
予選通過後の練習方法・6つのポイント


コンクールの予選通過後は、本選に向けてどのように過ごすかが課題です。
本選は各地の予選を勝ち抜いてきた人が集まるため、よりハイレベルになることは間違いありません。
予選後の期間は、より高いレベルの演奏を目指すための重要な時期と考え、練習方法も本選用に変えていきましょう!
ここから本選までの期間、ぜひ練習に取り入れてほしいことをご紹介します。
練習メニューに取り入れてみて♪
講評・フィードバックを活用する
予選が終わると審査員からの講評用紙・フィードバックをもらえることがあります。
そこには、本選に向けて改善すべきポイントがたくさん書かれているはず!
審査員のコメントは、自分の演奏を客観的に振り返ることができるチャンスです。
ときには今習っているピアノの先生が気づかないようなことを書いてくれたり、逆に普段先生から言われていることとまったく違うことが書かれていたりすることもあるかもしれません。
特に、自分が気づかなかった弱点や、表現の細かい部分を指摘された場合は、その部分を重点的に強化するメニューが必要になるでしょう。
一方で普段言われていることと異なることが書かれている場合は、もう一度先生とよく相談して納得のいく演奏にしましょう。
表現の部分については審査員の好みによる部分が大きいので、一人の審査員が書いたことを鵜呑みにしてしまうのは危険な場合もあります。
審査員のコメントは、本選までの糧になるように【本選への課題】として自分なりにまとめたメモを楽譜に貼っておくと振り返りやすいですよ。
違う曲も弾いて気分転換する


予選と本選の曲が同じ場合は、本選までコンクールの曲だけでなく違う曲も弾いてみましょう。



コンクールの曲だけ頑張ればいいんじゃないの?
子どもにとっては、このように「この曲だけ頑張ればいい」と思うかもしれません。
しかし、ずっと同じ曲を半年も弾き続けていたら飽きてしまいますし、演奏も雑になってきてしまいます。
「同じ曲ばかりでなく違う曲も弾いて気分転換しましょう」
これは実際にコンクールの全体講評で審査員もお話しされていました。
予選で納得のいく演奏ができても、本選でボロボロになってしまう場合は、緊張する以外に
- 慣れすぎて雑になってしまう
- 飽きてやる気が出なくなってしまう
このようなケースが考えられます。
上手にほかの曲も弾いて気分転換しながら、コンクールの曲にも取り組んでいきましょう。
新しい曲の譜読みをしたり、これまで仕上がった曲を思い出して弾いてみたりするのがおすすめです!
ゆっくり片手ずつの練習に戻す
予選から本選まで同じ曲を練習する場合は、本選に向けてまたピークを作っていかなければいけません。
先ほどもお話ししたように、同じ曲を長期間練習すると飽きてしまうので、一度ゆっくり片手ずつの状態に戻してみましょう。
- 楽譜に書かれていること(スラー・スタッカート・速度の変化など)を再確認する
- 先生が記入したアドバイスをよく見て弾く
- しっかり打鍵できているか確認しながら弾く
- メロディーが歌えているか確認しながら弾く
- 左手(ハーモニーとベース)のバランスをよく聴いて弾く
片手ずつの練習に戻すときは、上記のことに気を付けてていねいに練習してくださいね。
両手だと見落としていることも片手なら気付ける♪
左手だけの暗譜ができているか確認する


曲が仕上がれば仕上がるほど、
両手なら弾けるけど片手だけだと弾けない
という生徒が増えてきます。
片手ずつ確認することの大切さは先ほどもお話ししましたが、もう一つぜひ練習メニューに取り入れてほしいのが左手だけの暗譜です。
それはなぜかというと…
コンクールで弾き直しをしたり、止まってしまったりして頭が真っ白になった際の原因は、私がこれまで見てきた限りほぼ左手にあるからです。
ここには右手と左手の役割分担が関係してくるので確認してみましょう。
多くの曲の場合、次のような役割分担で曲が作られています。
| 左手 | 右手 |
|---|---|
| 伴奏(ハーモニー・ベース) | 旋律(メロディー) |
メロディーは心の中で歌いながら弾くことができるので、緊張して音を外すことはあるかもしれませんが、頭が真っ白になって忘れることはあまりありません。
しかし左手は歌える要素が少ないため、暗譜の段階でわからなくなってしまうことがあります。
このような理由から、ぜひ本選前に左手だけ暗譜できているかを確認することをおすすめします!
\ちゃんと暗譜できてる?/
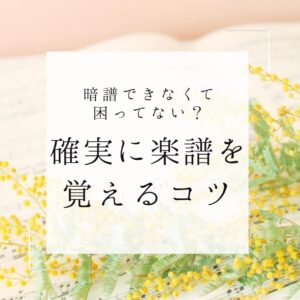
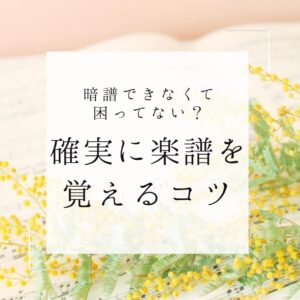
\左手の失敗しやすいポイントも紹介/
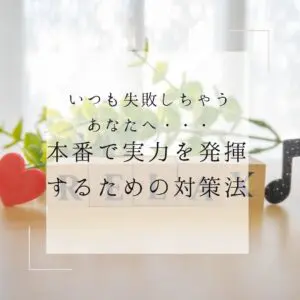
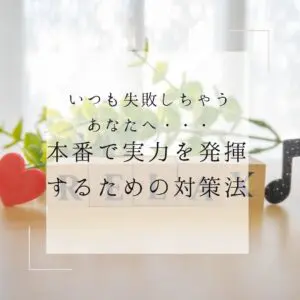
基本的なテクニックを強化する
コンクールでは、表現力はもちろんテクニックの正確も高く評価されます。
- 指が独立して動いているか
- 重音・和音をそろえて打鍵しているか
- 強弱
- リズムの正確さ
これらを強化するために、基本的なテクニックの練習としてハノンやスケール・アルペジオの練習を毎日のルーティンに組み込みましょう。
また、苦手なパッセージはゆっくりしたテンポで確実に演奏できるようにし、少しずつテンポを上げていく方法が効果的です。
\スケール練習に意味はある!/
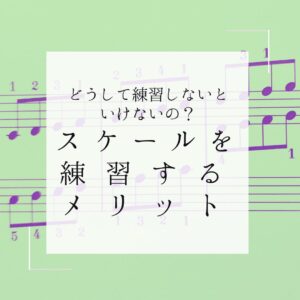
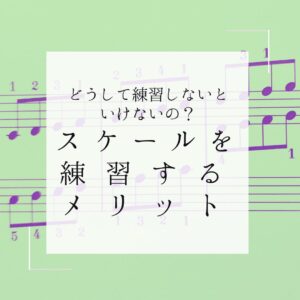
\スケール・アルペジオはこちらがおすすめ/
\ハノンで指の独立を促す!/
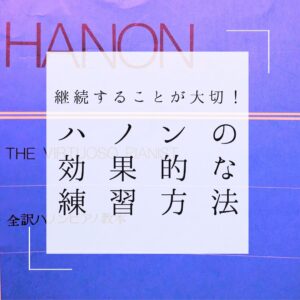
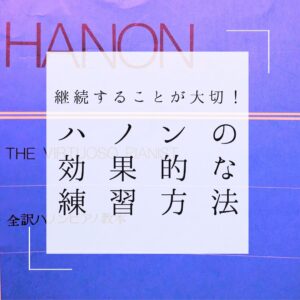
フレーズ練習・部分練習を強化する
全体を通して弾くことも大事ですが、特に難しい部分やな大切にしたいフレーズには、たっぷりと時間をかけて練習しましょう。
細かいフレーズの表現力をアップさせるためには、その部分を繰り返し練習し、各音のニュアンスを丁寧に確認することが大切です。
また、メロディーラインやハーモニーのバランスを意識して練習することで、より深みのある立体的な演奏が可能になりますよ。
部分練習に時間をかけよう♪
予選後~本選までの精神的な準備と過ごし方


コンクールの予選が終わってから本選を迎えるまでは、またあらたに精神面を作り上げピークを高めていかなければいけません。
ここからは予選後どのように過ごしたらよいのかを精神面に焦点をあてて考えていきます。
ゆったり過ごす時間も必要
予選が終わったら、少しゆったりする時間も必要です。
ずっと張りつめていた精神面を開放できるよう、ピアノ以外の趣味を楽しんだり、思い切り体を動かしたりしましょう。
本選に向けて、また精神面のピークを持っていけるように、リラックスする時間も作ってみてくださいね。
好きなことを思い切り楽しもう!
精神面の強化をする
「本選に向けて」に限らず、コンクールは本番に向けての精神的な準備も重要です。
緊張やプレッシャーを感じやすい場合は、リラクゼーションやイメージトレーニングを取り入れて、心の準備を整えましょう。
たとえば、深呼吸や瞑想を取り入れたリラクゼーション方法を練習に組み込むことで、落ち着いた心持ちで本番に臨むことができます。
また、ステージでの演奏をイメージしながらの通し練習も効果的です。
本番と同じ緊張感を意識しながら練習を重ねることで、実際の舞台でも安定した演奏が期待できますよ。
\具体的なメンタル強化方法はこちら/
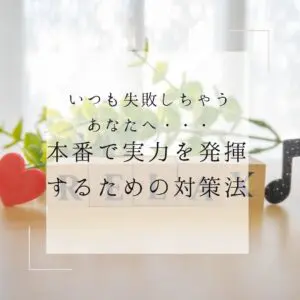
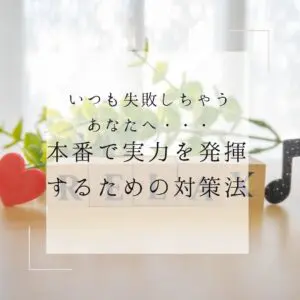
本選直前の過ごし方


本選の直前は、無理に新しいことを詰め込むよりも、これまでの練習を確認し、最終調整を行う期間にしましょう。
直前で違う指番号を試したり、表現方法を変えたりすると、本番で迷ってしまうことも…
直前に変更すると、あらたに取り入れたものがうまくいかず、焦ったりイライラしたりしてしまい、逆にメンタル面に悪影響を及ぼすことも考えられます。
なにか新しいことや別のことを試してみたい場合は、最低でも本番の一週間までとし、変更点がきちんと定着するまで練習することが大切です。
直前の変更はトラブルの元!
きちんと準備をして本選にピークを合わせよう


ピアノのコンクールは、予選から本選までの期間をどのように過ごすかが、本選の演奏の明暗を分けるカギとなるでしょう。
本選までは技術的な向上だけでなく、精神的な成長ももちろん必要です。
予選通過後の審査員や先生からのフィードバックを活かし、効率的な練習方法を取り入れながら、精神面でもコンクール本選にピークを合わせていきましょう!
徐々に気持ちを高めていこう♪
この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿