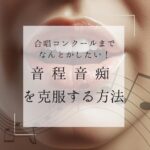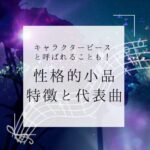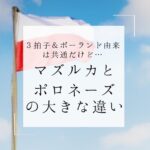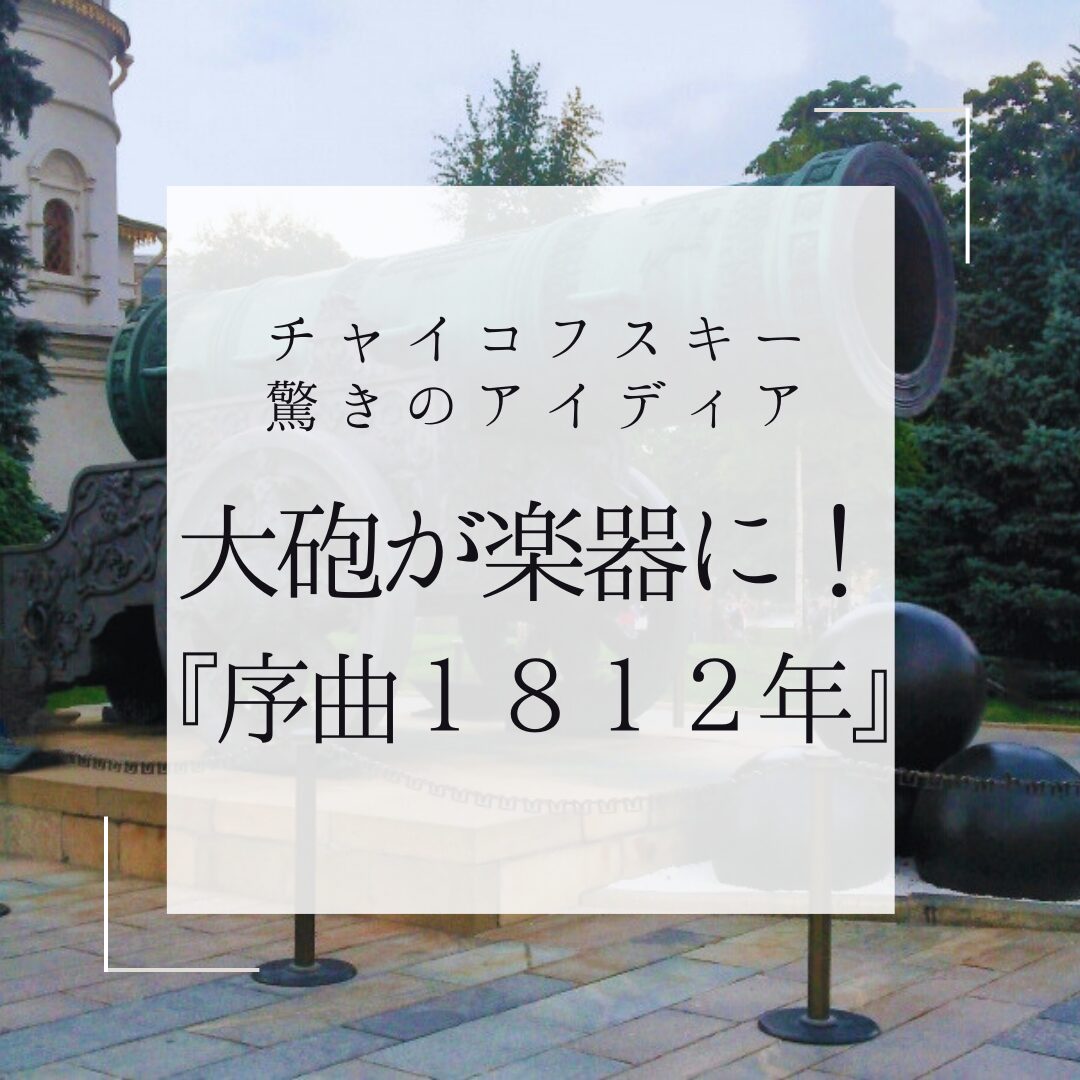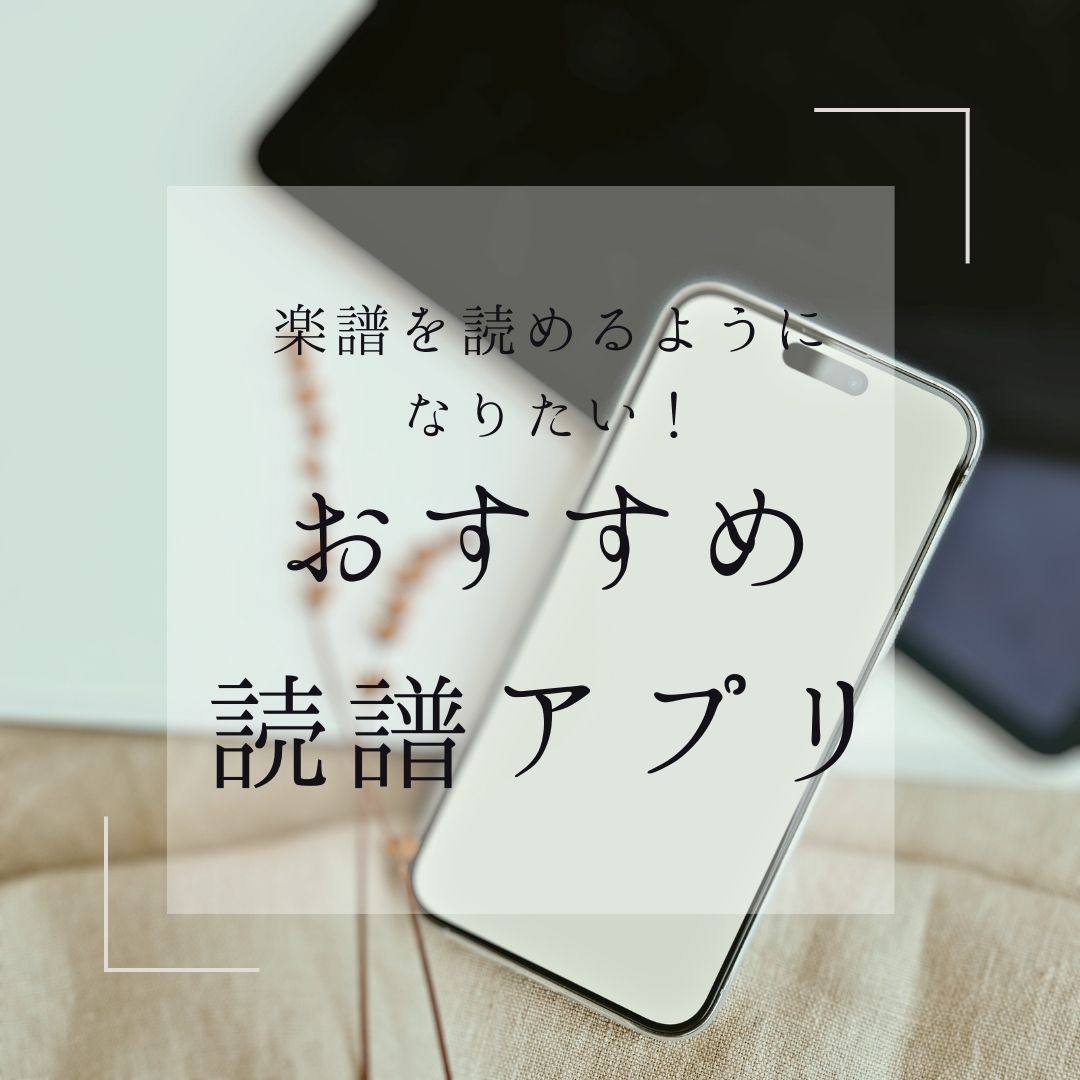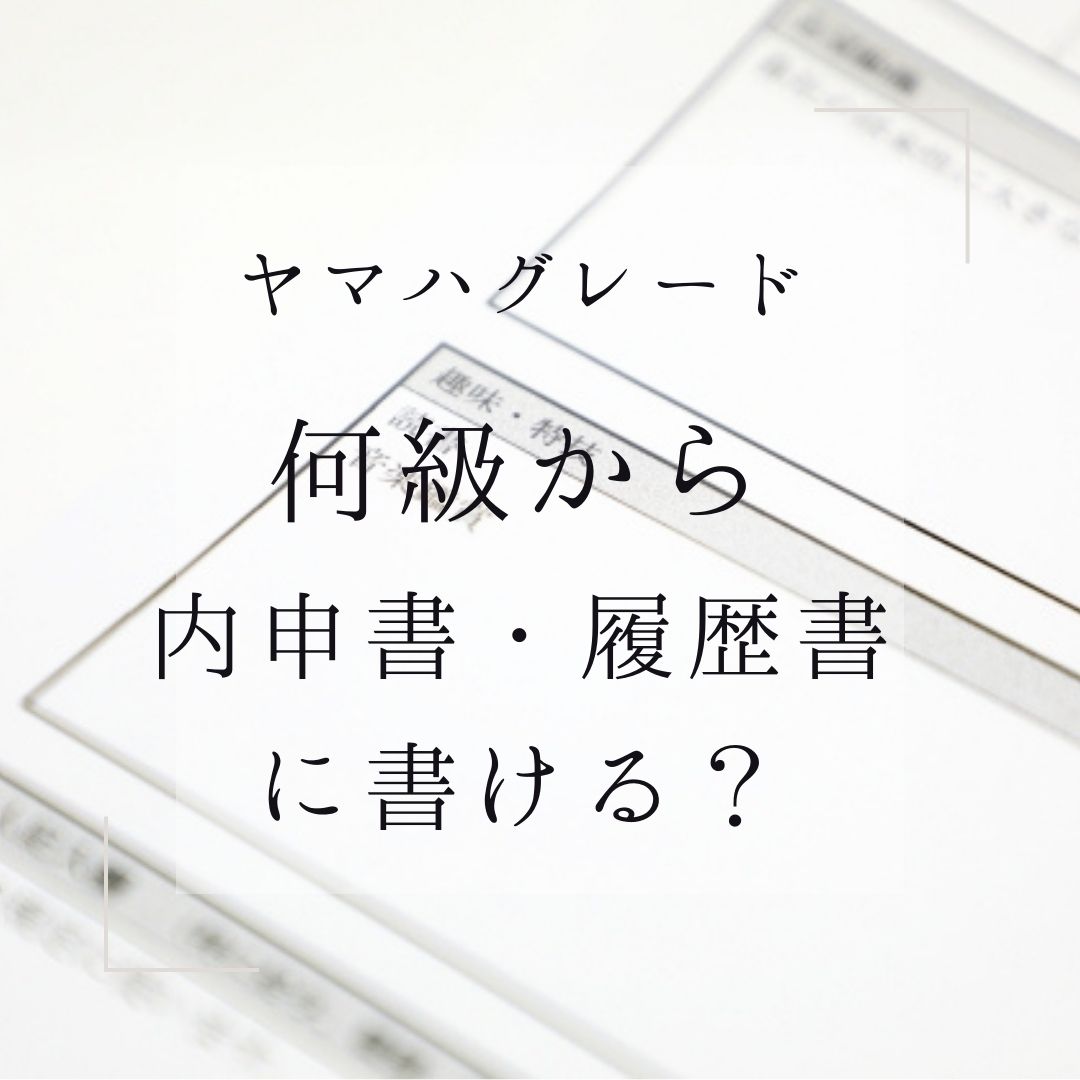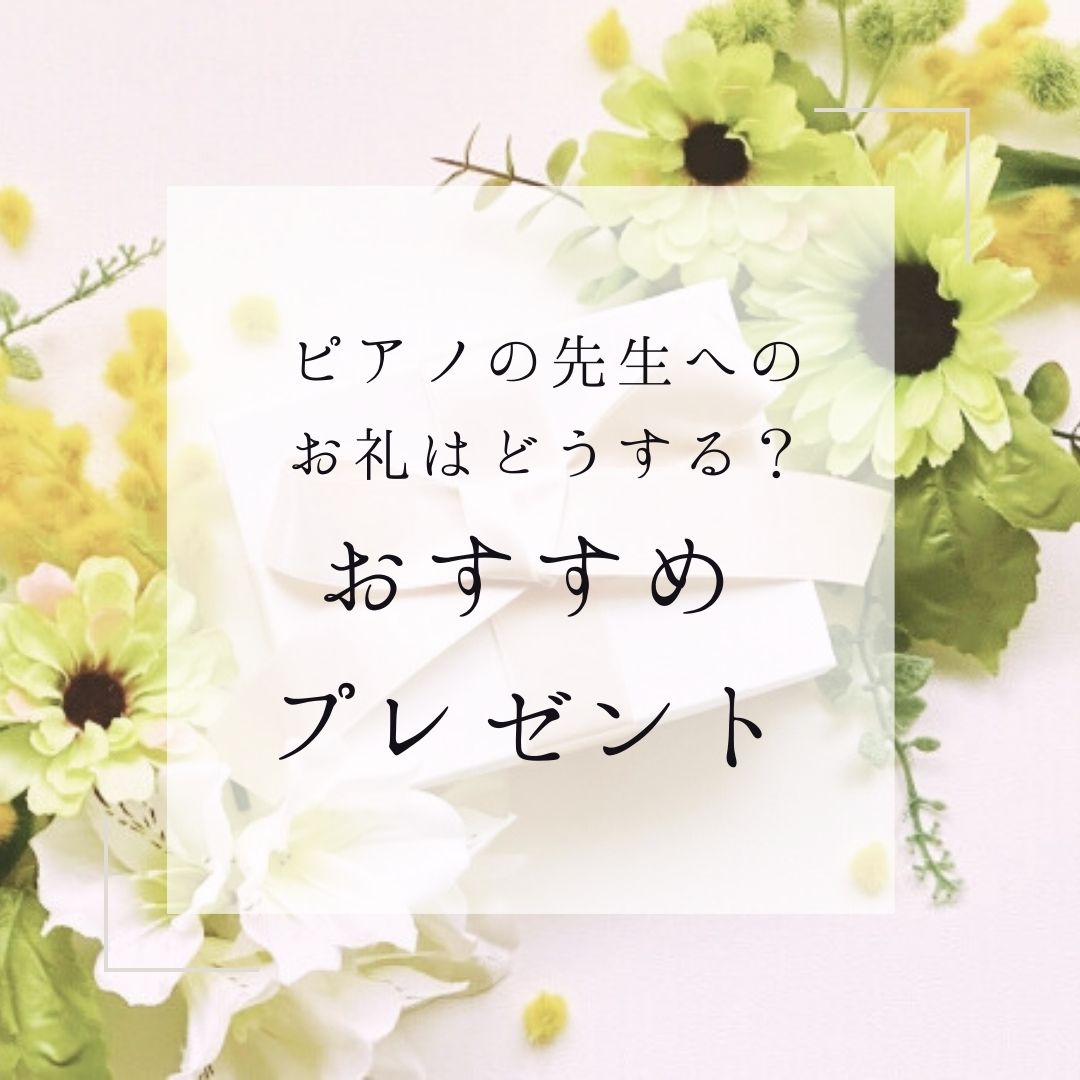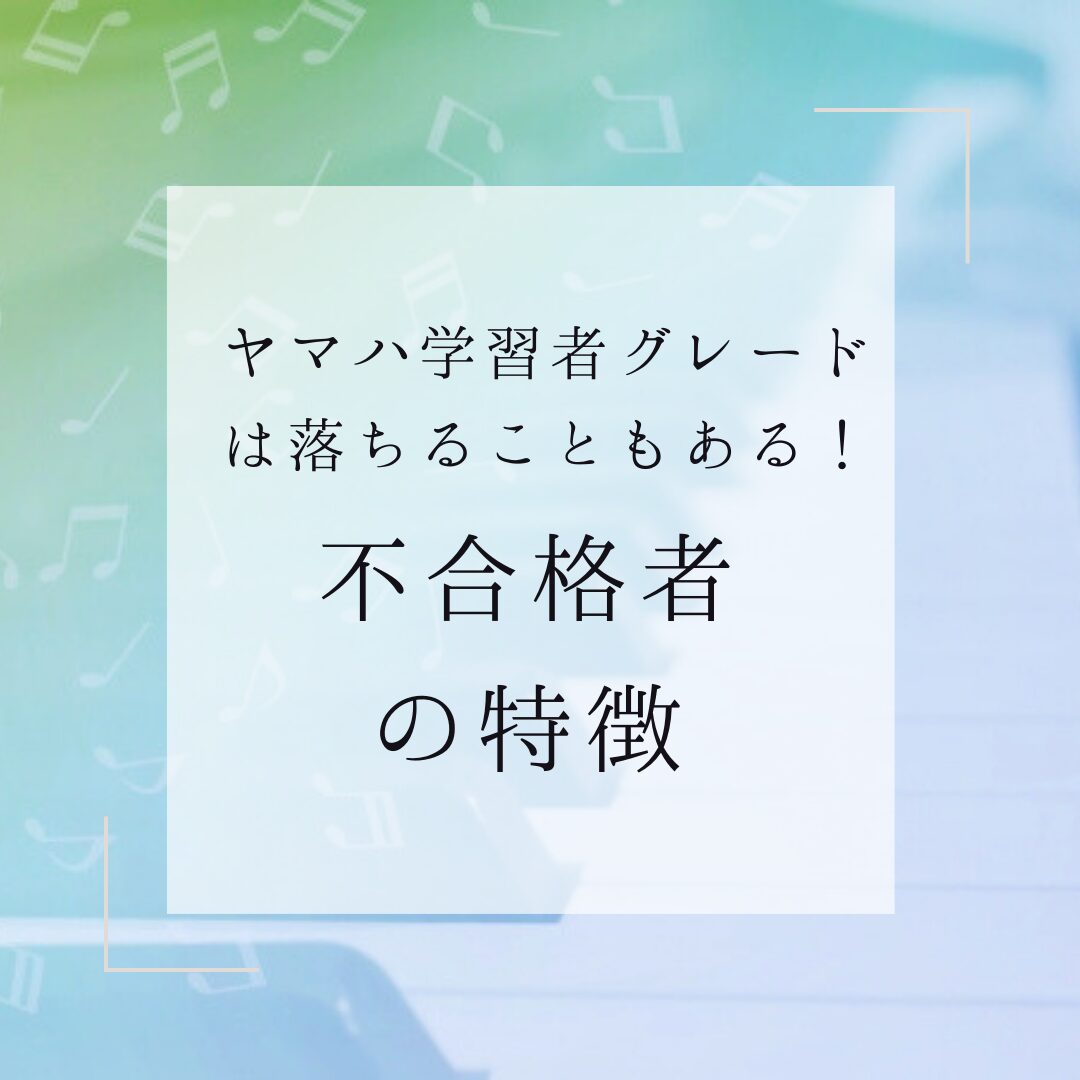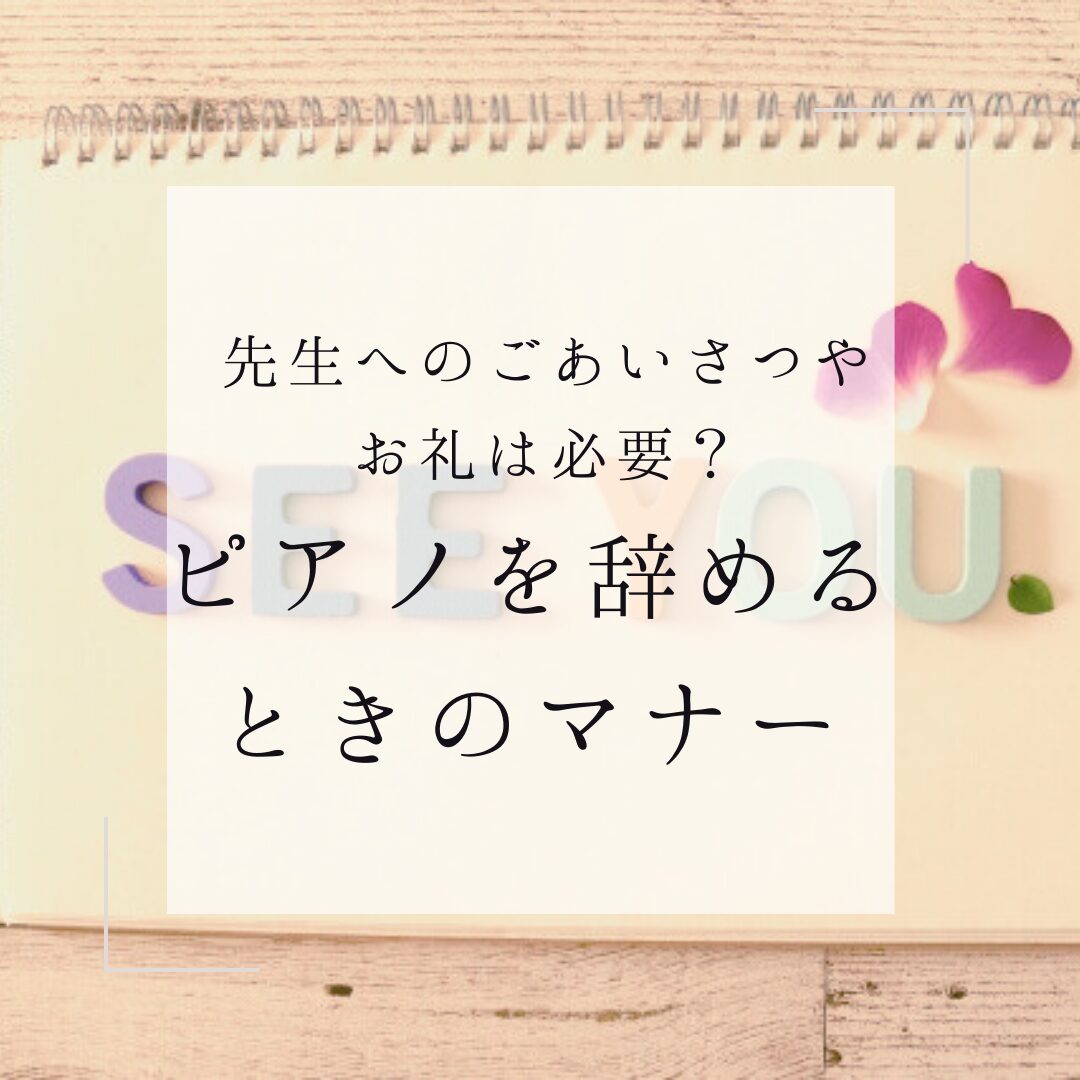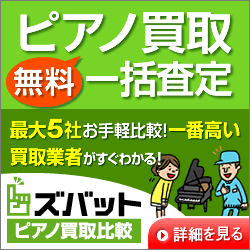クラシック音楽で本物の大砲を使った作曲家がいるのを知っていますか?

クラシックに大砲!?
あり得ないような組み合わせに、驚いてしまう方も多いでしょう。
そんな奇抜なことをしたのは、ロシアの作曲家・チャイコフスキーです!
この記事は
- なぜ大砲が使われたのか知りたい
- どんな曲で大砲が鳴るのか気になる
- 実際に大砲が鳴るところを聴いてみたい
という方におすすめです!
今回は、ロシアの作曲家ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーによって作曲された「序曲1812年」について、わかりやすく解説します。
どんな曲かな?
チャイコフスキー作曲「序曲1812年」ってどんな曲?


はじめに、「序曲1812年」を作った作曲家チャイコフスキーについてと、この曲が作られた背景をご紹介します。
作曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー


「序曲1812年」を作曲したのは、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーです。
P・I・チャイコフスキー(1840-1893)
ロシアの作曲家
チャイコフスキーというと、あなたはどんなことをイメージしますか?
- バレエ音楽をたくさん作った人
- メロディーが美しく感動的な作品が多い
- クラシックが苦手でも聴きやすい曲が多い
このようなイメージを持つ方が多いのではないでしょうか?
たしかにチャイコフスキーというと、
「白鳥の湖」
「くるみ割り人形」
「眠れる森の美女」
といった世界的有名なバレエ音楽を作曲したことで知らていますよね!
そんな優雅で美しい曲想のイメージがあるチャイコフスキーですが、曲中に大砲を使うという荒業も行っていたのです。
「序曲1812年」とは
大砲を楽器として使った「序曲1812年」について、ご紹介しましょう。
この曲は、チャイコフスキーが1880年に作曲したオーケストラ曲です。
海外では「1812 overture」と表記され
- 「大序曲 1812」
- 「祝典序曲 1812」
- 「荘厳序曲 1812」
などと呼ばれることもあります。
ナポレオン戦争でロシアの勝利を祝う曲


1812年はフランスの皇帝ナポレオンがロシアに遠征した年です。
すなわち、 ナポレオン軍がロシア帝国へ侵攻した年なのです。
このナポレオンの侵攻がどうなったのかというと、結果的にロシア帝国に負けてしまい、退却してきました。
この戦争は「祖国戦争」とも呼ばれています。
ロシア帝国に負けたことは、ヨーロッパ制覇を目指していたナポレオンにとって、とても悔しい出来事だったに違いありません。
そして、ナポレオンは流刑になってしまいます。
ロシアにとっては「1812年」が、ある意味記念の年になったわけですね。
この歴史的な出来事を音楽で表現したのが「序曲1812年」です。
この作品の特徴
ここまでご紹介してきたように、1812年にロシア帝国へ攻め込んできたナポレオン軍の様子が描かれているのが、「序曲1812年」です。
曲中には、
- フランスの国歌「ラ・マルセイエーズ」
- ロシア帝国国歌
が使われており、両国のカラーが現れています。
そのほか楽器編成もおもしろく、
- 合唱団が登場する(なしの編成も)
- 鐘がガンガン鳴る
- 大砲がドーンと放たれる
といった奇抜なことをする作品としても知られています。
愛情をこめた作品ではない?
チャイコフスキー自身はこの曲について
特に愛情をこめて作曲したわけではない
と言っている説もあります。
だから曲の最後の方で大砲を打つという無茶なことをしたのでしょうか?
曲の流れは後ほど解説♪
なぜオーケストラ作品に大砲が使われたのか


この曲の最大の特徴は、本物の大砲の音が楽器として使われていることです!
なぜ大砲を使ったの?
この曲はここまでご紹介してきたとおり、ロシアの勝利を祝う作品として作曲されました。
そこで、戦いの場面をリアルに表現するために、本物の大砲を使うことが考えられたといわれています。
特に、曲のクライマックスでは大砲が何発も鳴り響き、壮大な雰囲気を作り出しています。
本当に大砲を使ったの?
チャイコフスキーが演奏会で本当に大砲を使ったかどうかは、諸説あるようです。
しかし スコア上には
cannon(キャノン、つまり”大砲”)
と書かれていて、自衛隊や米軍などの演奏で実際に本物の大砲が使われたことがあります。
実際の映像がyoutubeにありました!
(前半と後半に分かれています)
こちらの動画は自衛隊の音楽隊による演奏のため、オーケストラ編成ではなく吹奏楽アレンジされたものと思われます。
2番目の動画では8分くらいのところで大砲が鳴っているので、聴いてみてください。
画面手前の聴衆は、大砲が鳴った瞬間耳を塞いでいますね!
さらに10分以降からクライマックスに向けて、大砲が何発も放たれています。
その前の自衛官の弾丸をセットする動きが揃っててすごいですよね!
「○小節目でこう動く!」とか決まっているのでしょうか…
大砲係は、出番まで微動だにしていないのもすばらしいです。
さすが軍隊!
コンサートホールではどうするの?
多くのコンサートホールでは、実際に本物の大砲は持ち込めませんし放てません!
「大砲」の指示が書かれている場面では、各楽団でさまざまな工夫をして演奏しています。
- 本物の大砲の音を録音したものをスピーカーで流す
- 複数のバスドラムで代用
- シンセサイザーの大砲の音で代用
大砲の音を代用する理由としては、次のようなことが挙げられます。
録音を使う理由
- 安全面:本物の大砲をコンサートホール内で放つのは現実的ではない
- 音量の調整:本物の大砲は非常に大きな音を出すため、演奏とバランスを取るのが難しい
- 設備の問題:コンサートホールに大砲を設置するのは無理!



そりゃそうだよね…
「序曲1812年」のストーリー


「序曲1812年」は、ナポレオンのロシア侵攻から、ロシア軍の勝利までの流れを音楽で描いています。
どのようなストーリーで構成されているのか、5つの場面をご紹介します。
第1場面:Largo
曲の始まりは、とても静かで落ち着いた雰囲気で「ロシアの祈り」ともいわれる場面です。
これは、ロシアの人々が戦争の前に祈りを捧げる場面を表しているそうです。
この場面では、ロシア正教会の聖歌「主よ、汝の民を救いたまえ」が使用されていますよ。
第2場面:Andante
弱いティンパニのトレモロ(ティンパニ ロール)から始まり、徐々に戦争の気配が漂ってくるところです。
この場面は「ロシア軍の行進」と呼ばれています。
第3場面:Allegro giusto
フランス国歌の「ラ・マルセイエーズ」が登場する場面で「ボロジノの戦い」と呼ばれることも。
戦争の場面では、音楽が激しくなり、両軍の戦いが繰り広げられます。
この曲の大砲初登場となる場面で、5発放たれます。
第4場面:Largo
第1場面の主題が再現され、ロシア軍が反撃する場面。
この場面では鐘が鳴らされますが、これはロシア正教会の鐘を表現しているとのことです。
第5場面:Allegro vivace
最後は、ロシアの勝利を祝う音楽が鳴り響きます。
ここでロシア正教会の鐘がゴンゴン鳴り、大砲もふたたび登場!
ロシア帝国国歌が高らかに奏でられ、感動的なフィナーレを迎えます。
演奏時間は17分くらい♪
ウクライナへの侵略で演奏中止になったことも
ロシア軍の勝利をイメージした「序曲1812年」は、2022年にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した際に、国内の楽団で「演奏するのは不謹慎」と判断され演奏を見送る動きがありました。
曲目がシベリウス作曲の交響詩「フィンランディア」に変更になった例もあります。
しかし、作品や作曲家に罪はないとの意見も多く、演奏中止の是非については議論が続いているようですね。



難しい問題だね
機会があれば本物を聴いてみたい!


チャイコフスキーは大砲をも楽器にしてしまいました。
- 「序曲1812年」は、ナポレオン戦争のロシア勝利を祝う曲
- 本物の大砲の音が楽器として使われている
- 曲の最後には、ロシア国歌と鐘の音が響く感動的なフィナーレ
当時、チャイコフスキーが実際に大砲を使って演奏をしていたかどうかは分かりませんでしたが、現在日本では自衛隊でない限り本物の大砲を使った演奏はできないのではないでしょうか。
このように、「序曲1812年」は歴史と音楽が一体となった壮大な作品です。
大砲の音が響くクラシック音楽はとても珍しいので、もし機会があれば、実際にこの目で見て聴いてみたいです!
名曲を存分に楽しむなら音楽配信サービスがおすすめ!
無料トライアル体験を活用すれば、気軽にクラシックの世界を楽しめます。
ぜひ下のボタンから無料体験をお申し込みください♪
\ショパンやドビュッシーの名演が豊富/
\楽天ポイントが使える&貯まる/
いろんな作品を聴いてみて♪
\チャイコフスキーはワルツ王/


\世のキテレツ曲シリーズ/


この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿