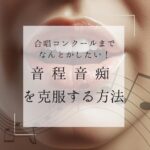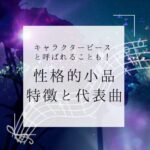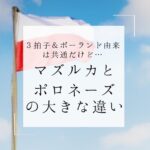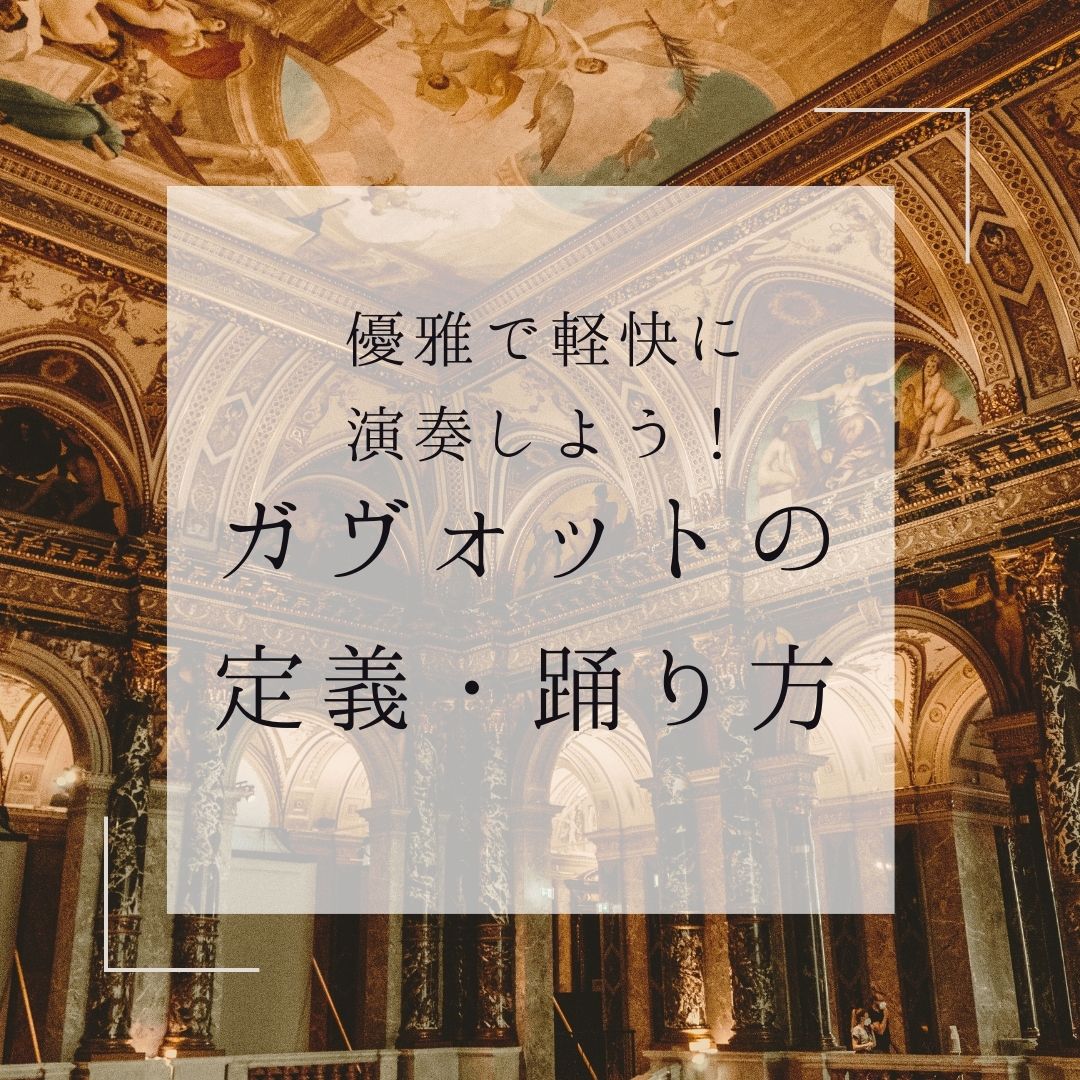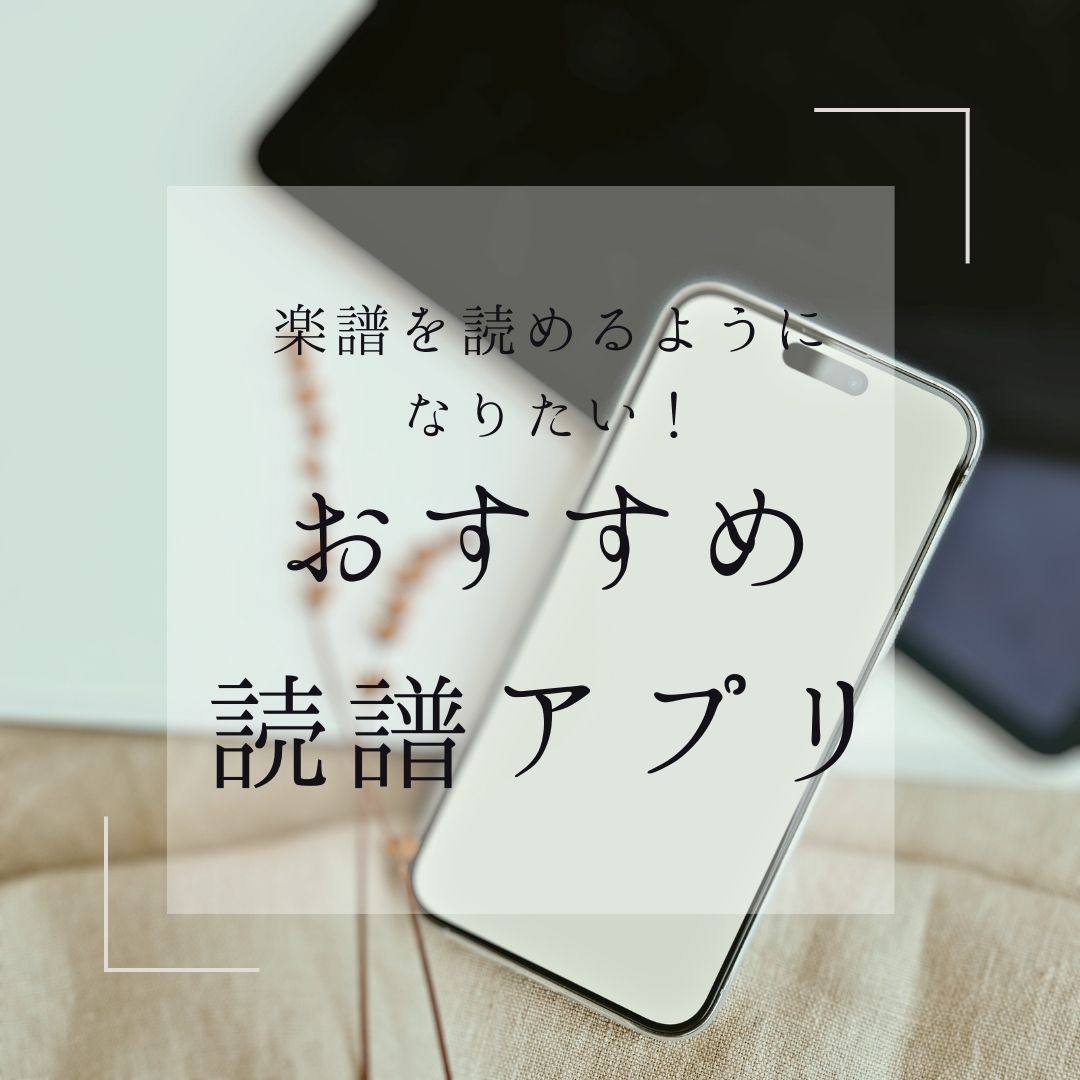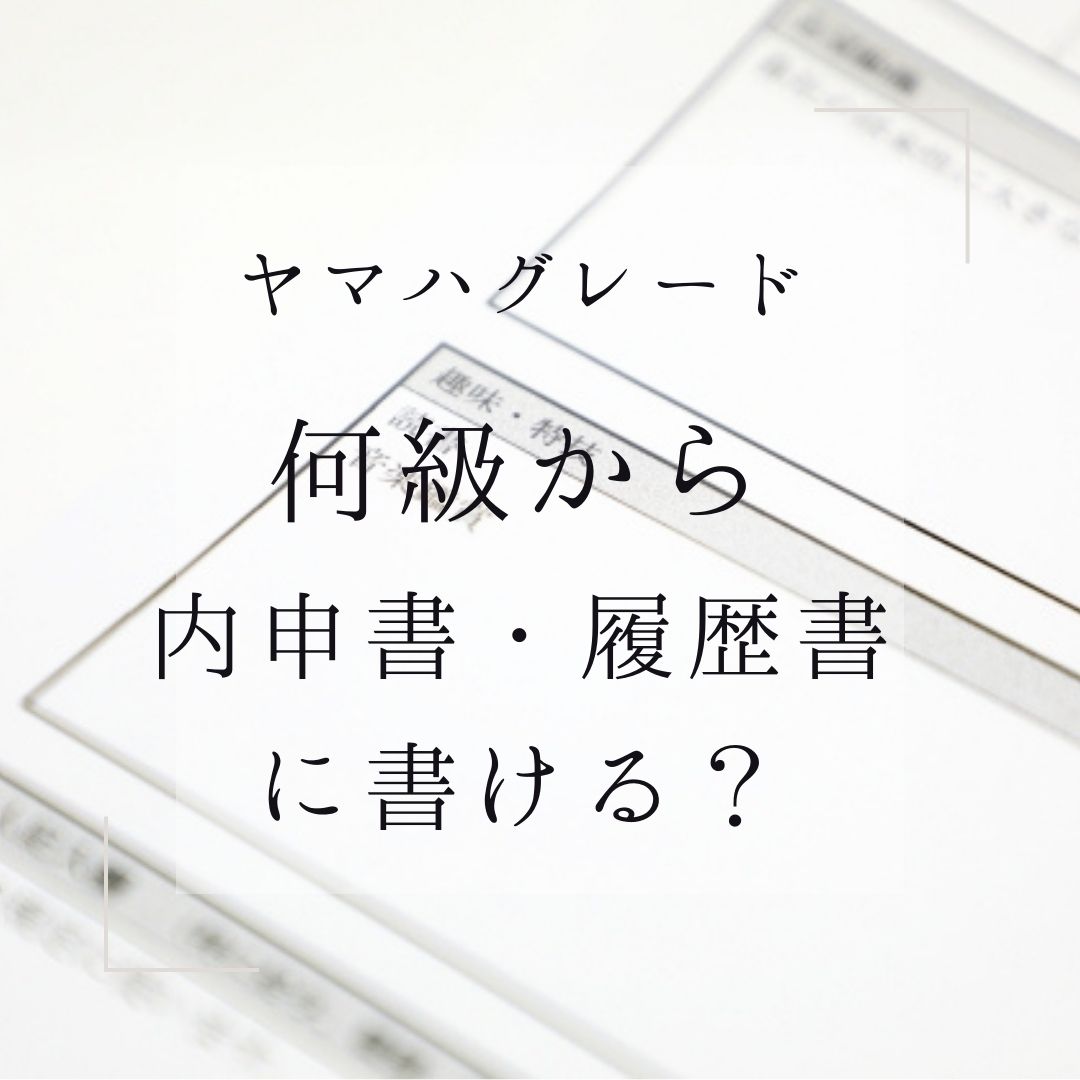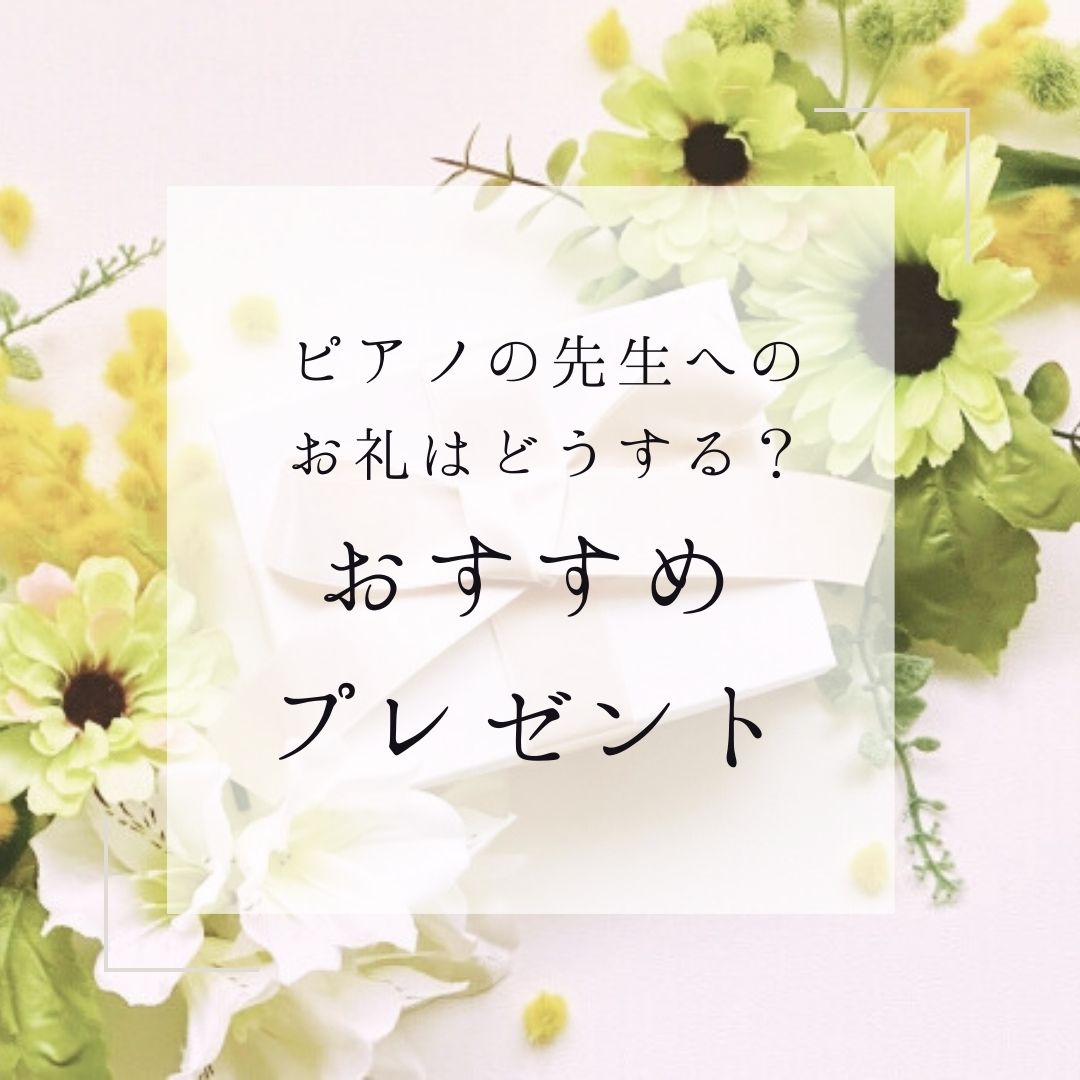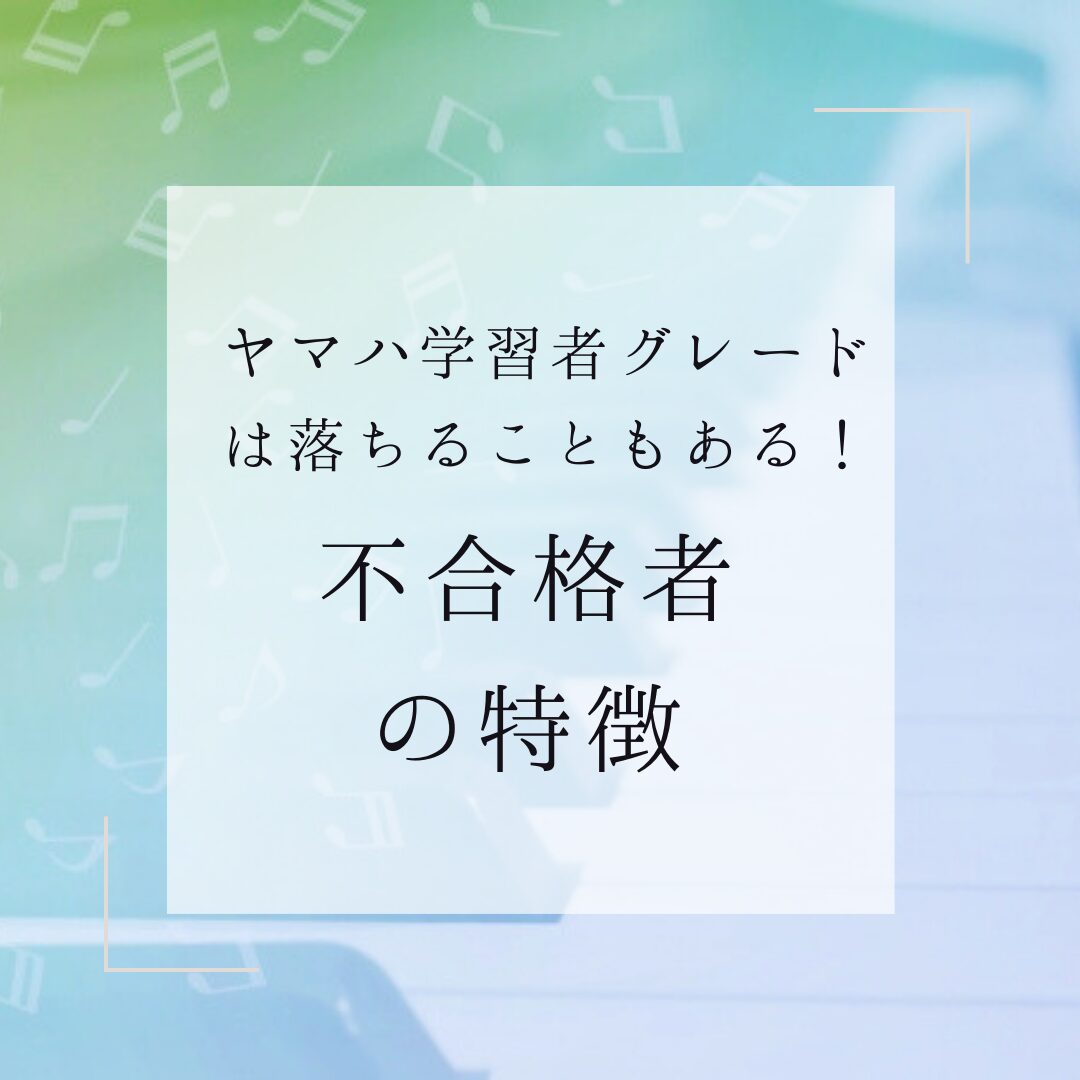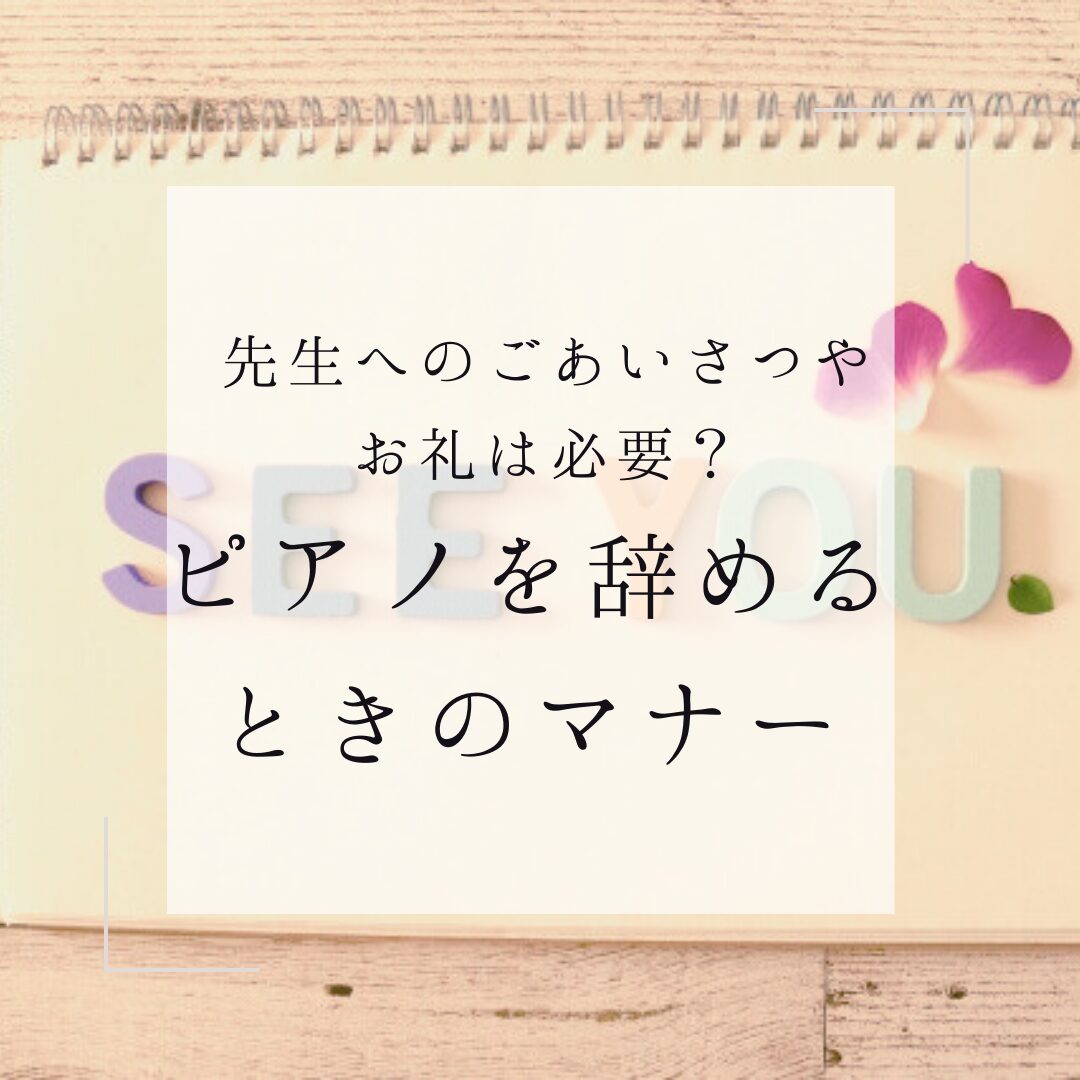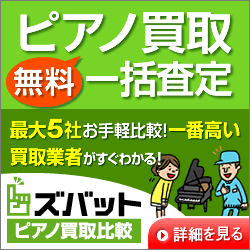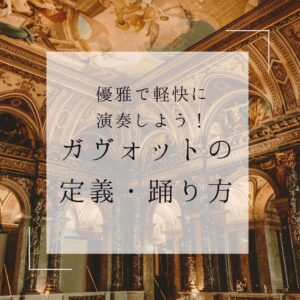ピアノ曲に限らず、器楽曲にはさまざまな舞曲があります。
舞曲の名前(種類)は、拍子やテンポの違い、発祥地、時代よって異なっているんですよ!

先生に今度から「ガヴォット」っていう曲をやろうか・・・
って言われたんだけど、ガヴォットってなんだろう?
ガヴォットも舞曲の一つだよ!
【ガボット】って表記されることもあるよ♪
今回は舞曲の一つでもある 「ガヴォット(ガボット)」 について取り上げます。
ガヴォットがどんな踊りかを知ったうえで演奏すれば、曲への理解や表現がさらに高まるはず!
ガヴォットとは宮廷舞曲(バロックダンス)の一つ


ガヴォットは宮廷舞曲の一つです。
宮廷舞曲・宮廷舞踏は、バロックダンスとも呼ばれます。
まずは有名なガヴォットの作品や言葉の意味などをみていきましょう!
絶対知ってる!有名なガヴォット
ガヴォットというと、どの作曲家のガヴォットをイメージしますか?
有名なところでいうと
ゴセックのガヴォット
グルリットのガヴォット(イ短調)
などがありますね。
どんな曲かちょっと聴いてみよう♫
どうでしょう?
この2つのガヴォットは、きっとどこかで一度は耳にしたことがあるはずです。
ちなみに、「アマリリス」もガヴォットだよ!



え?あの「ラリラーリ ラリラー」って曲?
学校で歌ったことがあるよ!


ガヴォットの定義
ガヴォットがどのようなスタイルかをまとめると、次のようになります。
- 4分の4拍子、または2分の2拍子の舞曲(偶数拍子)
- 曲の始まりがアウフタクト(弱起)か小節の途中から始まっているもの
このように定義されていますが、ほとんどのガヴォットは4分音符2拍分を上拍として曲が始まっている場合が多いようです。
最初の小節の2拍前から始まっている曲が多いよ。
小節の真ん中から始まって、小節の真ん中で終わる感じだね!
ガヴォットのテンポや雰囲気の感じ方
ガヴォットのテンポは、中庸とされています。
中庸というのは「中くらい」という意味だよ!
moderato(モデラート)も「中くらいの速さで」っていう意味だね。



速くもなく、遅くもなく・・・ってことね。
結構ざっくりしてるね。
曲の雰囲気は宮廷舞曲でもあるので、優雅なイメージ、そしてスタッカートが記されている楽譜も多く、軽やかに演奏される印象です。
ガヴォットのつづり
ガヴォットは、フランス語で「gavotte」と表記します。
日本の楽譜では「ガヴォット」または「ガボット」となっていますね。
どちらで発音しても大丈夫ですよ!
ガヴォットが誕生するまで


続いて、ガヴォットが誕生するまでの歴史・時代の流れをみていきましょう!
ガヴォットはフランス発祥
先ほど、ガヴォットのつづりについてご紹介しましたね。
フランス語でつづられていることから、ガヴォットはフランスで発祥した舞曲であることが分かります。
もともとはプロヴァンス地方の農民の踊りだった
ガヴォットには、元になった踊りがあるといわれています。
それは、14世紀フランスのプロヴァンス地方で農民が踊っていた音楽です。
この農民は山岳民族のガヴォ族と呼ばれている人たちで、ガヴォットの名前の由来はこの「ガヴォ(gavot)」ともされています。
- gav は「山の小さな流れ」という意味
- gavot は「山に住む民族」という意味
17世紀には人気の舞曲に


農民たちの間で親しまれていたガヴォットの踊りは、その後フランスで16世紀末~18世紀に宮廷舞踏の一つとして取り入れられるようになりました。
17世紀ごろには、人気の舞曲として流行したといわれています。
宮廷舞踏で人気になったガヴォットは、フランスだけでなくドイツにも広まっていきました。
オペラやバレエ音楽にも使われるようになり、特に鍵盤では組曲に必ずといっていいほど取り入れられる舞曲の一つになっています。
その後、18世紀末のフランス革命を境に、ガヴォットは流行らなくなってしまいました。
ガヴォットを踊っている様子を見てみよう
ガヴォットが宮廷舞曲として取り入れられていた時代、どんな感じで踊っていたか動画をみてみましょう。
ゴセックのガヴォット
バイオリンとピアノ伴奏に合わせて踊っている様子です。
「軽やかなステップ」で踊っているのが分かりますね!
マルティーニのガヴォット
蹴り上げて跳ねるステップが特徴になってますね!
優雅な雰囲気ですが上下の運動が多いので、結構体力を使いそうです。
バッハのガヴォット
この動画では、そのほかの宮廷舞踊でもあるメヌエットやブレーについても解説しています。
ガヴォットの様子は2:40くらいから、ほんの少しですが見ることができますよ。
ガヴォットのイメージをしっかり持って演奏しよう!
ガヴォットの定義や歴史をご紹介しましたが、どんな踊りなのか分かりましたか?
- 偶数拍子(4分の4拍子、または2分の2拍子)の舞曲
- アウフタクトまた小節の途中から曲が始まる
- フランス発祥の宮廷舞踏(バロックダンス)の一つ
- 中くらいの速さで優雅で軽快なステップが特徴
ガヴォットがそのほかの舞曲と大きく異なるのが、 アウフタクトまた小節の途中から曲が始まる という特徴があること。
演奏する時になんとなくアウフタクトの頭を1拍目と感じて演奏してしまう人も多いのですが、 どこがアウフタクトで・どこが1拍目になるのかを意識してみると、よりガヴォットらしさが出る と思います。
楽譜をよく見て、強拍となるのがどこなのか意識してみよう!
バロックダンスについては浜中庸子先生の解説が参考になるので、ぜひ読んでみて♫
名曲を存分に楽しむなら音楽配信サービスがおすすめ!
無料トライアル体験を活用すれば、気軽にクラシックの世界を楽しめます。
ぜひ下のボタンから無料体験をお申し込みください♪
\ショパンやドビュッシーの名演が豊富/
\楽天ポイントが使える&貯まる/
いろんな作品を聴いてみて♪


この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿