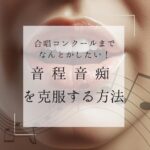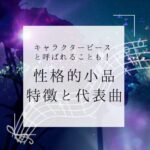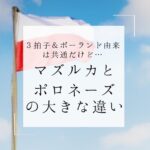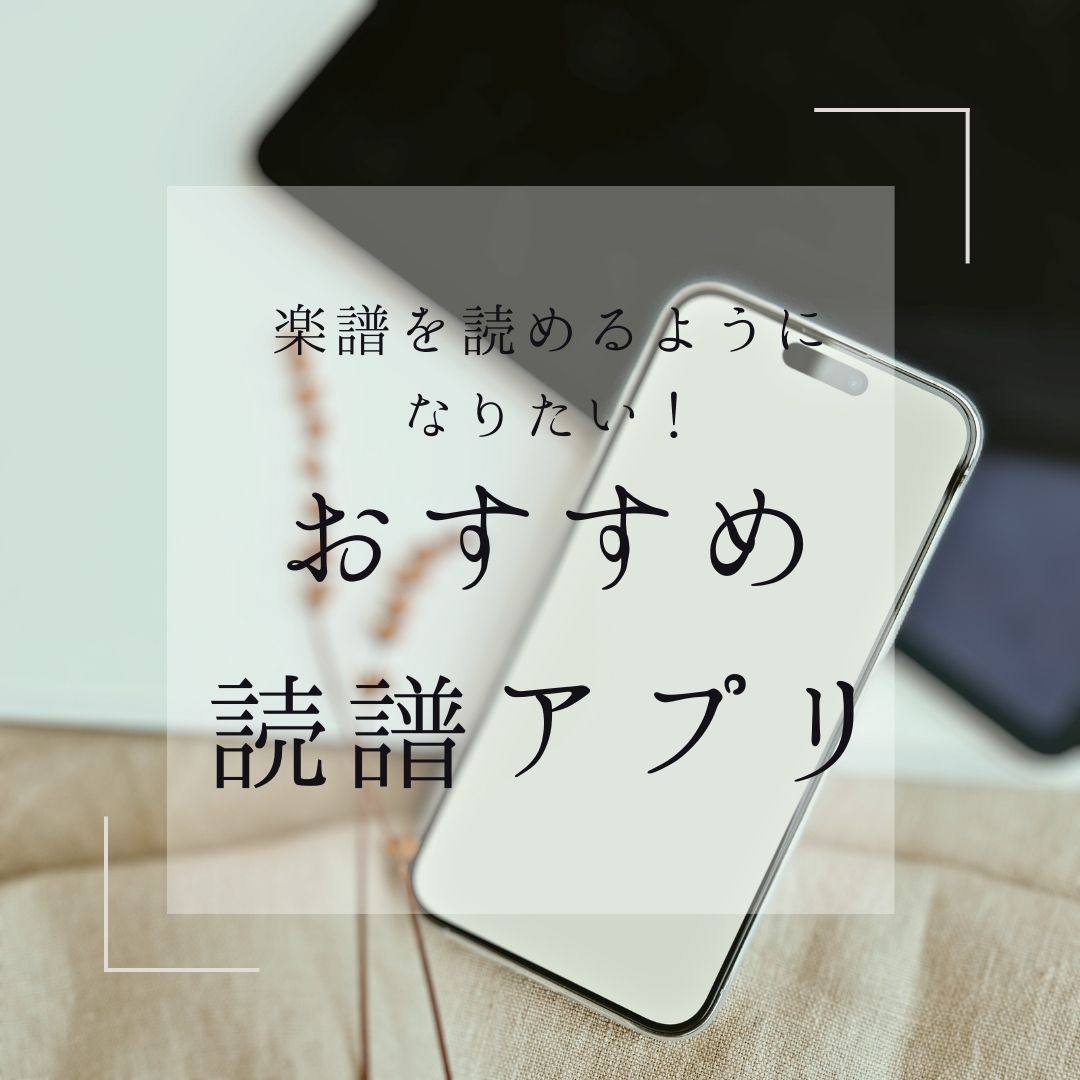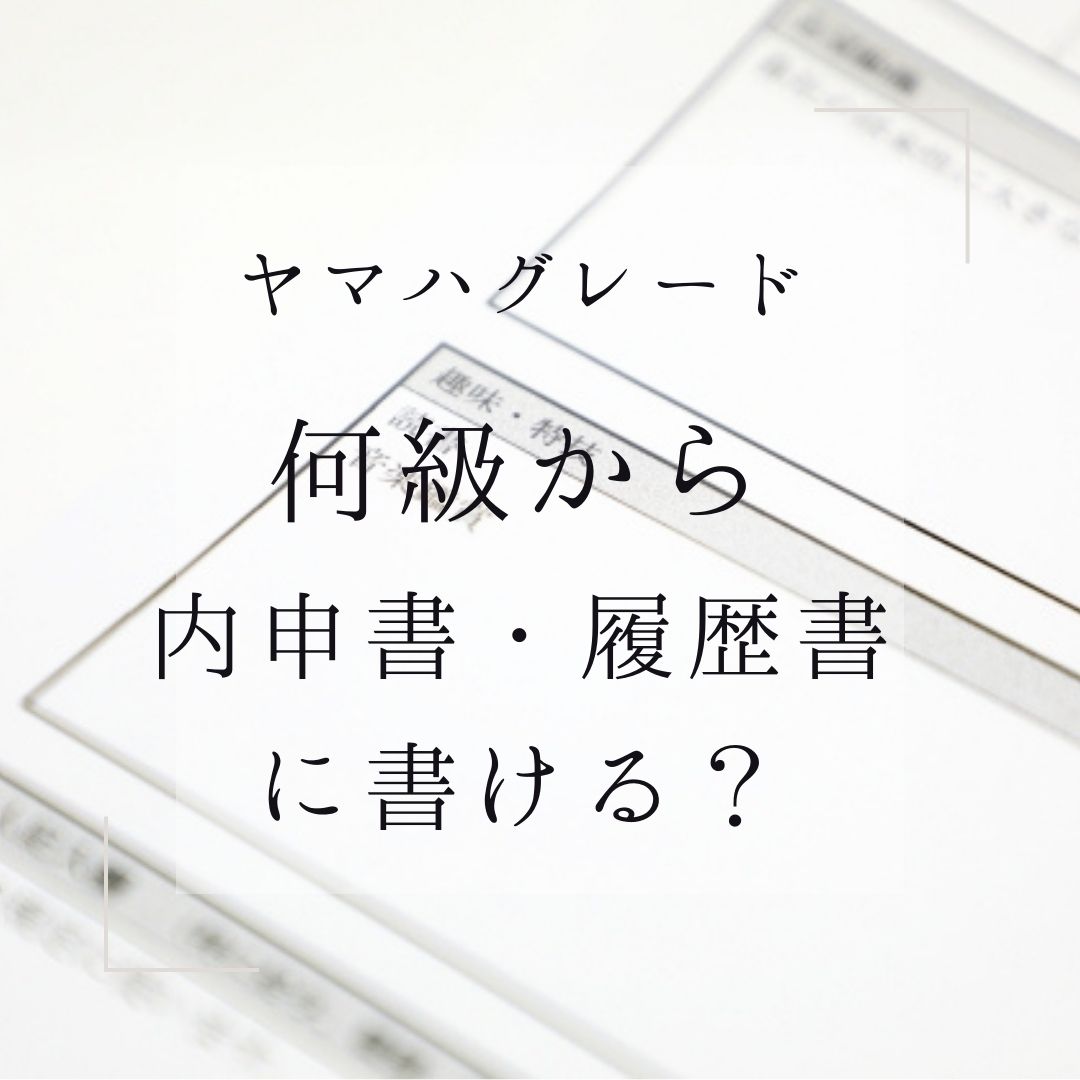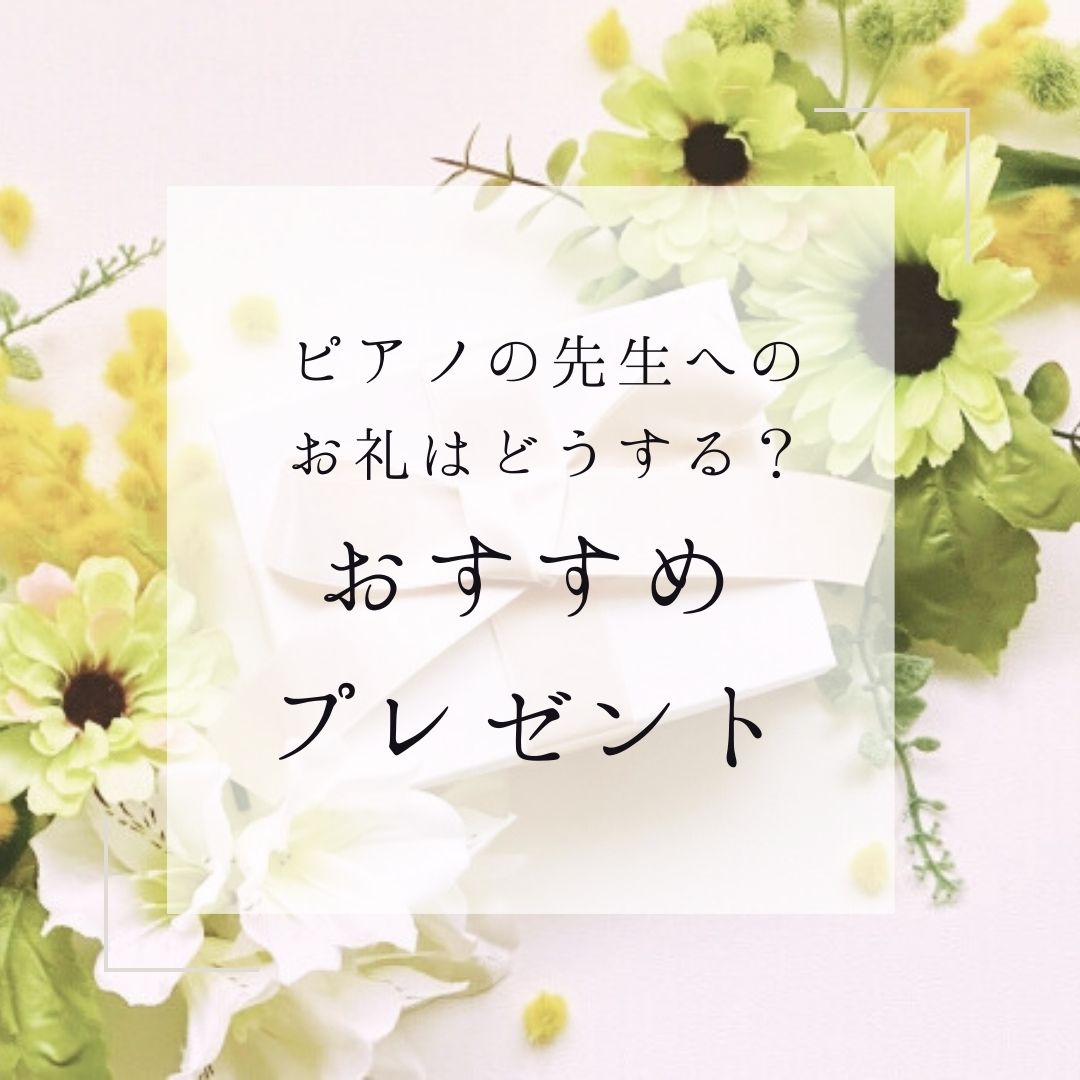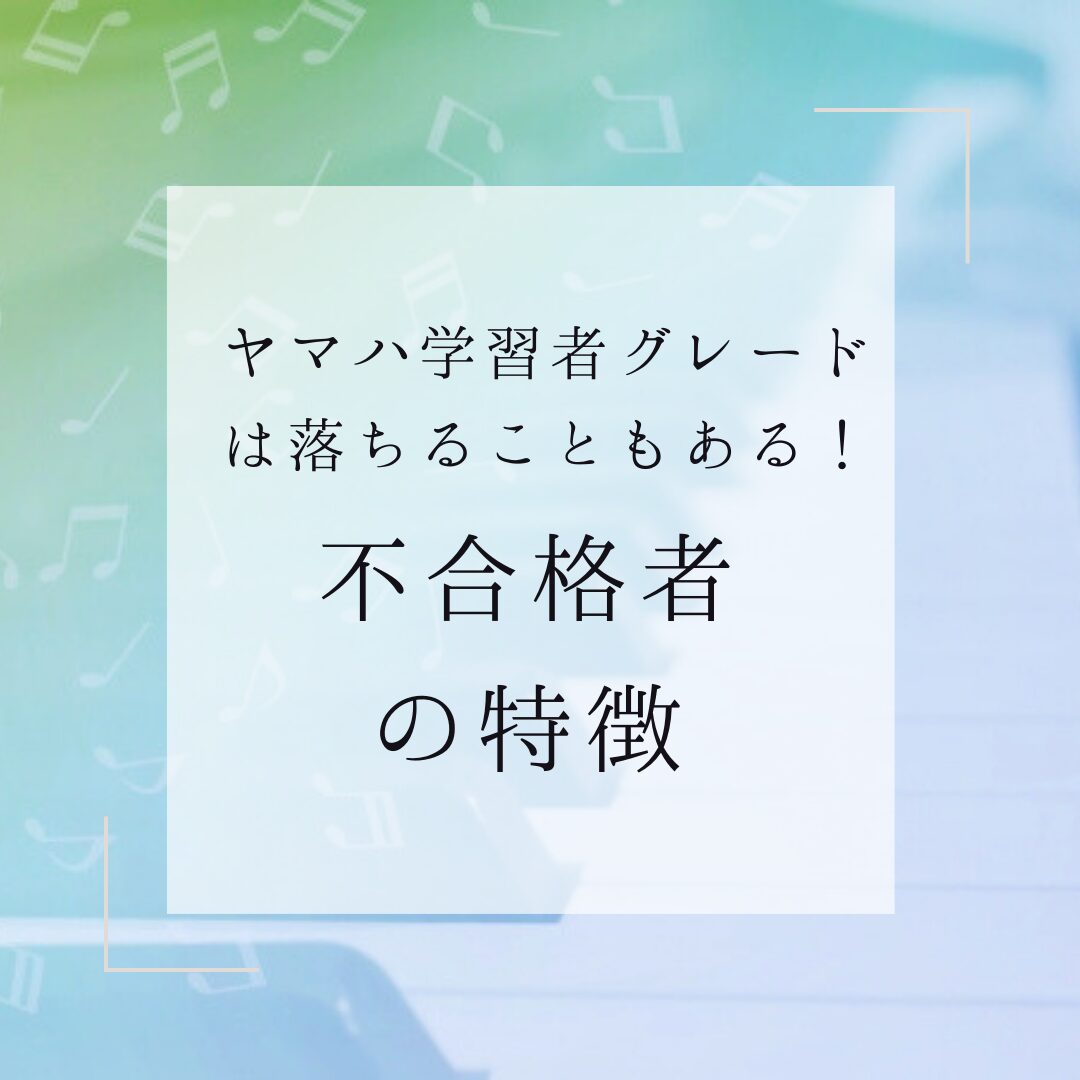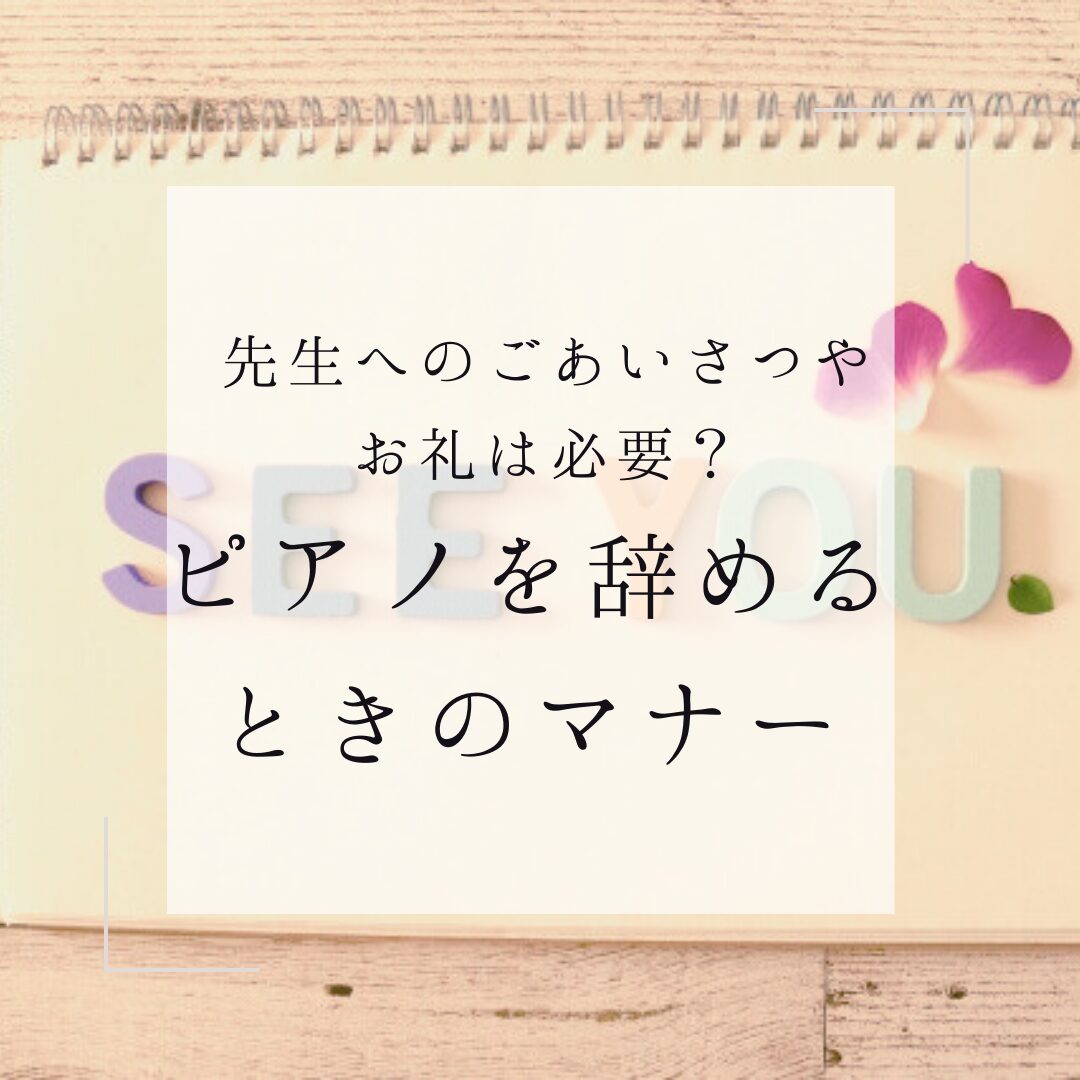合唱コンクールで指揮者に立候補した方、みんなから推薦された方、もしくはジャンケンで負けて指揮者になってしまった方・・・など指揮者になる経緯はさまざま。
この記事は
- 未経験で指揮者に選ばれた人
- 素人でも上手に指揮する方法を知りたい人
- 指揮のポイント・コツを知りたい人
- 指揮者賞をとりたい人
- クラス合唱で一体感を出したい指揮者
におすすめです!
今回は、合唱コンクールで指揮者になった方に知っておいてほしいことや指揮のコツなどについてご紹介します。
指揮者に選ばれたけど、どうすればいいの?

秋は、中学校や高校では校内合唱コンクールが開催される時期ですね。
合唱コンクールで、もっとも大事な役割なのが指揮者です!
指揮者に選ばれた方は、こんなことを思っているはず。
指揮者の色々な胸の内
- 指揮の経験なんてないよ!
- どう振ったらいいかさっぱり分からない
- 学級委員っていうだけで指揮者にされちゃった
- ジャンケンで負けて指揮者になっちゃった
- やるからには指揮者賞を取りたい!
実際、指揮をすることが未経験な人が合唱の指揮をすることは、とても大変なことです。
合唱コンクール・指揮者が押さえておきたい5つのコツ

合唱の指揮は難しそうに感じるかもしれません。
しかし、これからご紹介するポイントをおさえれば「それなりに」上手に指揮をしているようにみえるので安心してくださいね。
ここからは、中学校の合唱コンクールを想定してお話ししたいと思います。
①基本の拍子はきちんと振れるようにする

指揮者にとって大切なのは、 拍を正確に振ること です。
基本の4拍子や3拍子の指揮をきちんと振ることができるかや、同じ速さで振り続けることができるかをメトロノームなどを使って練習してみましょう。
胸の前に左手を手のひらを上に向けておきます。
右手で指揮をしますが、左手の手の平に「1.2.3.4」と拍を打つときに右手をぶつけるようにすると、同じ点で拍を打てるようになります。
4拍子の右手の動き
- 1拍目で左手にぶつけて上に振り上げる
- 2拍目で左手にぶつけて左に振り上げる
- 3拍目で左手にぶつけて右に振り上げる
- 4拍目で左手にぶつけて上に振り上げる
こんな感じです。
慣れてきたら左手のサポートがなくても同じ点で拍をとれるように練習してみましょう。
こちらの動画も参考になります♬
まずは4拍子・3拍子・2拍子の振り方をマスターしましょう!
打点がみんなにわかるようにしよう!
②楽譜の指示を細かくチェックする


楽譜に書いてある指示をしっかり理解しておく ことも大切です。
テンポや曲想、強弱など、鉛筆やマーカーでチェックを入れておきます。
意味も調べて書いておきましょうね!
楽語辞典もありますが、今はスマホやPCで検索すればすぐに調べることができますし、音楽の先生に聞いてみるのもいいでしょう。
指示記号は日本語で書いていないことも多く見落とされがちですが、実はすごく大事なことが書いてあることも・・・。
rit.(リタルダンド=だんだんおそく)や accel.(アッチェレランド=だんだんはやく)などの速度記号を無視してずっとおなじテンポで歌い続けると、緩急がない平坦な音楽になってしまいますよね。
指揮者は楽譜に書いてあることをきちんと理解して、クラスのみんなに伝える という重要な役割を担っているのです。
\ 楽譜が読めない指揮者必見! /


③各声部(パート)の入りをチェックする
楽譜をチェックするときは、 各声部(ソプラノ・アルト・テノール・バス)がどのタイミングで入ってくるのかも把握しておくといいですよ!
合唱曲はみんなで一斉に歌う場面もありますが、「バス→テノール→アルト→ソプラノ」など入るタイミングをずらして積み上げていくような場面もありますね。
そのときに、ただ拍子を振るだけでなく、体を次に入ってくるパートに向けて左手ですくう様な指示を出してあげると、歌う方は入りやすくなります。
ちょっと上級なテクニックですが、余裕が出てきたら、ぜひ各声部が入るタイミングを出してあげましょう。
これができると、とっても上手な指揮にみえますよ!
④強弱は指揮の大きさで表現する


強弱を表現したい場合は、指揮を振る手の幅(指揮を振るサイズ)で調整します。
P(ピアノ=弱く)だったら小さく指揮をし、f(フォルテ=強く)だったら大きく指揮をします。
また、できるなら左手も使ってみましょう。
pのときは声を抑えるような指示をし、fのときは左手も大きく振ります。
⑤伴奏者とのコミュニケーションをしっかりとる
伴奏者とコミュニケーションをとることも大切です。
伴奏者に選ばれる人は、それなりにピアノを長く習っていて、音楽的な知識もある人だと思います。
言ってしまえば、中学生くらいですと「指揮者<伴奏者」こんな関係ではないでしょうか。
ですから、伴奏者のいうことは常に取り入れつつ、テンポの揺らし方、強弱の付け方などを丁寧に打ち合わせしましょう。
もし時間が許されるのであれば、 伴奏者と二人だけで合わせる練習もたくさんしておきましょう。
あとは、伴奏者に録音・録画などをしてもらい、それを流しながら自宅で一人で練習する方法もおすすめです。
\ 絶対音感は指揮にも活かされる /


こんな指揮はNG!気を付けたいポイント
指揮をする腕はなるべく上半身でキープするとかっこよく見えます。
例えば4拍子を振るときに、3拍目で腕が伸びきって下半身まで開いてしまうと、だらしなく見えるので気を付けてくださいね!
ラジオ体第一の腕を開きながら屈伸する動作のようにならないよう気を付けましょう。
下の動画の00:28の辺りのような感じになってしまう指揮はNGです
曲の理解を深めながら指揮の練習をしよう!


中学校の合唱コンクール、指揮者のコツは分かりましたか?
みんなの前に立って指揮をするのは、とても緊張すると思います。
しかしクラスの歌声が1つにまとまるかどうかは、指揮者にかかっています。
しっかり曲の理解を深めながら、練習を積み重ねて本番に臨みましょう!
\めざせ優秀賞/
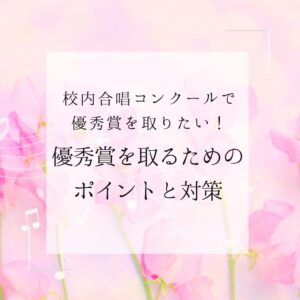
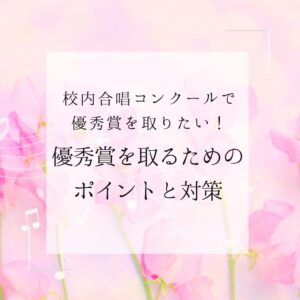
\ 伴奏者とのコミュニケーションも大事 /
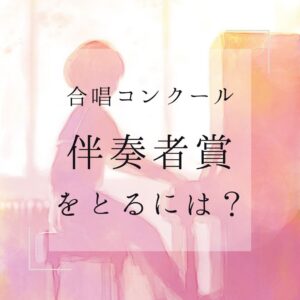
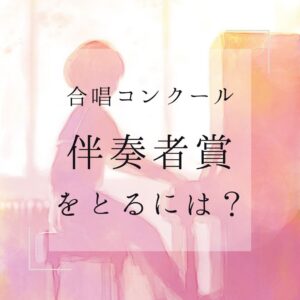
\ 音痴の人に教えてあげて /
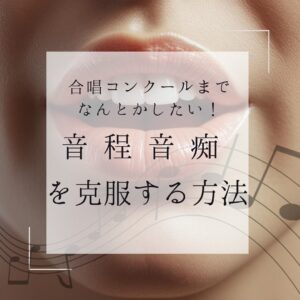
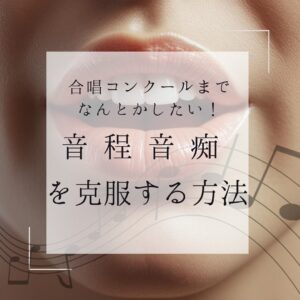
この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿