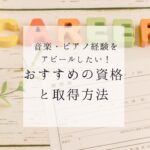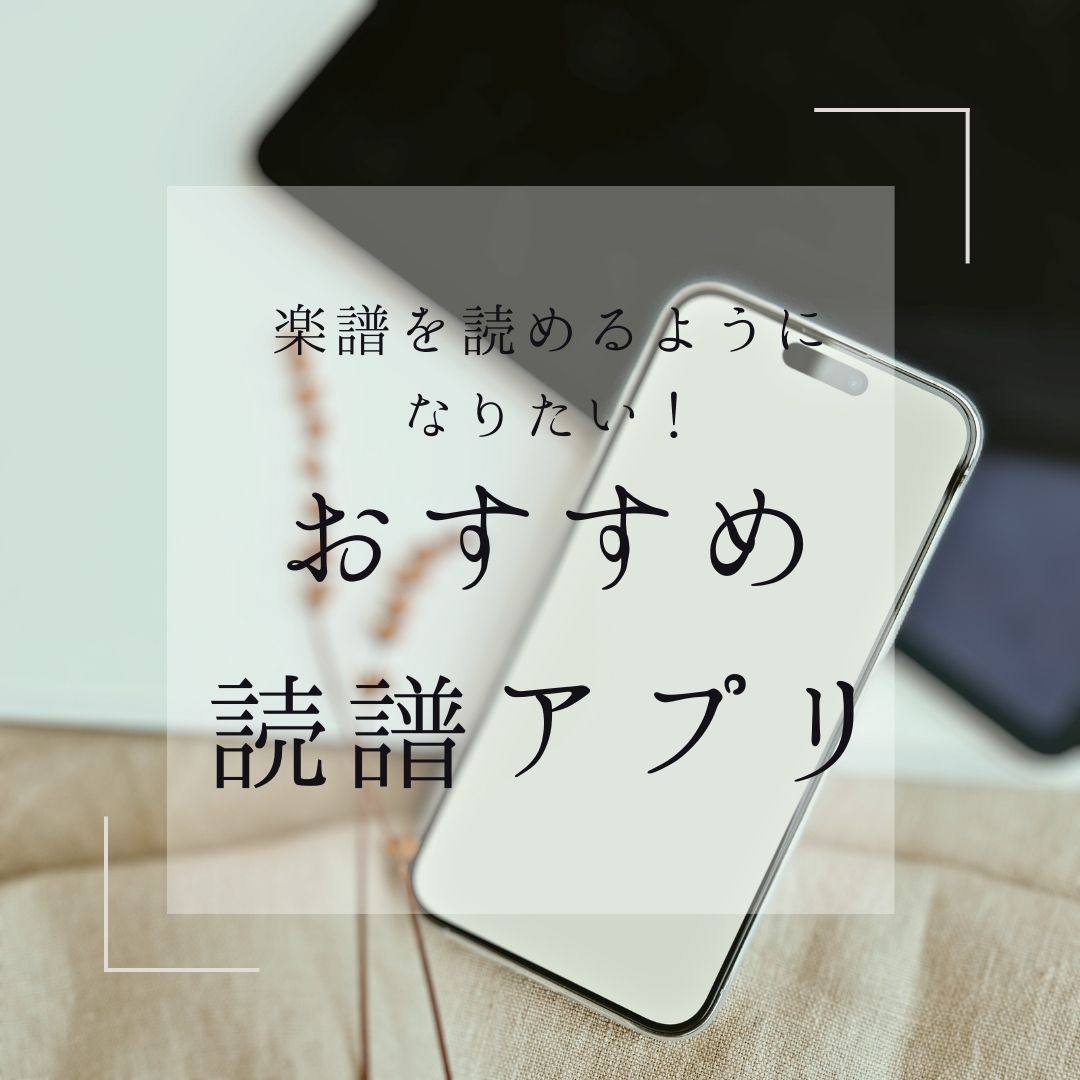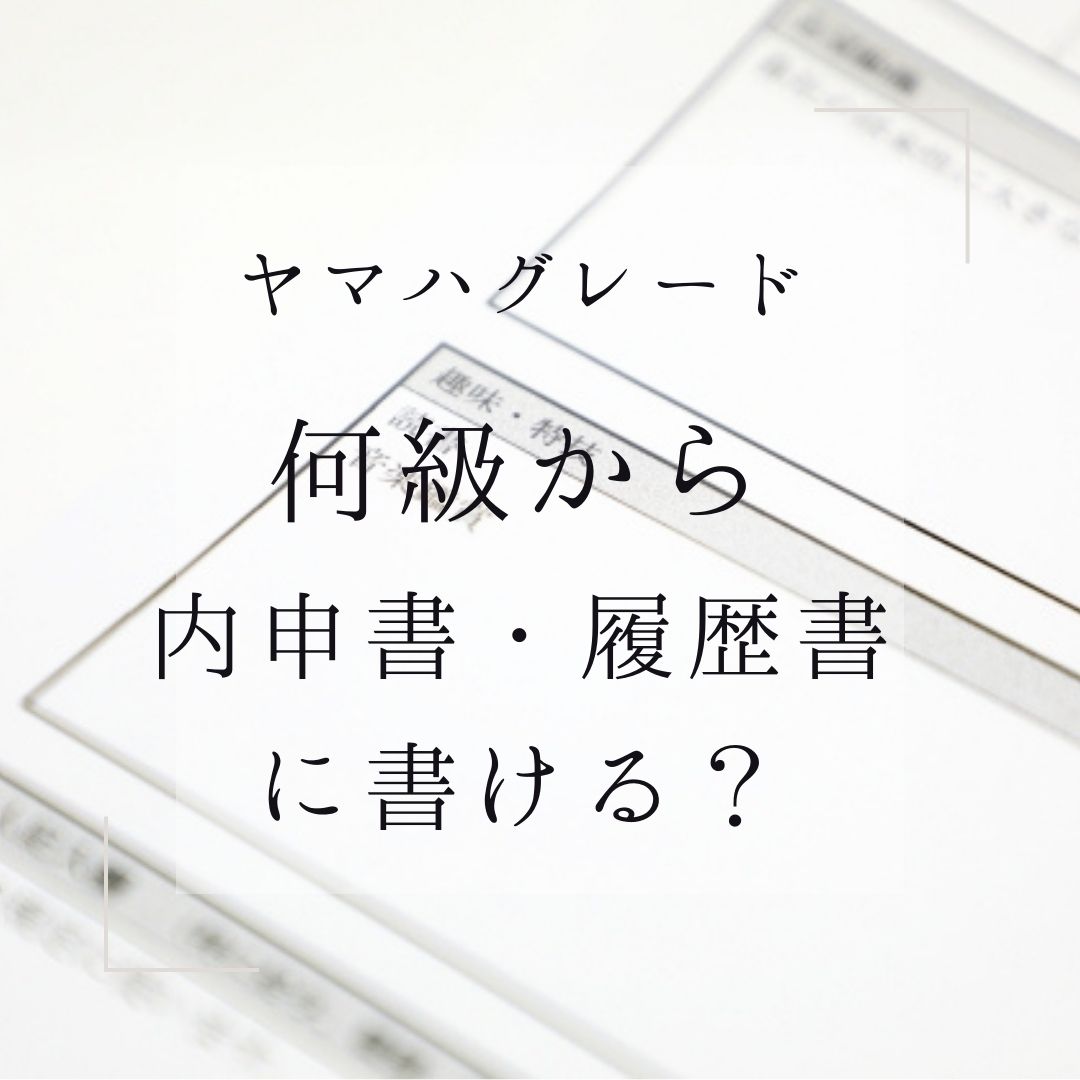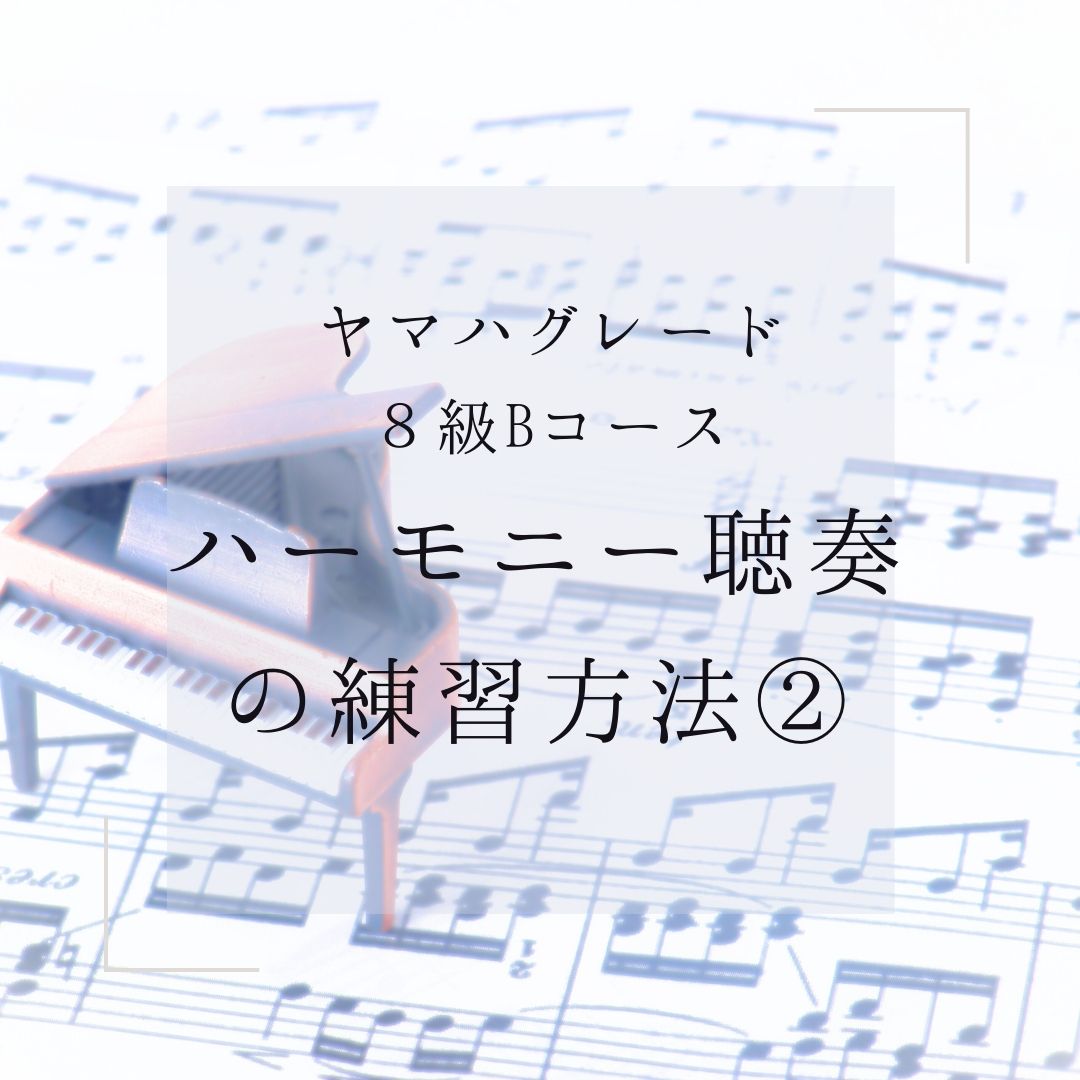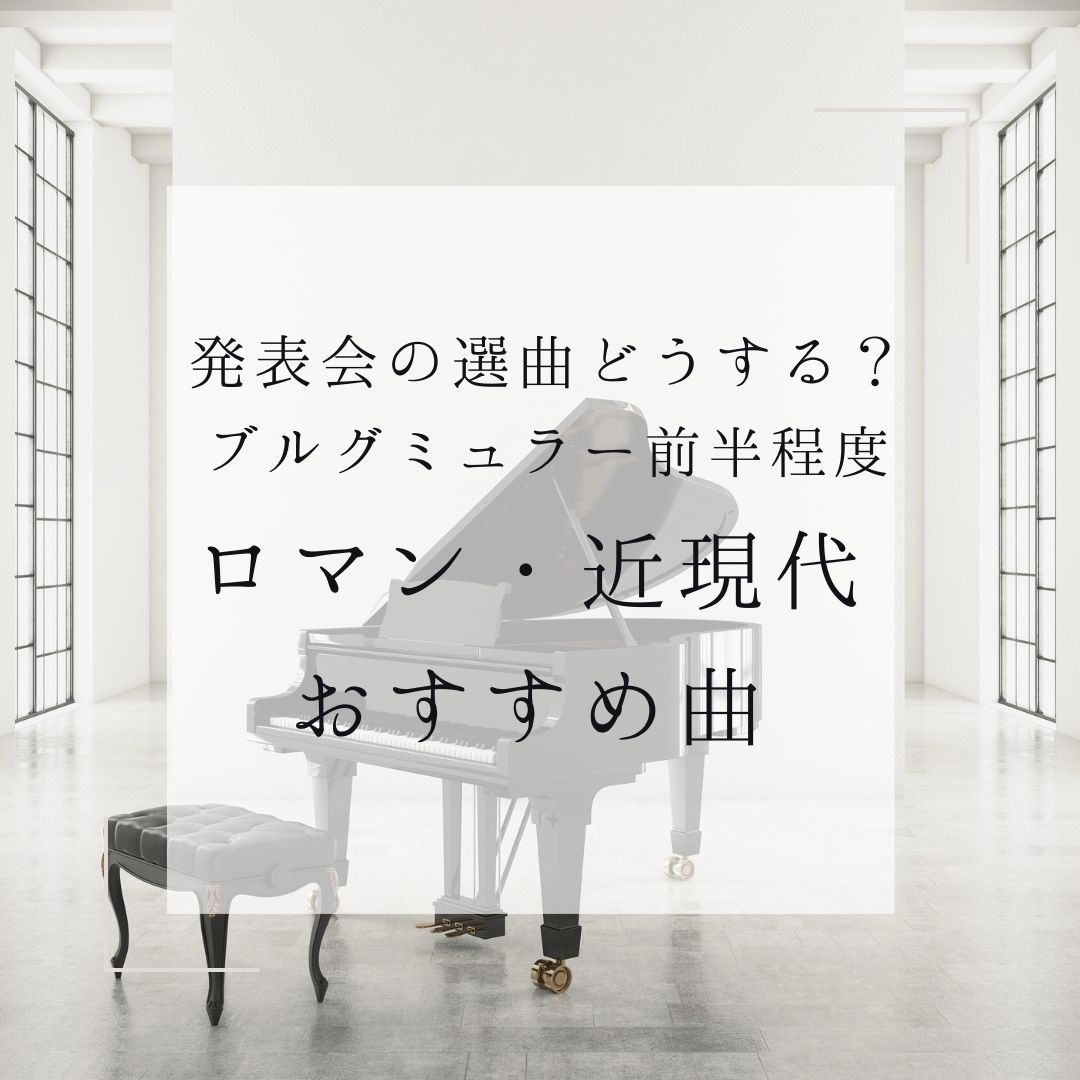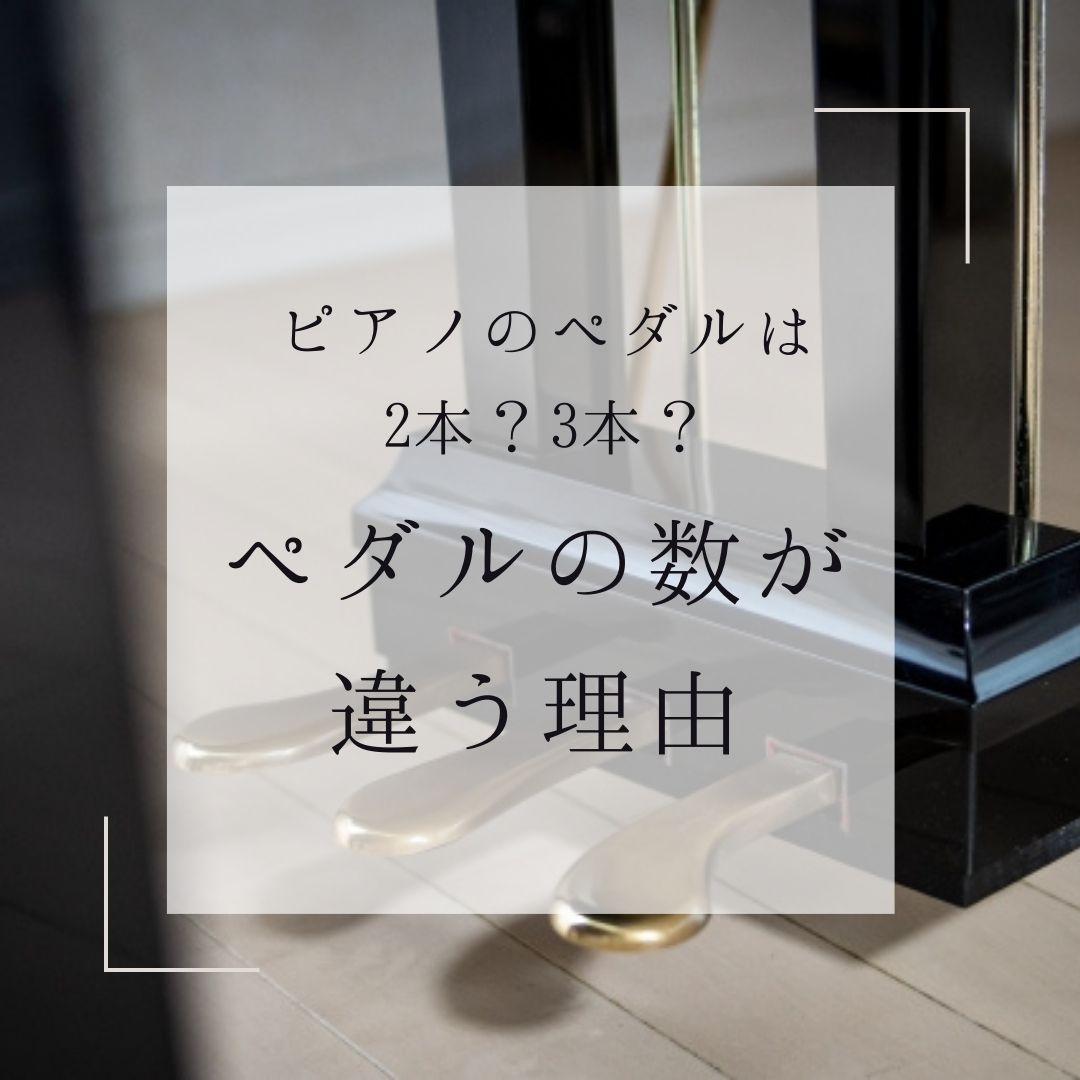2017年2月2日に、ネットニュースで見た驚きの記事。 JASRACが楽器の演奏などを教えている大手音楽教室などから著作権料を徴収することを検討しているとのこと。
これは音楽を教えている私にも重大ニュースです。今回はこのニュースについて考えてみたいと思います。
音楽教室での演奏にも著作権料がかかる?

経緯を簡単に・・・
JASRACは日本音楽著作権協会のことですね。楽曲の著作権を管理している団体です。 お金をとっての発表会やコンサートで演奏した楽曲については、著作権料を払わなければなりません。
また、楽譜にもJASRACのマークが入っているので、 楽譜を購入することで自然と著作権料を払っていることになっています。
今回問題になっているのは、音楽を教えている教室で先生や生徒が著作物を演奏することに「演奏権」が発生するかどうかです。 JASRACはこれを「公衆」に向けて演奏していると判断しているようで、演奏権としての著作権料を早ければ2018年1月から徴収しようとしています。
実際に徴収対象といわれているのが、大手の音楽教室。つまりヤマハ音楽教室やカワイ音楽教室などです。個人で行っている教室は対象になっていないようですが、将来的にどうなるか分かりません。
このニュースに対して現在業界は猛反発しているようです。
実際にレッスンで演奏権を徴収されたらどうなる?
演奏権を徴収できるのは、著作権が切れていない作品に限られます。作曲家が亡くなって50年経つと著作権は切れるので、アレンジしたり自由に演奏したりできます。(なかにはバーンスタインのように勝手にアレンジしたりすることを禁止している作曲家もいるので注意が必要です。)
レッスンで扱う曲は大体がクラシックで、著作権が切れている作品が多いです。しかし、 ヤマハやカワイなどで使っている教材に映画音楽やポップスなど著作権が発生する作品が含まれているものがあるとして、年間のレッスン料の2.5%を支払うことをJASRACが検討しているというのです。
仮にこのことが実際に起こってしまうと、どうなるでしょう?
音楽教室側の損害が増えてしまうので、月謝が上がるでしょう。 月謝が上がると、音楽を学びたくても学べない子どもたちが出てきてしまいます。
ただでさえ、少子化と習い事の多様化からピアノをはじめとする音楽を習う子どもは少なくなっているというのに・・・。
才能があっても、開花させられないまま埋もれていってしまうかもしれません。 日本の音楽は衰退の一途を辿るでしょう。
なぜ音楽だけが標的になるのか
ふと考えました。「なんで音楽だけが標的になっているのか」ということです。
今回の件を体操に例えてみましょう。
体操選手が発表する新技があったとします。大体その技には作った選手の名前が付けられますね。「タナカ」とか「モリスエ」とか。
この技を、体操教室で先生が生徒に教えるとします。このとき「著作権料」や「演技料」は発生するでしょうか?
書道にも例えてみます。
子どもが習字を習っているとして、有名な書道家さんが書いた作品を先生から教えてもらいながら真似して書いたとしましょう。このとき「著作権料」は発生するでしょうか?
これは料理教室(レシピは著作権があるのか)やダンススクール(振り付けに著作権はあるのか)など、いろいろと考えることができます。
なぜ音楽を教えるときにまで著作権料を支払わなければいけないのでしょうか?
まとめ
今回のニュースは、音楽を教える人にとって衝撃的なニュースだったと思います。私自身、職を失ってしまうのではないか・・・という危機感を覚えました。
たしかに、作曲者とその作品には敬意を払わなければいけません。でも、今回のJASRACの考えに正直私は納得できません。
ヤマハ音楽振興会では今回の件に関して「教室での演奏に著作権料は発生しない」と判断しているようなので、ぜひ業界全体でなんとか阻止してほしいと思います。
この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿
 資格2024-04-18ピアノ経験や音楽好きをアピールできる!おすすめの資格
資格2024-04-18ピアノ経験や音楽好きをアピールできる!おすすめの資格 ピアノ2024-04-171の指(親指)で黒鍵を弾いてはいけない理由と指導法~導入期のピアノ~
ピアノ2024-04-171の指(親指)で黒鍵を弾いてはいけない理由と指導法~導入期のピアノ~ ヤマハグレード2024-04-09ヤマハ学習者グレードを取る意味《メリット・デメリット》も紹介
ヤマハグレード2024-04-09ヤマハ学習者グレードを取る意味《メリット・デメリット》も紹介 ヤマハグレード2024-04-02【ヤマハグレード10~8級Bコース】メロディー聴奏のコツと練習方法
ヤマハグレード2024-04-02【ヤマハグレード10~8級Bコース】メロディー聴奏のコツと練習方法