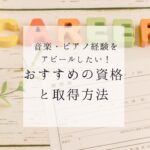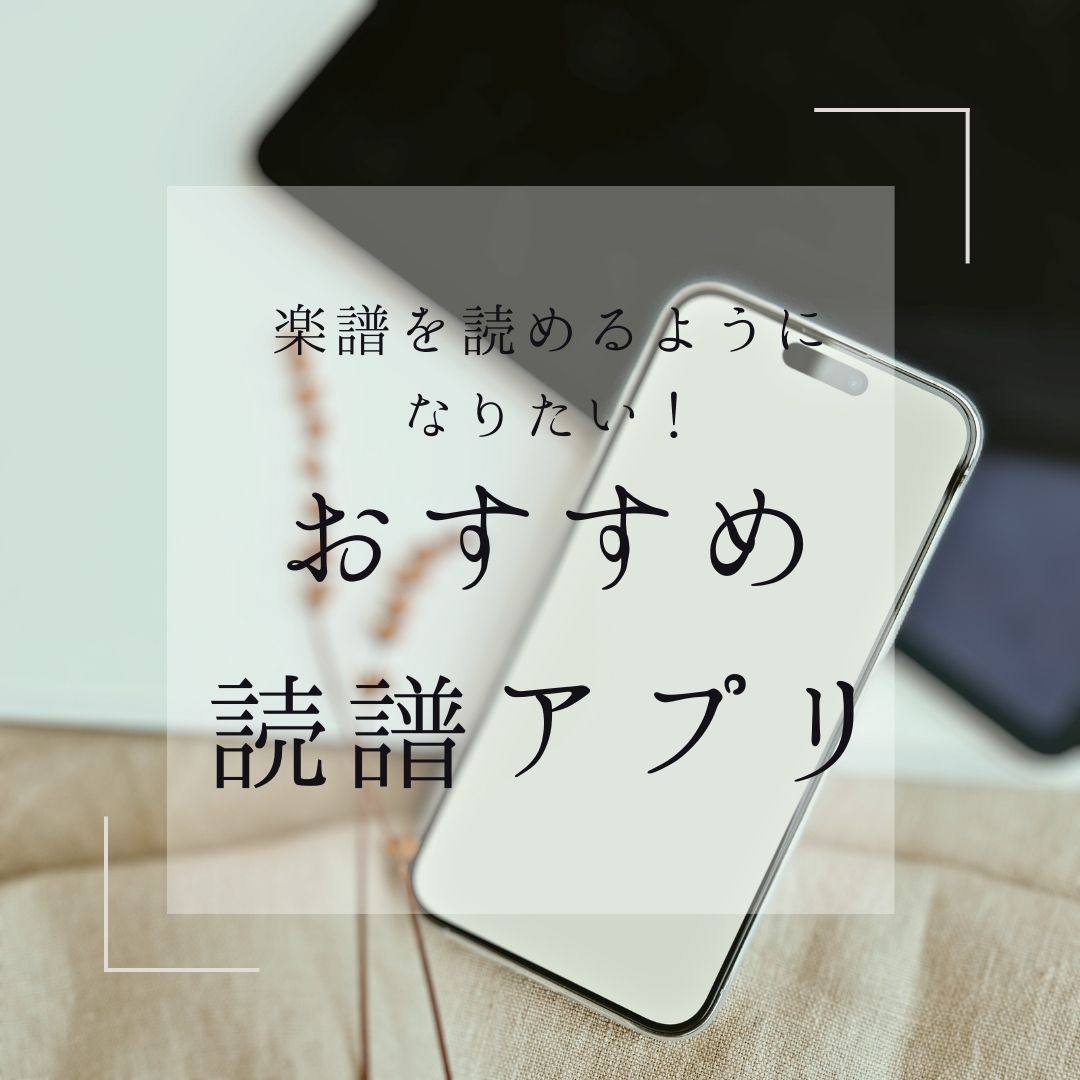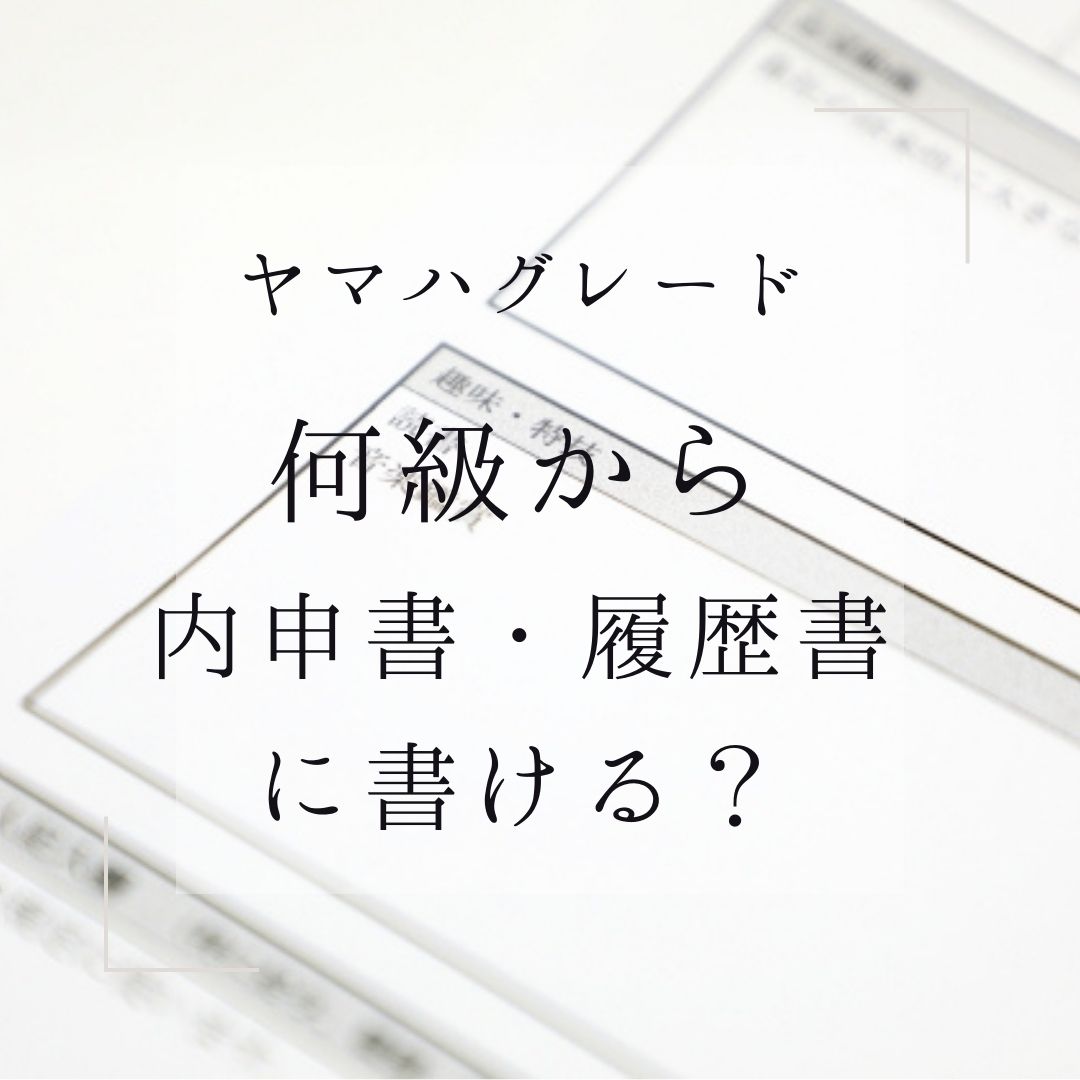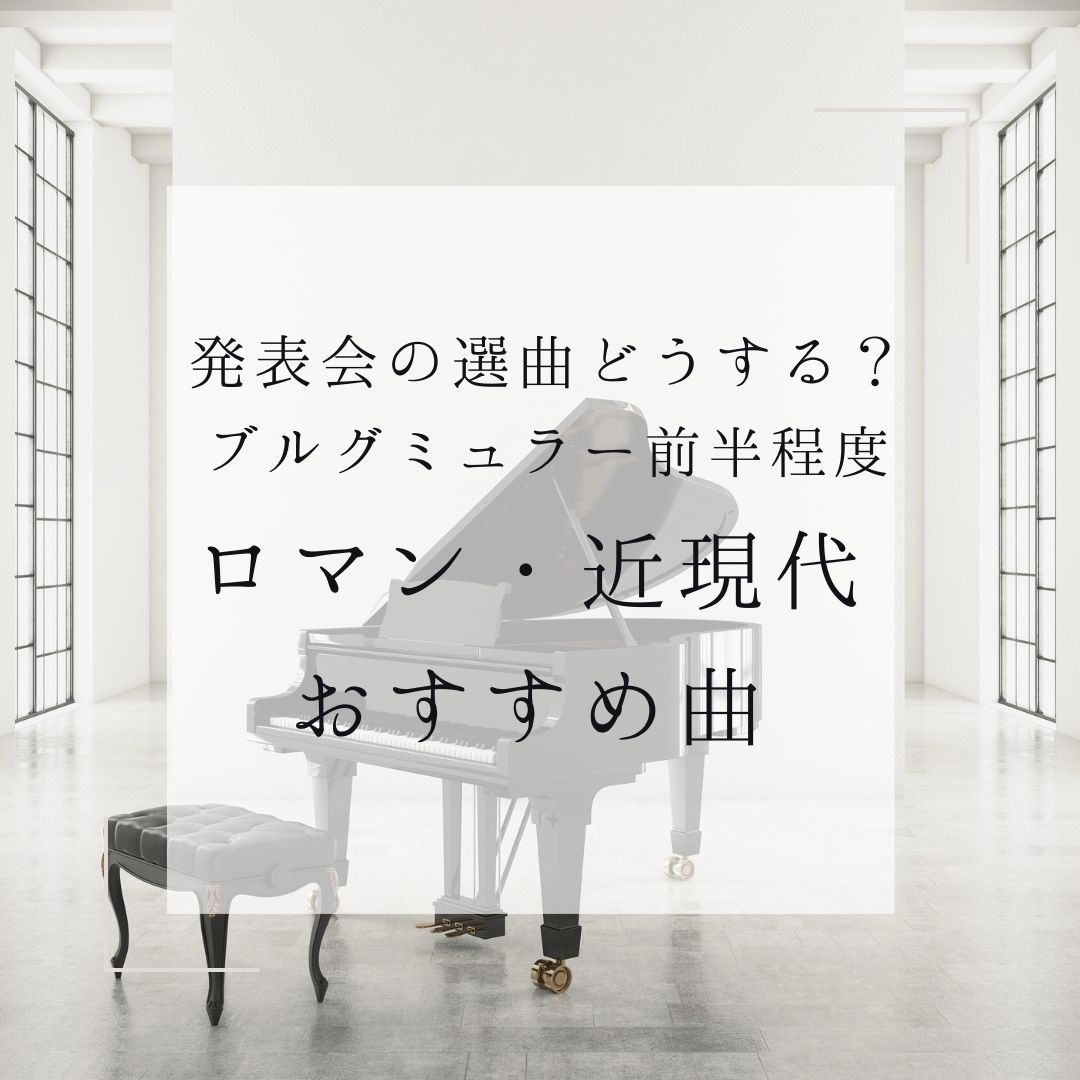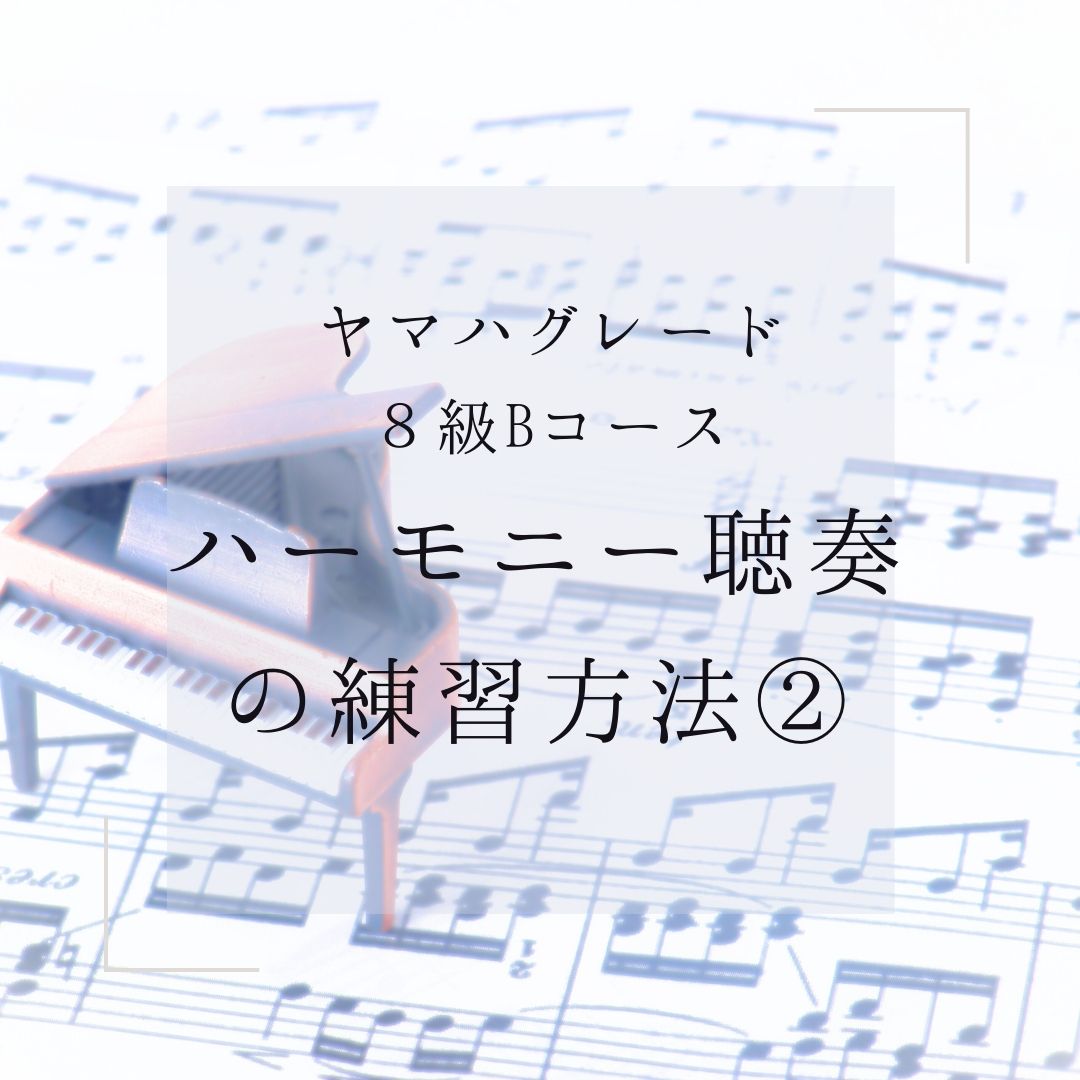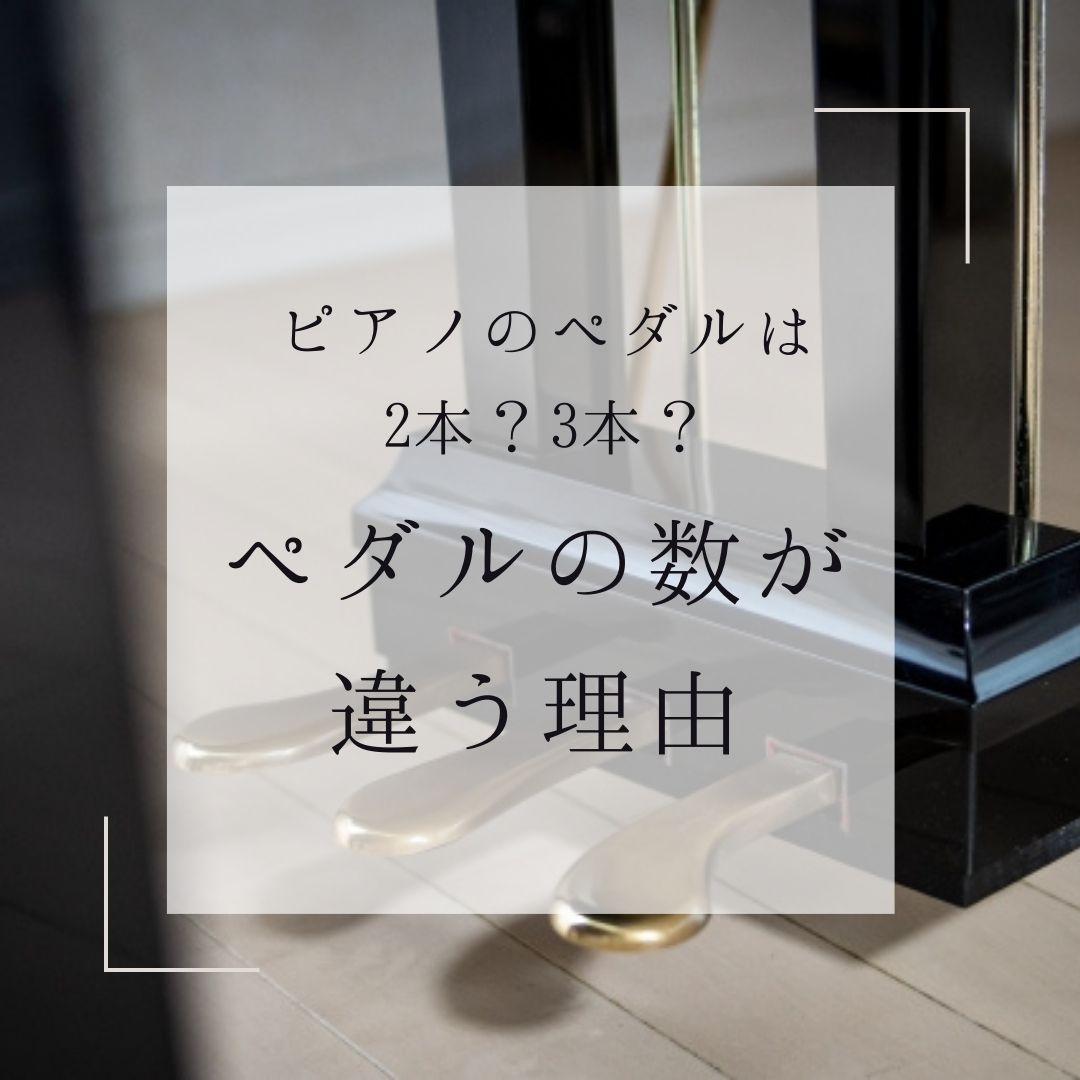子どもの習い事にもいろいろありますが、「スポーツもいいけど、音楽もさせたいな」と思うお母さんもいると思います。
「音楽をさせるならなるべく早い方がいい」 という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
今回は私の経験から、 音楽教育を早くはじめるといいという話は本当かどうか を検証してみたいと思います。
音楽は早期教育がいい

ピアノや歌、バイオリン、フルートなど音楽教育といっても選択肢が幅広いですね。その中でももっとも多いのがピアノではないでしょうか。
音楽教育を早期にはじめることで、どんな効果があらわれてくるのでしょう?いくつか考えられることをご紹介します。
音感がつきやすい
音楽の早期教育での一番のメリットといえば、音感がつきやすいことです。
音感がつくかどうかは 人間の耳の発達ととても大きく関係しています。
このことに関してはこちらの記事を参考にしてくださいね。
⇒絶対音感をつけたい!何歳までに訓練をしないといけないの?
⇒7歳までにに身につけたい!絶対音感のトレーニング方法とは?
こちらの記事では、7歳までに音楽教育を開始すると絶対音感がつきやすいということをご紹介しました。
確かに人間の耳の成長が止まる7歳というのはひとつの目安かもしれませんが、7歳ぎりぎりで音楽教育をはじめるより、 もっと前からはじめたほうが絶対音感を身につけられる確率は高くなるでしょう。
実際に小学生より年長さん(5歳)、年長さんより年中さん(4歳)からはじめた子どものほうが、より確かな音感が定着しているように感じます。
音符を感覚的に覚えられる
小学生くらいになると知的理解がどんどん進んでいきます。ですから「感覚的」ではなく「論理的」にものごとを考えるようになってくるのです。
幼児期の子どもは、大体が「感覚的に」「直感で」インプットし、アウトプットしていきますね。
ですから 幼児期の子どもは、五線の音を読むのもいちいちドから数えたりはしません。
ト音記号のこの部分にあるのがドで、この辺にあるのがソ・・・というように、五線に書かれた音をそのまま覚えてしまうのです。
音読みが早いと、楽譜を自分で読むことも早い時期にできるようになりますよ。
「感覚的に」五線の音を覚えさせたいなら、おんぷカードがおすすめです。併せてリズムカードも使うと効果的ですよ。
人前で何かすることに抵抗がなくなる
音楽教育を幼児期からおこなっていると、発表会やコンクールに参加する機会も多くなりますね。
例えば4歳でピアノをはじめたとして、小学6年生までに毎年発表会に出るとすると、人前で演奏する機会が8回あることになります。
そのほかにコンクールや学校の伴奏などもするようになると、その回数はもっと増えるでしょう。
小さいうちから人前で演奏するということは、緊張など感じないうちからステージに立つことになります。
なにがなんだか分からないうちからステージに立っていると、人前で演奏することが当たり前という感覚になるのでしょうね。 これが大切なんです。
幼児期からたくさんステージに立たせることで、度胸もつきますしプレッシャーにも強くなります。 これは演奏だけでなく、学校で発言したり受験の面接でこたえたりする際も活きてくることです。
実際に幼児期からステージで演奏している子どもと、小学校高学年からはじめてステージに立つ子どもを比べてみると、度胸の差がはっきり表れます。
それでも「ステージで緊張してしまう」という人は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
⇒ピアノの発表会・コンクールで緊張する人に試してほしいこと
⇒ピアノの発表会で緊張をコントロールするには?
まとめ
いかかでしたか?
音楽教育を早期におこなうことはいくつかのメリットがありましたね。
小学生より幼児期に音楽教育をおこなったほうが、成長や定着が大きなものになる傾向がありますが、なかには小学生からはじめて急成長するような子どももいます。
でも、もし子どもに「音楽教育を受けさせたいけど、小学生になってからでいいかな」と考えているのなら、少し考え直してほしいですね。
この記事を書いた人
-
はじめまして、nabecco(なべっこ)です。
のんびり田舎ぐらしをしながら、自宅でピアノ&エレクトーン講師をしています。
生徒時代は練習嫌い・劣等生だった経験を活かし、そんな人でも楽しく音楽を学べるような記事作りを心がけています。
主婦目線での子育て情報も。
最新の投稿
 資格2024-04-18ピアノ経験や音楽好きをアピールできる!おすすめの資格
資格2024-04-18ピアノ経験や音楽好きをアピールできる!おすすめの資格 ピアノ2024-04-171の指(親指)で黒鍵を弾いてはいけない理由と指導法~導入期のピアノ~
ピアノ2024-04-171の指(親指)で黒鍵を弾いてはいけない理由と指導法~導入期のピアノ~ ヤマハグレード2024-04-09ヤマハ学習者グレードを取る意味《メリット・デメリット》も紹介
ヤマハグレード2024-04-09ヤマハ学習者グレードを取る意味《メリット・デメリット》も紹介 ヤマハグレード2024-04-02【ヤマハグレード10~8級Bコース】メロディー聴奏のコツと練習方法
ヤマハグレード2024-04-02【ヤマハグレード10~8級Bコース】メロディー聴奏のコツと練習方法